米持 友加利
第一章 はじめに
声を模倣する楽器としてシンセサイザーやボーカルソフトウェアなど、今までさまざまな楽器が開発されてきた。その中でも、一際注目を集めているのがCRYPTON社のボーカルソフトウェア「キャラクター・ボーカルシリーズ01初音ミク」(図1)である。ニコニコ動画から始まり、今や、ゲーム、ライブまでこなしてしまう「彼女」の魅力とは何なのだろうか。本稿は、この〈初音ミク〉というボーカルソフトウェアが、「機械」にも関わらず、バーチャルアイドルと呼ばれるまでなったその人気の要因について、先行論文を参考にしながら、多角的に分析していく。それによって、今まではっきりとすることのなかった〈初音ミク〉の人気の要因を、総合的に見て一つの結論に導くことを目的としている。さらに、〈初音ミク〉に対する否定的な意見にも言及することで、より深く「彼女」の人気について考察していきたい。
〈初音ミク〉は、二〇〇七年八月三十一日に、YAMAHA社が開発し、CRYPTON社から発売されたボーカルソフトウェアである。このYAMAHA社が開発したボーカルソフトウェア=〈VOCALOID〉であるが、初音ミク以外にも何種類か発売されている。しかし、その中でもこの〈初音ミク〉は異例の売れ行きを示している。その理由は何なのであろうか。そのような所から話を始めていきたい。
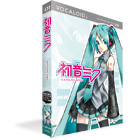 図1
図1第二章 〈初音ミク〉の変遷
第一節 〈初音ミク〉と他〈VOCALOID〉
他の〈VOCALOID〉については大きく〈初音ミク〉発売以前、〈初音ミク〉発売以後に分けられる。まず、〈初音ミク〉発売以後、〈初音ミク〉の発売以後も〈VOCALOID2〉シリーズとして、〈鏡音リン・レン〉、〈巡音ルカ〉、また、株式会社インターネットから〈がくっぽいど〉、〈めぐっぽいど〉などが発売されてきた。しかし、〈初音ミク〉ほど売れていないように感じるのは、恐らく〈初音ミク〉が初めて世間一般で人気が出た〈VOCALOID〉であるため、〈VOCALOID〉を使って作品を発表したい新規参入者にとって、一番消費者(ここでは、初音ミク作品を視聴して消費する人を指す)に、自分の作品を見つけてもらいやすいと考えるのではないだろうかという風に考えることで、説明できると思われる。
上記で説明した〈初音ミク〉発売以後の〈VOCALOID〉と〈初音ミク〉の関係より、本稿が今焦点としたいのは〈初音ミク〉発売以前の〈VOCALOID〉が何故〈初音ミク〉のような人気を獲得し得なかったのかということである。
〈初音ミク〉発売以前1、これには、二〇〇四年発売の女性ボーカルソフトウェア〈MEIKO〉(図4)、二〇〇六年発売の男性ボーカルソフトウェア〈KAITO〉(図5)が挙げられる。今でこそ〈初音ミク〉とともに〈VOCALOID〉というキャラクターとして、親しまれている〈KAITO〉と〈MEIKO〉だが、発売当初は世間一般には知られていなかった。〈MEIKO〉はDTMソフトとしては異例のヒット商品であったもののDTMを扱う人たちの購入にとどまっており、また〈KAITO〉に至っては、売り上げが長い間伸び悩んでいた。しかし、〈初音ミク〉の人気とともに改めて注目され、売り上げを伸ばしていったのである。
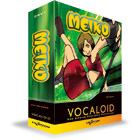 図4
図4
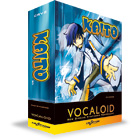 図5
図5では、〈初音ミク〉が世間一般に広まり人気が出たのに比べ、〈KAITO〉や〈MEIKO〉達のそれほどの人気が出なかったのは何故なのか。それには三つの要因が考えられる。第一は〈KAITO〉と〈MEIKO〉は、パッケージにマンガ的なイラストが描かれていたとはいえ、キャラクター性を前面に押し出した商品ではなかったこと、次に若干〈初音ミク〉が〈KAITO〉〈MEIKO〉に比べ安価であったこと、最後に〈初音ミク〉爆発的な人気に貢献した〈ニコニコ動画〉2がまだ設立したばかりであったということ。
〈KAITO〉〈MEIKO〉に比べ、〈初音ミク〉が爆発的な人気を誇った要因として考えられるのは、このような点であると筆者は考える。ニコニコ動画と〈初音ミク〉の人気との関連性、キャラクター性など、いきなり言われても、訳が分からない方が多いと思われるので、次の章から詳しくニコニコ動画と〈初音ミク〉の関連性や〈初音ミク〉の持つキャラクター性について言及していきたい。
第二節 動画サイトと〈初音ミク〉の関係
〈初音ミク〉はニコニコ動画とともに日本のCGM(インターネットなどを活用して消費者が内容を生成していくメディア)シーンを形成していった代表的なものといっても過言ではない。また、〈初音ミク〉はニコニコ動画から抜け出し、今や様々なメディアに展開されている。楽曲のCD化は勿論、イラスト、アニメーション、3Dムービー、ゲーム、3Dホログラムを駆使したライブなど、公式二次創作問わず、発売から三年経った今でも、その勢いは衰えていない。
今でこそ様々なメディアに展開している〈初音ミク〉だが、やはり最初に人気を博した理由には、ニコニコ動画との関連性が高いのではないかと思われる。そこで、何故〈初音ミク〉は様々なジャンルの派生作品、二次創作で消費され人気を獲得したのか、その根本的な理由はひとまず置いておいて、後ほど言及していくことにし、ここでは、ニコニコ動画との関連性に注目して〈初音ミク〉の人気が出た理由について述べていきたい。
ニコニコ動画と〈初音ミク〉の関連性に関しては、情報環境研究者の濱野智史氏の考察3を基に述べていきたいと思う。
ニコニコ動画がサービスを開始する以前も、同じような動画サイトYouTubeは存在していた。実際、初代VOCALLOID〈MEIKO〉を使った動画もYouTube上にアップされていたようである。しかし、結果としてYouTube上では〈MEIKO〉は〈初音ミク〉ほどのブームを起こすには至らなかった。では、〈MEIKO〉に関する理由がネックで人気に至らなかったのであろうか。〈初音ミク〉が登場したときに、もしもニコニコ動画がなかったら、YouTube上で〈初音ミク〉は今のような人気を持ちえたのか。この問いに濱野氏は「その可能性は低かったように思われる」と述べている4。そういえるのは何故なのか。その理由について言及する前にYouTubeとニコニコ動画の差異について述べておきたい。
YouTubeとニコニコ動画の差異をオープンソースやウイキペディアとの類似点に注目して、濱野氏は指摘している。まずニコニコ動画上では、
①不特定多数のユーザーがコンテンツの協働制作プロセスに関与することで、②しだいにコンテンツ(生産物)の質が改善されていき、③その結果、製作されたコンテンツはユーザーの間で共有され、他のコンテンツの素材(二次創作の対象)にもなっていくというサイクル
が見られる5。また、それがオープンソースやウイペディアになぜ類似しているのかということについて、濱野氏は以下の三つの点を上げている。一点目は「コラボレーションの「組織形態」」すなわち今までのピラミッド型の組織とは異なり、ネットワーク型の組織形態でコラボレーションが行われているということ、二点目は「コラボレーションによって「生産される財の性質」」すなわち、今までとは異なり「常に製品の質をネットワーク経由で改善できる」というソフトウェアの性質、三点目は「そのコラボレーションの結果生み出された「財の所有形態」」すなわち、参加者の中でその財が誰の所有にも属さない共有のものとして扱われていくことである6。
上述したオープンソース的現象はYouTubeには見られないと濱野氏は指摘している。 何故なら、オープンソース的現象が起こるには客観的評価基準が必要であるからである。YouTube、ニコニコ動画などの動画サイトでアップロードされ、消費されていく作品群は、音楽、映像などの評価が主観に頼らざるを得ないコンテンツで、客観的な評価基準を得にくい。しかし、ニコニコ動画にはオープンソース的現象が見られ、YouTubeには、それが見られなかった。この二つの動画サイトの違いを濱野氏はニコニコ動画のコメント機能に絡めて説明している。ニコニコ動画とYouTubeの明らかな違いとは何か。両方のサイトを思い浮かべてみて、真っ先に思いつくのは動画上にコメントが流れるか否かである。YouTubeにはコメント機能はあるものの、ホームページの掲示板のようにページ上にコメントを残すという機能しかない。一方、ニコニコ動画にはユーザーが動画上の好きな場所(時間)にコメントを残せるという機能がある。つまり、ニコニコ動画はこの機能によって、視覚的に、どの程度の人たちがこの動画を評価しているのか、また、動画のどの部分がより盛り上がっているのかということがわかるようになっているのである。この他の動画サイトにはない機能の働きで、ニコニコ動画は客観的評価基準を得て、オープンソース的現象が起こることとなったのである。
さて、ここで本題に入りたい。何故、〈初音ミク〉がニコニコ動画上でブームを起こし、これほどまでのブームになったのか。それは、上述したオープンソース的現象によって、他の動画サイトでは見られない「N次ポップの連鎖」が起こったからである。他の動画サイトでは、二次創作作品は「一つの元ネタ(一次ポップ)に大量の派生作品がぶら下がっている状態」に留まっていた。しかし、オープンソース的現象の起こったニコニコ動画、主に初音ミクの作品に関しては「「元ネタ→派生作品(元ネタ)→派生作品……」というように、ある派生作品がまた別の派生作品にとっての元ネタになっていくという「N次ポップ連鎖」」が起きた7。これによって様々な派生作品が作られ、〈初音ミク〉は爆発的に広まっていったのである。
第三章 様々な観点から見た〈初音ミク〉の魅力
第一節 〈初音ミク〉というキャラクター
先ほどの章ではニコニコ動画という〈初音ミク〉が花開いたコンテンツに交えて、「彼女」の人気について語ってきたが、次からはもっと根源的なところについて言及していきたい。ここからは主に雑誌『ユリイカ』の初音ミク特集8の記事を参考にしてまとめていきたい。
まず、〈初音ミク〉を構成する主な要素は大きく二つに分けられる。それは、声とキャラクターである。〈初音ミク〉の人気を語る上で取り上げられるのは、声の魅力よりもむしろ、そのキャラクターの方である。ボーカルソフトウェアは、その名の通り、声が商品の中心である。それにも関わらず、〈初音ミク〉の人気の要因はキャラクターであると言われている。それは何故なのであろうか。その答えはUG-K氏9も述べていたように「自由度の高さ」にあるのではないだろうかと筆者は考える。
〈初音ミク〉の本来の役目は女性ボーカルの代替である。しかし、それ以上にキャラクターが数多のアマチュアによる音楽、絵画、動画作品のモチーフ、所謂二次創作のモチーフになることで大きな人気を得ている。二次創作の〈初音ミク〉は、多種多様で公式とは全く違うものに見えるものが多い。様々な姿を見せる二次創作の〈初音ミク〉は何故〈初音ミク〉として捉えられるのだろうか。それは〈初音ミク〉がいくつかの特徴的な要素の集合体として捉えられているからではないだろうか。例えば、緑色長髪のツインテールや印象的な衣装、またその声、これらの要素の集合体として〈初音ミク〉は認識されているように思える。また、その要素のいくつかがあればそれは〈初音ミク〉として認識されるのである。
パーツのいくつかがあれば〈初音ミク〉として認識されるという点についての具体例に、「ブラック★ロックシューター」10という作品をあげたい。「ブラック★ロックシューター」(図6)はイラストレーターhuke氏が描いたオリジナルキャラであり、同時にそれに付随してryo氏が制作発表した楽曲でもある。この「ブラック★ロックシューター」の楽曲は、huke氏のイラストに感銘を受けたryo氏が初音ミクを用いてその世界観を表現した楽曲である11。huke氏が制作したアニメーションと共に楽曲を流すという体で、二〇〇八年六月にニコニコ動画上で発表された。ここでのアニメーションは当然huke氏のオリジナルキャラ「ブラック★ロックシューター」が出演している。しかし、この「ブラック★ロックシューター」がツインテールという〈初音ミク〉と同じ要素を持っており、なおかつ、初音ミクの楽曲と合わせられたことにより、動画の視聴者が「ブラック★ロックシューター」を初音ミクの派生キャラだと勘違いしてしまうという事件が起きた。これは、〈初音ミク〉と認識される「声」と「ツインテール」という要素が合わさってしまったために、視聴者の勘違いを誘ってしまった例であると考えられる。
このように、構成要素のいくつかがあれば、それは〈初音ミク〉と認識されてしまう可能性がある。別の言い方をすれば、構成要素を自由に切り貼りできる「自由度の高さ」があるとはいえないだろうか。
また、〈初音ミク〉のキャラクターを語るにあたって、設定の簡素さについても言及したい。
CRYPTON社公式サイト12に記述してある〈初音ミク〉の設定は非常に簡素なものである。まずボーカルアンドロイドであること、年齢、身長、体重、得意な歌のジャンル、テンポ、音域、これらのみである。また、KEI氏によって描かれたイラストも数点しか公開されておらず、その立ち絵も背景は空白で満たされている。このように「初音ミクというキャラクターは内面と背景を注意深く排除した人形としてユーザーの前に現れるようによく調律されている」とさやわか氏は記事内で述べている。そのため「ユーザーは背景を持たない人物像を見て、さながらセル画の後ろに背景画を重ねるようにして初音ミクというキャラクターを自分の好みの世界に生かすことができる」のである13。確かに二次創作の中での〈初音ミク〉は様々な世界に存在しているように感じられる。ある時は現代で生きることの辛さを歌ったり、パソコンの中からマスター14に対する恋心を歌ったり、ファンタジーの世界での御伽噺を語ったり、〈初音ミク〉は「どのような物語でも受容できる白紙の存在」15として私たちの前に現れているのだ。これも「自由度の高さ」として指摘できるのではないだろうか。
ここまでは〈初音ミク〉のキャラクターについての「自由度の高さ」について言及してきた。しかし、〈初音ミク〉はキャラクターと言う要素以外にも、自由度という可能性を秘めているように筆者には感じられる。
第二節 〈初音ミク〉と「データベース消費」
この〈初音ミク〉に関する「自由度の高さ」に付随して、東氏の「データベース消費」という考え方16について言及しておきたい。
東氏は雑誌『ユリイカ』の「初音ミクと未来の音」内で、「初音ミクの消費のされ方はデータベース消費そのもの」と語っている17。「データベース消費」とは、「単純に作品を消費することでも、その背後にある世界観(大きな物語)を消費することでも、更に設定やキャラクター(大きな非物語)を消費することでもなく、さらにその奥にある、より広大なオタク系の文化全体のデータベースを消費すること」18である。
〈初音ミク〉の消費のされ方が「データベース消費そのもの」であると東氏が述べるのは何故なのか。それは上述した「構成要素」が関係していると考えられる。「九〇年代のオタクたちは一般に、八〇年代に比べ、作品世界のデータそのものには固執するものの、それが伝えるメッセージや意味に対してきわめて無関心である。逆に九〇年代には、原作の物語とは無関係に、その断片であるイラストや設定だけが単独で消費され、その断片に向けて消費者が自分で勝手に感情移入を強めていく、という別のタイプの消費行動が台頭してきた。」19〈初音ミク〉がボーカルソフトウェアとして以上に、キャラクターとして人気を博した理由はここにある。物語より断片=構成要素を消費することがスタンダードになりつつある現代では、消費者側の受け取り方次第で如何様にもそのキャラクターを変化させることが出来る。それ故に〈初音ミク〉はこんなにも人気が出たのである。つまり、物語より断片=構成要素を消費されているという面で〈初音ミク〉は「データベース消費」そのものと言えるのではないか。
また、〈初音ミク〉は二次創作が活発である理由も、この「データベース消費」に関わるところがあると考えられる。現在、「作品はもはや単独で評価されることがなく、その背後にあるデータベースの優劣で測られる。そしてそのデータベースはユーザー側の読み込みによっていくらでも異なった表情を現すのだから、ひとたび「設定」を手に入れてしまえば、消費者はそこから原作と異なった二次創作をいくらでも作り出すことが出来る」のである20。
〈初音ミク〉は「データベース消費」によって消費されている。例えば、「アンドロイド」という設定、これは人に限りなく近いことの苦悩などをよく描かれるモチーフであり、作品でよく描かれる要素である。また、見た目の面だと「ツインテール」は記号化された萌え要素と言っても差し支えないのではないだろうか。製作者側としては、人間に限りなく近いがアンドロイドである、つまり機械であるという事実を埋めるためにキャラクター要素を付け加えた。しかし、そのキャラクターが所謂萌え要素を持つものだったため、「データベース消費」的に消費者、創作者に消費されていったのである。
〈初音ミク〉は、このように世の中が「データベース消費」をするように変化していたからこそ、人気が出たと考えられる。〈初音ミク〉の「自由度の高さ」も「データベース消費」という素地がなければ、全く役に立たず、人気もそこそこに留まっていたのではないだろうか。その点で「データベース消費」と〈初音ミク〉は密接な関係性にあると言える。
この節では主に「データベース消費」と〈初音ミク〉の関係性について言及してきたが、次の段落からは、〈初音ミク〉を取り巻く環境から、〈初音ミク〉の「自由度の高さ」という魅力について考察していきたい。
第三節 〈初音ミク〉を取り巻く環境
〈初音ミク〉を消費しているのはどのような人間だろうか。それは大きく二つに分けられるのではないだろうか。まず、[創作者]、つまり、〈初音ミク〉を使って、歌や動画、イラストなどを作り、発表する人間、次に[消費者]、[創作者]が作った作品、及び、〈初音ミク〉というキャラクターを消費する人間、この二つに分けられると考えられる。この二つの視点から、〈初音ミク〉の自由度の高さについて論じていきたい。
始めに〈初音ミク〉の人気の要因のひとつとして、〈KAITO〉〈MEIKO〉に比べ安価で売り出された点を挙げた。[創作者]視点で考えると、この点は他の点に比べても非常に魅力的であると考えられる。普通、同人音楽21で歌が入っているものを作るとき、〈初音ミク〉のようなボーカルソフトウェアを使うのでなければ、歌い手に依頼するのが一般的である。しかし、音楽を作る〈創作者〉に比べ、歌い手の方が圧倒的に少ないという事実がある。また、更にその少ない中の優秀な歌い手に依頼が殺到するという状況が続いており、その活発な活動を続けるうちに、有名になった歌い手への依頼料は同人の範囲に収まらないほどの高額になることも少なくない。そのような状況から、新規参入しづらかった同人音楽に安価で参入できるきっかけをもたらしたということも、〈初音ミク〉の人気の要因である。また、安価で購入できるようになったことにより、音楽の用途に使う人たちだけでなく、他の層の人気も獲得したという事実も見逃せない。
では、〈初音ミク〉はどのような層の人気を獲得したのだろうか。その答えについては増田氏の論文22を参考にして言及していきたい。
増田氏は〈初音ミク〉ブームの原動力はある欲望であると述べている。その欲望とは「「自分の作品」としてソフトウェア「初音ミク」の声素材を用いるよりも、キャラクター〈初音ミク〉を仮構しつつ「歌わせてみたい」」という欲望である23。その欲望がブームの原動力になっているという証明に、増田氏は〈初音ミク〉作品が〈初音ミク〉の図像を伴っていること、また「作者たちの多くは「~P」24という名を名乗り、自らが制作した事実を強調するよりも、〈初音ミク〉という虚構のキャラクターを「プロデュースする」という擬制を採用」25している事実を指摘している。
上述した音楽を制作したいという層の目的、つまり、「創作労力の節減により、ユーザーのコントロールできる音素材を拡大」26するという本来の目的とは違う、この欲望を持った層の人気をも〈初音ミク〉は獲得したのである。
このように、この欲望を持った層に消費されることによって〈初音ミク〉はブームになったと考えられる。では、この〈初音ミク〉を歌わせてみたいという欲望を持った層の[創作者]はどのように〈初音ミク〉を消費しているのだろうか。
ニコニコ動画を見てみると、〈初音ミク〉というソフトは実に色々な使われ方をしていることが分かる。歌を歌うのは勿論のこと、小説の朗読や寸劇に使われていることもある。〈初音ミク〉は上述した通り、本来音楽創作の支援のためのソフトウェアである。小説の朗読や寸劇に使う目的では作られていない。しかし、安価で〈初音ミク〉が発売されたことにより、〈初音ミク〉をキャラクターとして消費する新しい層の[創作者]が参入できるようになり、彼らが音楽以外の「ワンアイディアで暴力的に使うことができる飛躍」27を〈初音ミク〉に見出したのである。
また、音楽を制作したいという欲望を持った層から見た〈初音ミク〉の「自由度の高さ」についても考えてみたい。
先ほど、生身の人間である歌い手に依頼せず、〈初音ミク〉を使用することにより、安価で音楽創作活動ができるという利点は、先ほど述べた通りである。また、他にも生身の人間より指示が出しやすいという利点もあるように感じられる。人間であれば、意見に食い違いが起こることもないとは言えないだろう。また、人によって感覚の違いがあるため創作者の細かなニュアンスが伝わりにくいこともあると考えられる。その点〈初音ミク〉は、生身の人間ではなく、ソフトウェアであるため、意見の食い違いは起こらず、細かなニュアンスも[創作者]の納得がいくまで調教することによって、表現することが出来る。
他にも歌い手にはない〈初音ミク〉ならではの魅力として、人間では歌いにくい歌詞音域を歌いこなせることも挙げられる。
人間では歌いにくい歌詞音域を歌いこなせることは〈初音ミク〉の楽曲を多少知っている人なら、知っているのではないかと思う。「最高速、最高圧縮の別れの歌。」と投稿者コメントにある通り、人間では不可能ではないかと思えてしまうほど高速な部分がある『初音ミクの消失』28、またサビで高音が続く『メルト』29、そのような、人間では歌いにくい歌も〈初音ミク〉は歌いこなしてしまう。
このように、[創作者]の観点から〈初音ミク〉の魅力について考えても、やはり「自由度の高さ」が大きく関連しているように考えられる。歌わせたい欲望を持った[創作者]が参入することによって、歌以外の使い道が見出されたこと、つまり、上述したように、歌以外にも小説の朗読寸劇、様々な用途に使えることや、また性能的な面でも人間では歌いにくい歌詞音域を歌いこなせることなどから、そのことが指摘できると考えられる。
さて、今までは[創作者]の視点から〈初音ミク〉の魅力について言及してきたが、次は[消費者]の視点から〈初音ミク〉について考えていきたい。
「「初音ミク」は「歌」を育てるソフト」であり、「初音ミクというキャラクターを育てるソフト」とは、細馬氏の言葉である30。細馬氏は[創作者]側の視点で、この言葉を使っていたが、これは[消費者]側にも当てはまることなのではないだろうかと、筆者は考える。
創作するでもなく〈初音ミク〉というキャラクターを消費している[消費者]が、〈初音ミク〉というキャラクターを育てているとはどういうことなのであろうか。ここで、〈初音ミク〉の派生キャラ〈はちゅねミク〉(図7)にスポットを当てて言及していきたい。
この問いで、重要なのは先ほども言及した設定の簡素さである。上述したとおり、「彼女」に与えられた設定は、ボーカルアンドロイドであること、年齢、身長、体重、得意な歌のジャンル、テンポ、音域のみである。しかし、今CRYPTON社から公式に順ずる扱いを受けている設定がある。それは、「彼女」がネギを持っているという設定である。この設定の発祥は「VOCALOID2 初音ミクに「Ievan Polkka」を歌わせてみた」31という動画である。この動画は、元々二〇〇六年にYouTubeで話題になったFlashムービー「Loituma Girl」のオマージュとして作られた作品である。「Loituma Girl」がLoitumaの歌うフォークソング「Ievan Polkka」と、日本のTVアニメ『BLEACH』の登場人物、井上織姫がネギをエンドレスで回す映像を組み合わせた動画だったため、「VOCALOID2 初音ミクに「Ievan Polkka」を歌わせてみた」でも、二・五頭身の〈初音ミク〉=〈はちゅねミク〉がネギを回すアニメーションが用いられた。「とぼけた表情と歌を体現するかのような、間の抜けたネーミングセンスのはちゅねミクは瞬く間に大人気となり、元ネタにフィードバックされる形でミクの付属アイテムとして認知され」るようになったのである32。
皆が共通認識として持つことの出来る設定をキャラクターに付与する。これはキャラクターを育てるということに繋がるのではないかと筆者は考える。この[消費者]がキャラクターを育てることが出来るという点も〈初音ミク〉の人気の要因ではないだろうか。また、これも設定が簡素であった〈初音ミク〉だからこそ起こったことであり、その根本にはやはり「自由度の高さ」が関連していると考えられるのではないだろうか。
第四節 〈初音ミク〉と他キャラクター(他VOCAROIDと派生キャラクター)
〈初音ミク〉の人気を語るにあたって、他キャラクターは欠かせない要素の一つである。この節では、他キャラクターとの関連性から、〈初音ミク〉の自由度について言及していきたい。上述した通り、〈初音ミク〉は、キャラクターが数多のアマチュアによる音楽、絵画、動画作品のモチーフ、所謂二次創作のモチーフになることで大きな人気を得ている。それには、他キャラクターとの関係性も強く関連しているように、筆者には感じられる。「VOCALOID Leads Us to Future」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』第四十巻第十五号、二〇〇八)内で、有村氏は「女性ファンの想像力」が〈VOCAROID〉達の関係性を語る上で欠かせないと述べている。「女性ファンの想像力」とは何なのであろうか。有村氏の論文から引用して考えていきたい。
「女性のオタク全般に見られる傾向として、キャラクター個人(もしくはその属性)よりも、キャラクター同士の関係性――カップリングが萌えの対象になりやすい。たとえば初音ミクとマスターのカップリングを描く同人誌は多いが、非常に大雑把に分けるなら、ミクの性的魅力(具体的な性行為も含む)に注力するのが男性向けで、二者間の感情の交流を重視するのが女性向けであるといえる」33。つまり、「女性ファンの想像力」とは、キャラクター間に関係性を見出し、それに萌えられる力とでも言い換えられるだろうか。その「女性キャラの想像力」を発揮しやすい環境に〈VOCALOID〉はあったと言える。設定が簡素なためにキャラクターに自由に設定を付け加えられる〈VOCALOID〉達に、彼女たちは様々な関係性を容易に見出すことができるからだ。例えば「鏡音リン・レンは血縁上の関係はないものの初音ミクの妹分・弟分としてファンの間で扱われているが、レンは実の姉とされるリン、及び姉貴分のミクとの姉妹カップリングが成立するという、女性ファンにとって非常に「おいしい」ポジションにいる」34。また、他にも「MEIKOとKAITOの、アダルトな雰囲気を漂わせる年長カップリング。KAITOと彼を兄と慕うミクの兄妹カップリング。MEIKOとミク、あるいはミクとリンの姉妹百合関係。お互いを鏡に映したようなリン・レン姉弟の強い絆。」KAITOとレンのコンビ。「さらに、直截的なKAITOとレンのやおいカップリング。そして――五人の兄弟姉妹の、温かい関係」35と、有村氏が挙げただけでも多数のカップリングが存在している。また、最近では〈めぐっぽいど〉〈がくっぽいど〉が同じ株式会社インターネットから発売されているということで、既存の〈VOCALOID〉の関係性とは違うところで、兄妹関係に見立てられていたり、また、色気故か、曲などでコラボレーションすることの多い〈がくっぽいど〉と〈巡音ルカ〉のカップリングなどが増えてきていたりもする。どんどん増えていく〈VOCALOID〉ファミリーは、これからも関係性を持たせられ、「女性の想像力」によって消費されるのだろう。
〈初音ミク〉の自由度を語る上で、他〈VOCALOID〉との関連性以外にも、〈VOCALOID〉の〈派生キャラクター〉という存在があることも言及しておくべきであろう。
〈派生キャラクター〉とは、既存の〈VOCALOID〉をヒントに作られたキャラクターで、〈VOCALOID亜種(ボカロ亜種)〉とも呼ばれる。これらの〈派生キャラクター〉は、ベースの〈VOCALOID〉に共通する部分もあるものの、違った姿をしている。代表的なものだと、〈亞北ネル〉(図8)や〈弱音ハク〉(図9)などが挙げられる。これらはどちらも〈初音ミク〉の〈派生キャラクター〉で、「ある行動や心理を体現したキャラクター名を持っている」36。〈亞北ネル〉は「飽きた、寝る」から、〈弱音ハク〉は「弱音を吐く」からと言った具合である。このように〈初音ミク〉は、設定を自由に付け加えられる上に、その要素によっては〈初音ミク〉であり、〈初音ミク〉でないキャラクター=〈派生キャラクター〉になることも可能なのである。また、〈派生キャラクター〉には性転換をさせたもの(〈初音ミクオ 〉37など)までおり、これも、初音ミクの自由度を示唆していると考えられる。
このように、設定が簡素なためにキャラクターに自由に設定を付け加えられ、様々な関係性を容易に見出すことができるという〈VOCALOID〉の関係性に関する自由度や、その要素によっては〈初音ミク〉であり、〈初音ミク〉でないキャラクター=〈派生キャラクター〉になることができる自由度が、〈初音ミク〉にはあり、そのことも〈初音ミク〉の人気に一役買っていると言える。
第四章〈初音ミク〉に関する否定的な見解
第一節 〈初音ミク〉に関する欲望の相違
初音ミクが何故人気になったのかということについて、今まで言及してきたが、多角的に見ていくため、ここでは初音ミクに関するマイナス面や否定的な意見についても、少し触れておきたい。
初音ミクの消費の仕方に関する欲望について言及したときに、参考にした論文を書いた増田氏は〈初音ミク〉が苦手であると、雑誌「ユリイカ」の記事で述べている。同氏は、その理由に「「声」をめぐる、聴覚に還元できない位相での欲望の相違」38という点を挙げている。〈初音ミク〉ブームを引き起こした主要な欲望は、上述したとおり、「声の操作によって虚構の人格〈初音ミク〉を現実化させようとする志向」39である。しかし、「『初音ミク』の生成する音響は果たして「声」なのであろうか」40。この問いに、増田氏は「〈初音ミク〉の「声」として現象している音響は、音高と音価、日本語のコードによって分節された語彙をソフトウェアのユーザーが指定することによって生成された、徹底的に分節されたもの」であり、「そこには分節的なコントロールにあらがう実体、非分節的な「歌われる声に表れる身体」は存在しない」41と答えている。 つまり、〈初音ミク〉の「声」は身体をシミュレートする「声」ではなく、「音」なのである。それを踏まえ、「〈初音ミク〉の「歌声」を、歌声として、身体をシミュレーションするものとして聞くのではなく、単なる電子音響として聞く」と、「『初音ミク』の音響は別のものとして聞こえてくる。「声」に似た、何か不十分な身体の肌理のようなものを感じさせながらも、否応なくぎくしゃくした感覚を与える電子的な音響」=「人の身体の模倣に失敗した音」42に聞こえてくるのだ。「模倣に失敗した音」、例えば「テクノ」などの音楽ジャンルは元々の楽器の音と微妙にずれた音響を発するものを使うことで、ジャンルとして成り立っている。しかし、〈初音ミク〉は「模倣に失敗した音」をそれとして楽しむのではなく、その音響を「声」として聞き、楽しんでいる人が大多数なのである。その根本には先ほどの「声の操作によって虚構の人格〈初音ミク〉を現実化させようとする」欲望があり、その「音響を「声」として聞くことを強いる欲望」43に増田氏は違和感を感じているのだろうと述べている。
「不気味の谷現象」という言葉がある。人型ロボットなどの様態があまりにも人間に近いときに、見る者に違和感や嫌悪感を抱かせるとされる現象である。〈初音ミク〉並びに〈VOCALOID〉達は、今までのボーカルソフトウェアより、明らかに「人間」に近い。そして、「神調教」44というニコニコ動画でよく使われる賞賛の言葉からも分かるように、なるべく人に似ている方が良いとされる傾向にある。しかし、今の時点では、〈VOCALOID〉は、どんなに「人間」に近く聞こえても、それは「近い」だけであり、「人間」そのものにはなりえない。どんなに「神調教」だと賞賛される動画でも、その「声」には、どこか違和感が付きまとう。その「声」をそういうものである。〈VOCALOID〉は機械であり、音を表現する手段に過ぎないと考えるか、その「声」をキャラクターと結びつけ、「歌声」として消費していくか、はたまた、その「声」を聞く違和感に耐え切れず、避けて通るか。様々な見方があり、どう受け取るかは個人の自由であるが、〈初音ミク〉がどんなに人気であったとしても、否定派の存在もあるということは留意しておかなければいけない事実である。
第二節 〈初音ミク〉という「アイドル」
最近、バーチャルアイドルとして〈初音ミク〉を表現することが増えてきていると感じる。実際のところ、〈初音ミク〉は、ただのボーカルソフトウェアであり、そこに〈初音ミク〉という「アイドル」は存在しない。しかし、私たちの前に「アイドル」という存在として現れてきている。この節では、所謂今までの「アイドル」とバーチャルアイドル〈初音ミク〉の関係性について言及していきたい。
そもそも、今までの「アイドル」と〈初音ミク〉は何が違うのだろうか。また、何をもって〈初音ミク〉は「アイドル」と呼ばれているのだろうか。さやわか氏は、雑誌「ユリイカ」記事内で、CRYPTON社の佐々木氏の発言から、こうまとめている45。
人間のアイドル(特に最近の)だと、多かれ少なかれ生活感が見えたり、キャラクター性が固まってしまっていたりして、広がりに"制限"がかかってしまうというのだ。その点、純粋な"偶像"である初音ミクには、そういった制限がない。(…)佐々木氏は、キャラクター性が製品の役割を果たしたことを認識しながらも、「80年代のアイドルが持っていた"きれいな偶像性"みたいなニーズが、デジタルアイドルのミクによって掘り起こされたのではないか?」と指摘する。
つまり、両者は「きれいな偶像性」を持っている=「どのような物語でも受容できる白紙の存在」であるということでは共通しているが、「純粋な偶像」であるか、そうでないかが違っている。また、〈初音ミク〉は「ユーザーがインターネットで自給自足的に新たな物語を紡いでいける」のに対し、現実の「アイドル」は、「ファンが自由に物語を読み出すことができる」46だけである。この二つの「偶像」の違いは一見些細なものに見える。しかし、実際ここで例に出されている80年代のアイドルは衰退していき、〈初音ミク〉は、新しく人気を得た。それは、上述した「きれいな偶像性」に関係性があると考えられる。
「メディア上の物語として存在するアイドル」が、実際に綺麗であるかは本来不問にされるべきなのだが、実際にニュースなどになってしまうと「特定の物語(=現実)への接近によってアイドルの「きれいな偶像性」を損なわせ、ファンが自由に物語を読み出す障害となり得てしまうため許容しがた」47くなってしまう。 つまり、両者とも「きれいな偶像性」を持っているものの、今までの「アイドル」は、「きれいな偶像性」を壊してしまう可能性をはらんでいるという点が〈初音ミク〉とは違っているといえる。
実体を持っている「アイドル」は「きれいな偶像性」を壊してしまう可能性をはらんでいるため、実体のない「純粋な偶像」であるバーチャルアイドル〈初音ミク〉ほどの人気を持ち得なかった。では、実体のない「純粋な偶像」であるバーチャルアイドルというものは〈初音ミク〉以前には存在しなかったのであろうか。実は、バーチャルアイドルというものは、〈初音ミク〉以前にも存在していた。ラジオ内で誕生したアイドル「芳賀ゆい」である。さやわか氏の記事から引用すると、「芳賀ゆい」は、
一九八九年にラジオ『伊集院光のオールナイトニッポン』の企画によって誕生した」アイドルであり、「リスナーから募った架空のプロフィールをそのキャラクター設定とし、五十人以上という影武者を使ってCDのリリースや顔を隠した写真集の販売、コンサート、握手会などの活動を行った。 48
この「芳賀ゆい」は「実在のアイドルに「きれいな偶像性」が整備されないのであれば、自分たちで作った架空のアイドルにそれを求めようという運動」の結果、作られたものであり、「「実体をあくまで物語存在として楽しむ」という八〇年代のアイドル受容形態から「実体」をも取り外し、アイドルを巡る物語の一切をファンが自給自足」49することができる存在である。この物語を自給自足で紡げるという点において、「芳賀ゆい」と〈初音ミク〉は同じであると言える。しかし、「芳賀ゆい」も〈初音ミク〉ほどのブームを起こすことはできなかった。では、〈初音ミク〉にあって、「芳賀ゆい」になかったものとは何なのだろうか。その理由として、さやわか氏は、「安価で高性能な家庭用コンピューターやインターネットなどの情報技術」50が整備されていたこと、また、三章第一節で言及した構成要素を自由に切り貼りできる「自由度の高さ」故に、メディアレベルで同じことを実現することが可能であることを指摘している。
まず、最初の点について説明すると、「芳賀ゆい」は最終的にファンの意志をラジオ番組に集めて決定し、またその反映された結果はテレビや雑誌、CDの流通を待たなければ見ることができなかった。しかし、「初音ミクにおいてはマスメディアや商業流通が関与しなくともユーザー同士で新しい初音ミク像の創出と受容がスピーディーに行える」51ようになったため、これほどまでのブームを呼ぶことになったと言える。
また二点目は、その自由度故に構成要素が自由に切り貼りできるため、動画などでも〈初音ミク〉は同じように現れているということである。つまり、「我々が視聴する初音ミク作品のほとんどは、初音ミクの声の裏にどのような楽曲が流されるのか、その曲に対してどのような映像が付加されるのか、場合によってはその動画にどんな字幕が乗せられるのかを作者が恣意的に選んで結合させたマッシュアップ作品として現れていると言え」52。この二点が「芳賀ゆい」にはなかったのである。
ゼロ年代前半においてはモーニング娘。のようにオーディション番組などを用いたドキュメンタリータッチによって「現実」に偽装された虚構を提供しようとするアイドル像が主流となっていた。それは『イカ天』53以降に「リアルさ」が追及された九〇年代から連続したものだったが、Perfumeや初音ミクなどが人気を博するゼロ年代後半においては映像や音声などの諸要素をマルチレイヤー的に重ね合わせ極端な虚構性を築き、かつその代替可能性に自らを委ねるアイドルが台頭している。
と、さやわか氏はまとめている54。これからも、アイドル界には、このような代替可能性を持つ自由度の高い「アイドル」が活躍していくのだろう。
第三節 〈初音ミク〉の自由度に関する弊害
〈初音ミク〉名義のCDが発売される最近では、「初音ミク」が歌っているからこのCDを買うという人も増えたように感じられる。そのことに関する弊害も最近では起きているようである。
さきほど、〈初音ミク〉を筆者は「アイドル」と表現した。「アイドル」は虚構の存在であり、〈初音ミク〉は、現実には存在しない。実際には「きれいな偶像性」を持つ「アイドル」は「虚構」である。「虚構」であるが故に、諸要素の組み合わせで〈初音ミク〉が出来ているように、「アイドル」も、ある意味諸要素の組み合わせから成り立っていると言える。多くの場合、「アイドル」は「曲」を自分で作ることがない。つまり、「曲」と「アイドル」―その人自身という要素から「アイドル」は成り立っていると考えられる。
今、一般的にCDなどに大々的にクレジットされるのは、その歌を歌っている歌い手であり、作詞作曲者=「創作者」はそれほど目立つところにクレジットされない。それ故に、その「曲」は「虚像」である〈初音ミク〉の「曲」であると認識されてしまうという自体が起きるのである。その上、〈初音ミク〉の背後に存在する「創作者」が限りなく多いため、〈初音ミク〉は、個性を自由に変えることが出来るという特徴がある。
普通「アーティスト」55は、個性に寄って曲を作ったり、奏でたりしており、その個性故にファンがつくという側面があると考えられる。しかし、上述したとおり、〈初音ミク〉には曲を提供する「創作者」が限りなく多く存在するため、その「創作者」の個性の分だけの〈初音ミク〉が存在してしまうのである。数え切れない個性を持たされた〈初音ミク〉は、その数え切れない個性の分だけのファンを得てしまう可能性があるのだ。その個性は全て〈初音ミク〉自身のものではないが、「アイドル」のCDに「創作者」の名前が大々的に書かれず、その「曲」の可愛らしさが全て「アイドル」自身のものになるように、やはりその個性は〈初音ミク〉のものとして消費者にはとらえられてしまうのである。
では、そのことに何の問題があるのというのか。問題は、各々の個性を武器にして戦っていた「アーティスト」が〈初音ミク〉という個性が集まるプラットフォームにより、淘汰される危険性があるということである。
もちろん「アーティスト」は人で、声の面では、遥かに感情豊かで〈初音ミク〉より勝っている。しかし、個性的な「創作者」をバックホーンに持つ〈初音ミク〉が「アーティスト」達を脅かす可能性があるということは紛れもない事実である。
終章 終わりに
最後に、ここまでの文章を簡潔にまとめ、初音ミクの今後の可能性について触れたい。
「どのような物語でも受容できる白紙の存在」である〈初音ミク〉は、その特性故にコラボレーション、いわば、「彼女」を巡る様々な創作作品を誘発した。また、そのコラボレーションを誘発しやすい媒体であったニコニコ動画の設立から、ある程度時間が経過していたため、活発にコラボレーションが出来る状況が整っていた。また、「データベース消費」という素地が出来ており、その消費の仕方に〈初音ミク〉の特性が合致していた。そのような要因から、初音ミクはここまで爆発的な人気を誇ったのである。そして、その要因の根本には「自由度の高さ」があるのではないかと筆者には思える。また、〈初音ミク〉の「自由度の高さ」を指摘できる部分はまだ存在する。まず、他〈VOCALOID〉との関係性を自由に想像できること、その要素によっては〈初音ミク〉であり、〈初音ミク〉でないキャラクター=〈派生キャラクター〉になることができることなどが挙げられる。しかし、そんな〈初音ミク〉でも否定的な意見はやはり存在する。それには、音を声として聞くことに違和感を感じる層には受け入れられにくいということや、〈初音ミク〉が数多くの「創作者」の個性を持ちえることで、「アーティスト」達を脅かす可能性が出てきたということなどがある。
このように〈初音ミク〉が人気を持ちえたのは「自由度の高さ」故である。しかし、その「自由度の高さ」故の問題を生み出しているという事実も心に留めておかなくてはいけない。
「自由度の高さ」と言えば、初音ミクの声質を六倍に増やす拡張音源パック『初音ミク・アペンド(MIKU Append)』が、二〇一〇年四月に発売された。CRYPTON社公式サイト56によると「甘くささやくような[Sweet]、 大人びた声で哀愁の有る[Dark]、やわらかく優しい声の[Soft]、ハキハキと活舌の良い[Vivid]、シャープで緊張感のある声質の[Solid]、明るくあっけらかんとした張りの有る声質の[Light]の合計六種類。オリジナルの初音ミクの歌声と合わせると七色の声を使い分ける事が可能」になるらしい。公式サイトでそれぞれの声質の〈初音ミク〉を使用したデモ音源も公開されており、筆者も視聴したのだが、確かにどの声質も今までの〈初音ミク〉とは違った魅力を持っているように感じた。今まで〈初音ミク〉の魅力=「自由度の高さ」について言及してきた。今でも十分その「自由度の高さ」には驚かされるが、この『初音ミク・アペンド(MIKU Append)』は、今後も〈初音ミク〉が自由度を高めていくことが出来るという可能性を見せてくれたように、筆者には思える。
また、同じく二〇一〇年三月九日ミクの日に、株式会社セガが同社のリズムアクションゲーム「初音ミク -Project DIVA-」のイベント「ミクの日感謝祭 39's Giving Day」を開催し、〈初音ミク〉が3D映像でライブデビューを果たすという出来事があった。虚像だとしても二次元のキャラクターがライブデビューを果たすのは、初めてなのではないだろうか。〈初音ミク〉は初めてのことを成し遂げることが多いように筆者には感じられる。中田氏は雑誌『ユリイカ』「主体の消失と再生」という記事内で「合成された音声のなかにひとつの主体性を見いだそうという人々の集団実践は、初音ミクにおいてはじめて現れたものである」57と述べているが、それ以外にも技術的に画期的な方法を採用したこと、上述した虚像である〈初音ミク〉のライブデビュー、ボーカルソフトウェアを使用したCDでのオリコン一位獲得など、今までは「機械」が成し遂げることが出来なかったようなことも成し遂げている。また、これは初音ミクが初めてであるわけではないが、ネットはもちろん、ゲーム、音楽、キャラクターグッズ、漫画、様々なメディア作品に進出している。「自由度の高さ」を持つ〈初音ミク〉は、その「自由度の高さ」故に、様々メディア作品に対応することが出来るのであろう。ここにも〈初音ミク〉の可能性を感じざるを得ない。
その他にも、〈初音ミク〉に、札幌市の魅力を発信してもらうという協定を、札幌市と開発業者のCRYPTON社が結び、雪祭りで初音ミクの雪像を設置したり、海外のアニメ祭で初音ミクが札幌市を紹介したりしていくということがあったり、また、民主党議員が、選挙活動の「秘策」として〈初音ミク〉を使用しようとしたりしていたようだ。この計画は、どうやら「特定の政治団体のためには使えない」ということで、頓挫してしまったようだが、当初、〈初音ミク〉を使って候補者のプロモーションビデオ(PV)を作ろうとしていたらしい。このような話を聞くと、様々な方面で〈初音ミク〉の人気と可能性にあやかろうという需要が増加しているように感じられる。
また、最近では英紙で「地球上で最大のポップスター」と大々的に報じられ、「知名度が世界規模になってきた。開発・販売したクリプトン・フューチャー・メディアもそれを認め、ヨーロッパ、アメリカだけでなく、ロシア、南米にも人気が拡大しているという。今後は現地の要望に応え、コンサートの開催なども検討」58しているようである。そして二〇一〇年十月にはニューヨークとロサンゼルスのアニメフェスティバルでコンサートを開催し、ニューヨークでは約一五〇人収容の会場が満員となり、入りきれないファンが二〇〇人も出てしまった。そのため急遽「追加公演」まで実施したという話もある。また、海外のゲームショーにゲストとして呼ばれるなど、その人気と可能性は留まるところを知らない。「本物のミュージシャンよりもバーチャルな彼女の方が人気になっている」のでは、などとネット上では騒がれているようだ。
このように全国どころか全世界にその人気を拡大していきつつある〈初音ミク〉は様々な「可能性」に溢れている。これからも、〈初音ミク〉は、その可能性を一歩ずつ着実に現実化していくのだろう。例え、将来「彼女」に代わる「誰か」が現れてしまっても、「彼女」が私たちに残してくれた「歌」や「可能性」は、ずっと私たちの記憶に残っていくはずである。
注
-------------------------------
1.他にも〈初代VOCALOID〉として、〈LEON〉(図2)、〈LOLA〉(図3)などが挙げられるが、マンガ風のイラストパッケージになっていないなど〈初音ミク〉との関連性が低いように感じられるので、ここでは便宜上言及しないこととする。
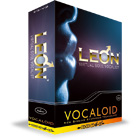 図2
図2 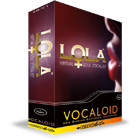 図3
図32.二〇〇六年十二月十二日設立
3.濱野智史『アーキテクチャの生態系 情報環境はいかに設計されてきたか』(NTT出版、二〇〇八)
4.前掲 『アーキテクチャの生態系 情報環境はいかに設計されてきたか』(二〇〇八、p247)
5.前掲『アーキテクチャの生態系 情報環境はいかに設計されてきたか』(二〇〇八、p248)
6.前掲 『アーキテクチャの生態系 情報環境はいかに設計されてきたか』(二〇〇八、p248)
7.前掲『アーキテクチャの生態系 情報環境はいかに設計されてきたか』(二〇〇八、p249)
8.『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号 青土社、二〇〇八)
9.UG-K「初音ミクの魅力とは 二〇〇八年の展開を振り返って」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八、p233)
10.初音ミクがオリジナルを歌ってくれたよ「ブラック★ロックシューター」〈http://www.nicovideo.jp/watch/sm3645817〉(2010/12/08 アクセス)
11.ブラック★ロックシューター supercell 〈http://supercell.sc/brs/〉(2010/12/08 アクセス)
12.クリプトン VOCALOID2特集 〈http://www.crypton.co.jp/mp/pages/prod/vocaloid/cv01.jsp〉(2010/12/08 アクセス)
13.さやわか「組み合わされる少女」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』第四十巻第十五号、二〇〇八、p184)
14.初音ミクというソフトを使用する人のことをこう呼ぶ。
15.前掲「組み合わされる少女」(二〇〇八、p185)
16.東浩紀『動物化するポストモダン』(講談社、二〇〇一、p78)
17.東浩紀・伊藤剛・谷口文和・DJ TECHNORCH・濱野智史『初音ミクと未来の音』(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八、p152)
18.前掲『動物化するポストモダン』(二〇〇一、p77~78)
19.前掲『動物化するポストモダン』(二〇〇一、p58)
20.前掲『動物化するポストモダン』(講談社、二〇〇一、p53)
21.自主制作の音楽
22.増田聡「データベース、パクリ、初音ミク」
23.『思想地図〈vol.1〉特集・日本 (NHKブックス別巻)』(日本放送出版協会、二〇〇八)
24.前掲「データベース、パクリ、初音ミク」(二〇〇八、p171)
「"P"はプロデューサー、あるいはプレイヤーの略。先行してブームになったアイドル育成ゲーム「アイドルマスター」(ナムコ 二〇〇五年)のプレイヤーネームの慣習を引き継いだものだと思われる。(前掲「データベース、パクリ、初音ミク」p175)
25.前掲「データベース、パクリ、初音ミク」(二〇〇八、p171)
26.「データベース、パクリ、初音ミク」(二〇〇八、p169~170)
27.田中雄二「初音ミクという福音」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八、p22)
28.初音ミクオリジナル曲「初音ミクの消失(LONG VERSION)」 cosMo@暴走P 〈http://www.nicovideo.jp/watch/sm2937784〉(2010/12/08 アクセス)
29.初音ミク が オリジナル曲を歌ってくれたよ「メルト」supercell 〈http://www.nicovideo.jp/watch/sm1715919〉(2010/12/08 アクセス)
30細馬宏通「歌を育てたカナリアのために」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八、p30)
31.「VOCALOID2 初音ミクに「Ievan Polkka」を歌わせてみた」〈http://www.nicovideo.jp/watch/sm982882〉(2010/12/08 アクセス)
32.有村悠「VOCALOID Leads Us to Future」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八、p215~216)
33.前掲「VOCALOID Leads Us to Future」(二〇〇八、p217)
34.前掲「VOCALOID Leads Us to Future」(二〇〇八、p217)
35.前掲「VOCALOID Leads Us to Future」(二〇〇八、p221)
36.「「ソワカちゃん」から「初音ミク」へ」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八、p176)
37.初音ミクの男性化として生まれた派生キャラクター
38.増田聡「初音ミクから遠く離れて」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八、p37)
39.前掲 「初音ミクから遠く離れて」(二〇〇八、p38)
40.前掲 「初音ミクから遠く離れて」(二〇〇八、p38)
41.前掲 「初音ミクから遠く離れて」(二〇〇八、p39)
42.前掲 「初音ミクから遠く離れて」(二〇〇八、p40)
43.前掲 「初音ミクから遠く離れて」(二〇〇八、p41)
44.ニコニコ動画の調教(声の調律)が上手いVOCALOID動画でよく見られるコメント。その多くは人間のようにナチュラルに歌っていることを賞賛するものである。
45.前掲「組み合わされる少女」(二〇〇八、p185)
46.前掲「組み合わされる少女」(二〇〇八、p186)
47.前掲「組み合わされる少女」(二〇〇八、p187)
48.前掲「組み合わされる少女」(二〇〇八、p187)
49.前掲「組み合わされる少女」(二〇〇八、p187)
50.前掲「組み合わされる少女」(二〇〇八、p188)
51.前掲「組み合わされる少女」(二〇〇八、p188)
52.前掲「組み合わされる少女」(二〇〇八、p190)
53.『三宅祐司のいかすバンド天国』というテレビ番組。素人がバンドを組んで作詞作曲し、ライブ活動で人気を拡大するというような番組。
54.前掲「組み合わされる少女」(二〇〇八、p191)
55.ここでは、人間で音楽創作・発表をしている人物、またはグループを指す。
56.「クリプトン・フューチャー・メディア(株)メディア・ファージ事業部」〈http://www.crypton.co.jp/mp/〉(2010/12/08 アクセス)
57.中田健太郎「主体の消失と再生」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八、p195
58.「「初音ミク」人気世界に急拡大 英紙は「地球上で最大のポップスター」(J-CASTニュース) - エキサイトニュース」〈http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20101027/JCast_79326.html〉(2010/12/08 アクセス)
〈他参考文献〉
冨田明宏「同人音楽の中に見る初音ミク」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク―ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八)
大杉重男「未クラシック、魅クラシック」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク―ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八)
円堂都司昭「Pの悲喜劇」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八)
石田美紀「「中の人」になる」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八)
白田秀彰「初音ミクの二つの身体」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八)
濱崎雅弘・武田英明『初音ミク動画はどうやって作られたか』(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八)
濱野智史「初音ミク、あるいは市場・組織・歴史に関するノート」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八)
小谷真理「ハルとミク」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八)
中森明夫「初音ミクと存在しないものの美学」(『ユリイカ十二月臨時増刊号 総特集初音ミク-ネットに舞い降りた天使』(第四十巻第十五号、二〇〇八)
「株式会社インターネット」
〈http://www.ssw.co.jp/index.html〉(2010/12/08 アクセス)
「ミクの日感謝祭 39's Giving Day 初音ミク -Project DIVA- 公式サイト」
〈http://miku.sega.jp/39/〉(2010/12/08 アクセス)
「セガ、「ミクの日感謝祭 39's Giving Day」を開催 「初音ミク -Project DIVA-」シリーズ最新作の発売日など、39の秘密を公開- GAME Watch」
〈http://game.watch.impress.co.jp/docs/news/20100310_353740.html〉 (2010/12/08 アクセス)
「「初音ミク」で選挙活動計画 「政治利用ダメ」で民主議員頓挫 (1-2) J-CASTニュース」
〈http://www.j-cast.com/2010/06/30069999.html〉(2010/12/08 アクセス)
「asahi.com初音ミク 札幌市とコラボするよ-マイタウン北海道」
〈http://mytown.asahi.com/hokkaido/news.php?k_id=01000001012030003〉(2010/12/08 アクセス)
〈図表〉
図1~5
前掲 クリプトン・フューチャー・メディア(株)メディア・ファージ事業部(2010/12/08 アクセス)
※図6~9は省略しました。