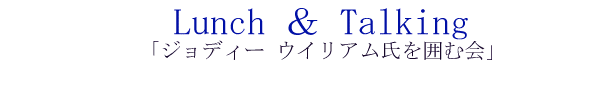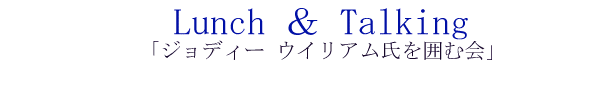


昨年11月、専修大学創立120周年記念フォーラム「21世紀への創造」に参加されたノーベル平和賞受賞者・ICBL国際大使 ジョディー・ウイリアムズ氏が以前このように語っていました。
「また訪問する時には専修大学を訪れたい。来年後半には来られると思う。学生など若い人達と話ができるのは、とても楽しみだ。」
この言葉通り今回この話は学長室を通じて望月宏ゼミに依頼が来た訳だが、趣旨から考えて経済学部全体に募集をかけることがふさわしいと判断し経済学部の学生全体に募集を募り学生と話し合う会を設ける運びとなりました。
日時は11月16日(火) 12:00から13:30ごろまで当日9号館で彼女を迎え入れた後、昼食を共にしながら地雷撤去、NGOの役割についてなどの学生の視点から和やかな雰囲気で話ができたらよいと考えております。
こうした経緯を経て無事に彼女との昼食会は和やかな雰囲気の中行われました。我々参加者は、偶然にもこういった機会に恵まれた者たちであり、この機会を大切に有意義なものにしたいという
思いから、何度ものミーティングを重ね、彼女との限りある時間を最大限に活かしすばらしいものにしようと取り組みました。
最初は、皆地雷問題に対する意識すら薄い状態でありましたが、勉強を重ねるたびにその関心は次第に「我々ができる国際貢献とは」、「我々にとって平和とは」などの
問題意識へと変わっていったのです。まずは、感激冷めやらぬ私達の昼食後の直の感想をお聞きください。
経済学部 国際経済学科 3年 河西 真祐美
1時間半というわずかな時間でしたが、昼食会を終えた後の私達は充実感、達成感でいっぱいです。
ジョディーさんとの昼食会の下準備「どうしたらジョディーさんが喜んでくれるだろうか
」「私達が学生として彼女に何をプレゼントできるだろうか」など何度も何度も話し合いをし、地雷問題や平和についてもディスカッションを重ねました。
そして本番当日、私達は心を弾ませながらジョディーさんを迎えました。ジョディーさんの気さくな語り、暖かい笑顔に私達が自然に溶け込み、自分達の素直な気持を伝えることができました。また会話の中で彼女のICBLに対する考え方、彼女の生の声、人柄を知ることができました。1つ1つの彼女からの投げかけが私達の胸に強く残りました。
そうして1時間半の充実した時間があっという間に終り、名残惜しい別れを迎えました。
このジョディーさんとの昼食会の経験を通し、地雷に関しての知識はもちろんですが、平和・国際貢献のために自分は何ができるかなど、彼女と出会ったことにより皆に大きな意識の変化がありました。この出来事は私達の胸に一生忘れられない思い出として残るでしょう。
「Think Global Act Local」の言葉のように今後1人1人が何らかの形で社会に貢献していきたいと思います。
最後に今回このような機会を与えて下さった学長室の方々を始め、関係者の方々すべてに感謝の気持でいっぱいです。本当に有り難うございました。
経済学部 経済学科 3年 安宅幸介
・ジョディ・ウィリアムスさんとの会談を終えて
ジョディウィリアムスさんとの会談を終えての感想ですが、当日の私はノーベル平和賞受賞者と話すことに非常に緊張していて頭が真っ白な状態で昼食会もあっという間に終わってしまったという感じだったので、正直な話、ジョディさんが何を話していたかぼんやりとしか覚えていないので、感想もまとまりのないものになると思います.
まず、ジョディさんとの会談で印象に残っていることは、彼女の人柄です.実際にお会いするまでは、ノーベル受賞者ということで厳格な人というようなイメージを持っていましたが、実際に会ってみると、実に気さくな方で、「日本の温泉は試されましたか」「八橋は好きですか」といった質問にも愉快に答えてくれて、自己紹介でも「私も学生時代に経済学の授業を履修したことがあるが、難しいので、当時は一生懸命勉強したが今となってはきれいさっぱり忘れてしまった」と言って経済学部の私達を笑わせてくれました.しかし、地雷廃絶運動の進め方・彼女の平和感などについて尋ねると、顔つきも変わって自分の意見を非常に明確に答えてくれました。そんな彼女の、普段は気さくだがいざと言うときには自分の意見を相手が納得させるほどしっかり述べるという、人柄にまず惹かれました.
また、ジョディさんの生き方にも強く惹かれました.会談の中で彼女は「Life is challenge」と言ってくれましたが、彼女自身今まで自分の信じる道へ精一杯生きてきた方だけあって、その言葉は真実味があり、私にもこれからまだ先が長い人生をいきていく上での励みになりました。
ジョディさんはもう50歳間近ということですが、彼女の表情は「これから先もまだまだ地雷廃絶へ全力を尽くさなければ」という意欲に満ち溢れ、これまでも、また、これからも充実した生き方を送っているといったことが感じ取れました.そんな彼女の表情を見て、私も彼女のように、40.50歳からが人生において本当に充実している、という人生を歩みたいと強く思いました.
今回ジョディさんとお会いしたのを機に、世界中で起こっている問題に、微力でも、自分には何ができるのかということを絶えず考えながら生きていこうと思います.
最後になりましたが、会談を振り返って、ジョディさんとお会いできたのもそうですが、それと同じくらい強く思い出されるのが、この会談プロジェクトへの参加者との準備作業です.ジョディさんへの質問事項の発案・検討、それの英語への翻訳、昼食会をどのように進行していくか、についてみんなで集まりいろいろ思考錯誤しながら進めていくのは大変な作業であった.特に昼食会直前の1週間前は毎日遅くまで学校に残り、前日などはリハーサル、自己紹介文の英訳の最終仕上げに予想以上に時間がかかり帰ったのは結局夜の12時近くでした。しかし、みんなで力を合わせて1つのプロジェクトの準備を進めているという充実感があったので、夜遅くまでの作業も苦にならず、それどころか作業の間は時間の経過が非常に短く感じました.今回この昼食会に参加して、ジョディさんにお会いできたことに加えて参加者みんなと力を合わせて作業をしたこと、2つも学生時代のよい思い出ができました.
経済学部 経済学科 3年 高地 良典
彼女との出会いと対談の時間は今でも鮮明に印象に残っています。自己紹介のときに"Hi,Yoshi!"とジョディさんが返事してくれたのは本当に嬉しく、生き生きと夢を持って活動する中の一人の人として感じ取れる瞬間でもありました。特に危険性の高い地雷問題を扱った特異な活動家ということでなく、自分自身の強い真摯な活動意欲を持つ者として彼女の発言には強い力がありました。
彼女から学んだことは、まさに生きるヒントであります。果敢に勇気をもって問題にチャレンジすること、そして夢をかなえようとする確固たる意識と行動力にあふれていることです。問題は考えるだけでは解決しないということ。
"Think Global Act Rocal!!"
経済学部 国際経済学科 3年 藤原 英知
ジョディーさんとあったとき最初私はノーベル平和賞をとる人なんて絶対に堅物に決まっていると思っていました。でもジョディーさんは僕みたいな人と会っていてもとてもやさしくてしっかりと僕の意見を聞いてくれてわかりやすく教えてくれてとても感動してしまいました。
ジョディーさんと握手したときに僕の手は正直言って汗ばんでいました(緊張して)。
でもジョディーさんの手はとてもさらっとかわいていて温かかったんです。
少し悔しかったです。ぼくはがちがちに緊張していたのに、彼女はまったく緊張していなかったんです。まるで僕なんて目にも止めていないかのように。
いつか僕もジョディーさんのような人に握手するときに手が汗ばむほど緊張させられるような人間になりたい。だからこれからもがんばって勉強していきたい。
僕の人生にとって彼女に会ったことはこれからの人生においてのがんばる気合になりました。そしていっしょにがんばった学友たちとの勉強も、大学で死ぬ気でがんばって
いる人がいるということを知って僕の励みとな
りました。
経済学部 経済学科 2年 山村直子
ジョディ氏とお会いする機会を持たせて頂き本当にありがとうございました。偉大な活動家を囲んでの昼食会は、思っていたよりも和やかに、そして、充実した時となりました。それは偏に、この昼食会を裏で支えて下さっていた方々と望月宏教授。それから、共に数日間アイデアを出し合った仲間がいたからだと考えております。それともう一点。それは温かい人柄をお持ちのジョディ氏です。その理由をこれから少し述べさせて頂きたいと思います。
氏は、信念や目標という生きるにあたっての根本のところが、明確なのだということをお話させて頂きながら感じ取ることが出来ました。勿論、お会いする以前にもそのようなことを考えてはいたのです。“地雷廃絶運動”という人間の理想と現実を行き来する問題に取り組んでいらっしゃるのだから、志固い方なのだろうと。
しかし、現実にお会いして、私の想像の甘さを思い知ることとなりました。例えば、普段は、大変穏やかな方なのです。しかし、話の内容が氏の本職に当たる部分になりますと、顔つき、話し方等が豹変するのです。まるで、大衆を前に演説しているかのごとく。私はこのことから、次のことを感じました。一つは、方向性、志を明確に持つ者は話し方、態度等々、その他あらゆる点で押さえるべきポイントを解っているのだということ。それから、そういう人は、強く優しいものなのだということを実感致しました。
私は、まだちっぽけな存在であり。生きていくためのお金すら稼げない状態です。
しかし、いつか私は、たとえどんなにちっぽけな存在であっても光りを放てる人間になりたいと考えております。ジョディ氏とお会いしてそれをますます強く感じました。世界中の人間一人一人は、大変小さいものです。しかし、唯一無二の存在です。それぞれが、輝けばどんなに素敵な空間を誕生させることが出来るでしょうか。私自身、これから少しずつでも磨きをかけていければと思っております。
最後に、
「今回の昼食会に参加する機会を与えてくださって本当にありがとうございました。」
ジョディ氏を始め、この企画に携わったすべての方にそう申し上げたいと心から思っております。
経済学部 経済学科 3年 大熊 博道
「ジョディ ウィリアムズ氏との昼食会」に参加できましたことを私は大変誇りに思います。会議室の前にて「Hi!」と彼女から、声をかけられ、何週間も前から張り詰めていました「ビシッ」という姿勢が、「フワッ」というリラックスムードに一気に変わりました。それは、彼女のもつ雰囲気であり、空気であったように思えます。
その空気に、引きつけられながら、私は彼女と大変充実した時間を過ごしました。しかし、時間が過ぎ、参加者各自の質問へとすすんでいくと、その空気は、最初のものとは異なるものへと変わっていく事を体感しました。会議室の空気はリラックスの中にも、彼女が我々の質問に対して真正面から受け止め、思ったことを答えるという、「ズシッ」とした重く、真剣で、熱い空気に確実に変わっていたのです。私は、彼女のおっしゃる「小さな声の大切さ」というものを目の当たりにしたのです。私はそのような、彼女の姿勢と、彼女が我々に対して返してくださる答えの鋭さに、金縛りにあったような感覚になり、思わず涙が流れそうになりました。
私は、この席に出席し、彼女の空気を体感する事ができました。その事で、「何かに対して、誰かがそれをやるのを待っているのではなく、自分でそれをやればいい」ということや、「一つのことに力を注ぐことの難しさ」「ヒトとして正しい事をする事の当然性」などを吸収しました。しかし、何度も言いますように、彼女の空気を同じ空間で体感したということが、今回、私が得た全てのものであると思います。
今回「ジョディー ウィリアムズ氏との昼食会」に出席しました事で、今後、私の長い人生におきまして、「大熊 博道の空気」を持てるようなヒトになりたいと思いました。そして、「大熊 博道の空気」を感じたものが、それによって、新しい何かを感じ取っていただけるようなヒトになりたいとも思います。これから、私の空気を私自身がつくり続けていきたいと思います。また、今回、このプロジェクトを実行するにあたりまして、多大な協力をしていただきました、学校関係者、教授、参加した学生皆さんに、この場を借りまして感謝したいと思います。ありがとうございました。
経済学部 経済学科 3年 田中 聡
今回の昼食会はとても有意義なものであったと思います。
ジョディー氏はとても気さくな方でしたし、ジョディー氏の英語
も私達学生に合わせてくださったりと非常に丁寧に接してくれた
ことが印象に残っています。
今回の昼食会で一番感銘を受けたこ
とは将来の若い世代のことを真剣に考え、どうすべきかというこ
とを真剣に考えていたことのありました。世界を動かし、地雷禁止条約を成立させた方の考えていることはやはり違うというのを
感じさせられました。また彼女の平和観という話の中で、ただ戦
争がないことが平和ではないというのもすごく印象的でした。
たとえ戦争がなくとも地雷のようなものが人々の生活を危険にさ
らし、なおかつ経済的な発展すら望めなくすることからも平和と
いうものが非常に難しいものであると感じました。
今回のことを通じて一回り大きな視点から物事を見れるような
リました。非常に有意義な時間でした。
私達の素直な感想が見て取れると思います。まさにこの千載一遇の機会は確かに私達の地雷問題に対する意識を変え、我々のできる国際貢献とはまさに関心を持つことから始まることを知ったのです。
一人の勇敢な活動家の意思と行動が私たちに影響を与え、我々の関心が具体的な行動へと移り変わるときに初めて彼女の行動の原動力を知り改めて強さを再認識することになるだろう。
そして、同時にそれは<平和>を希求するものの一人として平和活動に参加することの第一歩になるに違いない。
ある専修大学の学生の中には、ジョディ氏の学位授与式の特別講演会に参加し聴講された方もいらっしゃるかも知れない、また
10月26日に長有紀枝氏(難民を助ける会事務局次長)の『一人一人ができる国際貢献〜難民救済の現状から』というテーマでの講演に参加された方もいるかもしれない。そして、このホームページを偶然観られた方たち、その全ての人々が「自分自身にとっての国際貢献とはなにか」を考え、この質問に自問自答する時、全ては始まるだろう。最初から地雷に対して問題意識をもっていた者などいませんでした。
しかし、もう始まったのです。このホームページには、あなたの<平和>に対する意識を照らす黄色いカウンターが上部に付いています。一人でも多くの人が地雷問題、またICBLの存在を知ってもらうことで、また1つ確実に<平和>への想いが広がったことでしょう。
ジョディ氏はおっしゃっていました、「何かに対して、誰かがそれをやるのを待っているのではなく、自分でそれをやればいい」と、平和を願いだけで終わらせてはならない。そこに問題がある限り、勇気をもってその問題にチャレンジすること。
それは、まさに自分自身を強く信じることから始まるだろう。

|
ジョディー・ウィリアムズ氏
1950年米バーモント州生まれ。バーモント大学卒業後、ジョンズ・ホプキンス大学大学院へ。メキシコ、英国、ワシントンで英語教育に携わり84〜86年、ニカラグア・ホンジュラス教育計画、86〜92年、エルサルバドル医療援助活動などに参画。91年、ベトナム戦争で負傷した人々に義足を世話する「ベトナム対役軍人アメリカ基金(VVAF)」に勤務、92年にICBLを創設。わずか2団体でスタートした運動を、6年間で1,000団体を超す規模に拡大させ、97年、ノーベル平和賞を受賞した。97年12月、123か国が参加する「オタワ条約(対人地雷全面禁止条約)」を成立させた。条約発効に必要な40か国の批准を終え、99年3月1日発効させた。98年2月、長野オリンピック開会式に参加。同年、ICBL国際大使に就任。
彼女に関する参考資料
(図書)
「地雷問題ハンドブック」 難民を助ける会 長 有紀枝著 自由国民社
1998年 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「21世紀への創造」
(インターネット)
http://www.icbl.org/
http://www.jca.ax.apc.org/~banmines
|
|