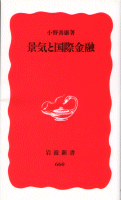|
2000年ゼミ活動第4回(5月11日) 書記 山村直子
|
| ①事前連絡(●新人戦について) |
| ②今週の顔 江藤裕史 TOPIC39「留学で感じたこと」 |
| ③討論①「民間需要を喚起させるための政府政策とは」 |
| ④教授からの補足説明 |
| ⑤討論②「民間需要を喚起させるための政府政策とは②」 |
| ⑥教授からの補足説明Ⅱ |
| ⑦次週までの課題 |
●新人戦報告
| 担当分野 |
参加ゼミ |
討論テーマ(現在調整中) |
| 金融班 |
野口ゼミ |
「金融・財政・国際経済における"規制緩和に関して”」
・ 長期で見たときに"規制緩和"の賛否を問う。
望月ゼミナールとしては、賛成。
|
| 財政班 |
鶴田ゼミ・徳田ゼミ |
「景気回復のための政策 」
・増税か減税か
・日本的経営の見直し 終身雇用制度など
|
| 国際経済班 |
野口ゼミ・徳田ゼミ鶴田ゼミ |
「アジアNIESの望ましい発展のための条件」
現在抱えている問題をとりあげる。
|
新人戦日程
6月1日 論文提出
6月17日 新人戦
新人戦班分け
|
金融班
|
国際経済班
|
財政班
|
| 田村直之(書記2年)
高村雅秀(2年)
石井英嗣(2年)
永松和宏(2年)
小西加津奈(2年)
吉岡千晶 (2年)
|
宮澤奈緒(書記2年)
株屋根彩子(3年)
稲嶺しのぶ(2年)
鈴木竜介(2年)
三宮慎大朗(2年)
|
辻文野(書記2年)
正根寺舞子(2年)
佐々木麻希(2年)
川嶋靖代(2年)
飯野勝也(2年)
江藤裕史(3年)
|
|
②今週の顔 江藤裕史 TOPIC39「留学で感じたこと」
|
ここでは今週の顔として、ゼミ生のコラムを紹介していきます。今回は3年生江藤裕史のTOPIC39「留学で感じたこと」です。
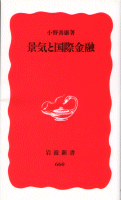 |
テキスト紹介 小野善康著『景気と国際金融』 岩波新書
内容紹介 本書の土台となった理論は、現代現代マクロ経済学の基礎をなす、ダイナミクス(動学理論)の考え方である。しかし、現在のほとんどの動学理論では需要不足が引き起こす不況という発想がきわめて軽薄である。本書の特徴はそれを中心据えて分析しているところにある。
学習方法
①ゼミ生は本ゼミまでに、指定された範囲を読み、火曜日24時00分までに掲示板に感想と論題を書きこむ。
②毎週交代で三年生が討論の司会進行をする。(司会は掲示板より論点と班分けをしてくること。)
③班別で論点整理をし、全体のディスカッションから結論を導き出す。希望者はパワーポイント等を用いたレジュメを作成してくる。また次週ゼミまでに感想を掲示板に書きこむ。
|
司会・吉沢裕典
方法・テキスト第一章を再確認して、その上で民間需要を喚起する政策について議論する
①グループディスカッション、「需要を喚起させるための政府政策(日本の財政に照らし合わせた上で)」
|
A班
|
|
政策:ベンチャー企業に補助金を
|
|
理由:補助金は、無駄な公共投資から回すそして投資先を提示することにより国民の不安感を拭う
ベンチャー企業は、消費意欲を歓喜し得るアイデアを持つ。
政府が補助金をだす
↓どこへ?
大企業ではなくベンチャー企業へ
↓なぜ?
大企業はリスクを嫌う性質がある。
ベンチャー企業で開発したアイデアを大企業に持ちこむことにより大企業の生産能力を生かす。 これは、最終的に補助金の効果を経済全体に波及することが可能性を秘める。
|
|
B班
|
|
政策:法人税を下げる→その分が設備投資に行く。 規制緩和→自由競争、価格競争を引き起こすため。
|
|
理由:政府政策は市場・新市場の環境整備からバックアップしていくことが大切と考える。特に21世紀のメインとなるであろうIT関連は法整備もインフラも十分でない。また法人税を下げることで、民間需要を喚起させる新商品開発のもととなる設備投資を企業がよりおこなうであsろうと考える。しかし、減税がどれほど設備投資にインセンティブを与えるか考えてみると、その効果は低いようにも思える。
|
|
C班
|
|
政策:①労働市場の活発化(企業経営としては、固定→変動へ)
②新商品開発の補助
③技術の研究の補助
|
|
理由:①→失業者の受け皿となるように
②→貯蓄分を新商品の消費に
|
|
D班
|
| 政策:日本をレジャー大国にする |
|
理由:そのためには、大型連休を作り、レジャースポット(国内旅行)に行かせる。
・交通網の整備
・国内旅行を安くする
・レジャースポットを魅力的にする
・地方を復興させる
・休み中にイベントを創る
|
|
教授からの補足説明Ⅰ
|
|
需要→消費需要→若年労働者→失業対策、年、再利用
→貯蓄高
→資産効果、為替
→投資需要
→輸出需要→国外 輸入需要
|
|
⑤討論Ⅱ「需要を喚起させるための政府政策(日本の財政に照らし合わせた上で)」
|
|
A班
|
|
注目:消費需要
|
| 理由:不況を脱するためには、消費意欲を喚起することが先決であるから |
| 政策:新製品開発ベンチャー企業に補助金を与える |
|
方法:消費需要に注目
↓
国内の需要が高まるようなベンチャー企業に出資
↓
多くのベンチャーのアイデアに対し、企業の投資需要も活性化させることが出来る
↓
需要拡大(円安方向へ)→雇用UP消費UP貯蓄性向が減る
↓
輸入需要UP(原材料) →円安により輸出需要UP及び、経常収支の改善
↓
結果としてサプライサイド強化が、需要喚起 するつまり単なる生産性上昇にとどまらない
|
|
B班
|
|
注目:消費需要
|
| 理由:低金利なのに、貯蓄に困るから |
|
政策:貯蓄率・・・将来不安から貯める
間接金融→直接金融→情報開示→自己責任
ベンチャー→中年労働者が安心して働けるセーフティーネットの確立
|
|
理由:政府政策は市場・新市場の環境整備からバックアップしていくことが大切と考える。特に21世紀のメインとなるであろうIT関連は法整備もインフラも十分でない。また法人税を下げることで、民間需要を喚起させる新商品開発のもととなる設備投資を企業がよりおこなうであsろうと考える。しかし、減税がどれほど設備投資にインセンティブを与えるか考えてみると、その効果は低いようにも思える。
|
|
C班
|
|
注目:消費需要
|
| 理由:景気に影響大 |
|
政策:○情報基盤の整備
○環境関連福祉への投資
○セキュリティー
|
|
方法:新興産業の支援→投資UP
↓
雇用UP
↓
労働市場の活発化
↓ ↓
株価上昇 雇用UP、消費 UP
↓ ↓
デフレ緩和
↓
物価UP→利子率UP→円安→国際競争力UP→輸出需要 UP
|
|
D班
|
| 注目:消費需要 |
| 理由:貯蓄性向を減らす |
|
方法:レジャー活性化による需要増加を狙う
①イメージ戦略(貯蓄するよりレジャー)
②地域振興(観光地の活性化)
③旅行会社の優遇税制
④大型連休の設定
|
|
教授からの補足説明
|
|
○貯蓄性向の劇的な変化は望めない。 もし、変化があるとすれば、ライフスタイルの変更により引き起こされるであろう。
○例えば、60歳以上が1番貯蓄を有するが、彼らは、それらを使いきることなく 生涯を終える。例えば、Early Retirementが平均的なライフスタイルになれば
貯蓄により悠悠自適な余生を過ごすことが出来る。 貯蓄を下げる可能性がある問題点
○年金が下がっている中で、Early Retirementは、可能か?
○高コスト体質
○Scrap and buildタイプの日本の家になぜそれほどの費用を投入するのか?
◎結論:○広範囲でのライフスタイルの変化がないと、日本の貯蓄率は変わらない。
○貯蓄率は、日本人がどういう生活を望むかというところに拠る。
|
○今週の感想は、①今日の感想 ②教授に指摘されたことに関する見解 を含んだものを載せてください。
○次週は、第3章の1節2節3節それぞれのまとめをBBSに。 出来れば、議論点も提示してみてください
○ "今週の顔"の担当の人は、用意をすること。来週は株屋根さんです。
○ 進級論文をPC班富田に提出 対象:吉沢・木幡
○ 新人戦の記録と数学の記録をそれぞれ担当の方はPC班富田に提出
書記係山村から英語班、数学班、新人戦の書記へ
○ 木目細かなフォローのため、英語班、数学班、新人戦班の担当の方は、それぞれ記録書を作成し、PC班富田の方まで直接提出するようにお願いいたします。
* 今回の書記に関して、何かご意見がございます方は、書記係山村までお願い致します。→e100548@isc.senshu-u.ac.jp