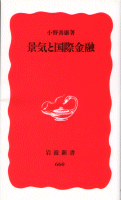|
◎投資乗数効果の理解 C=0.8 △100億円+△80億円+64億円・・・・・・・・
ポイント:投資乗数効果が少ない場合どういうことが考えられるか。
①消費性向よりも消費が少ない場合貯蓄にまわる分が大きい
②投資が最後まで循環し、消費されていない恐れがある・本来は、無限に投資し援助が最後まで使い尽くされることが前提で見込まれる効果であるから、途中で投資が使われずに貯めこまれてしまうと、その本来の投資が得られない。
(例)今の日本に投資するということは、開発途上国に投資するのに等しい
理由:産業連関分析よりも乗数効果が下がっている。
③ばら撒き型であった商品券→もとは税金であり、消費性向が増えたわけではない。+αで消費するような形であれば、消費性向が上がったかもしれない。
◎余剰労働力に関して 余剰労働力を生かすべき産業・・・ ・現在、人手不足の産業:IT系・Net Work系・SE関係 ・将来、人手不足に陥るであろう産業:福祉産業・心理系産業・健康産業
・現状:若年失業者の増加、50代リストラ、20代若年失業増加中
・E-commerce→流通形態を変えようとした場合に、起こる問題
・クレジットカードの普及率
・セキュリティーの問題 ⇒環境インフラを整備すべき
今後、・公認会計士、法曹関係の仕事の増加が見込まれる。
⇒日本の環境規制が多い。
政府は、戦略的新規事業をバックアップできる土壌をつくるべき。
結論:E-commerceの活性化を図るために、環境インフラ(福祉、心理、健康産業等)を整えることが重要だ。
◎視点
○新規事業への需要が増えても、従来の事業への需要が増えるとは限らないので消費意欲喚起可能とは言えないのではないか。
○勝ち組みと負け組みもそこそこの需要が出てくることが景気よくなることだと言えるのか?
アドバイス:
○ディスカッションをする時に、結論を出す時は、具体的な産業名を挙げて、肉付けをすること。
○具体的な例をあげて、負け組みと勝ち組み理解を心掛けてください。
|