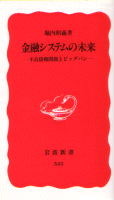|
2000年ゼミ活動第11回(6月29日) 書記 山村直子
|
|
①事前連絡(●就職活動の報告 ●夏合宿について ●ビジネスコンテストについて
|
| ②今週の顔TOPIC45 吉岡千晶「ダイオキシンについて」 |
| ③討論Ⅰ「85~92年までの金融政策の有効性」 |
| ④教授からの補足説明Ⅰ |
| ③討論Ⅱ「金融当局が適切に銀行を監督するには、どうすればよいのか」 |
| ④教授からの補足説明Ⅱ |
| ⑥次週までの課題 |
●就職活動の報告
①大内伸哉先輩
○業界:食品メーカー
○ポイント:エントリーシート。3分の2落される 説明会5000人参加。そのうちSPI受験は、3000人。 1次、2次、最終と試験があるが最終的には、20人程度。
○面接の質問:自己PR、元気、学生時代に何をしたのか(ゼミ、サークル、ボランティア等々)
○志望動機(何が出来るか)
○助言:エントリーシート(会社にどう貢献できるかに結びつける事) SPIの勉強
②河西真裕美先輩
○業界:人に可能性を与えられる業界を希望
○志望理由:インターンシップにより、人の大切さを実感。
○ポイント:エントリーシート(自身の履歴書を持参して下さいました。)積極性 面接の質問:大学時代に何をしたか、どう思ったか。この会社で何が出来るか、どう生かすか。
○決定業種:“教育+人事”の業務いづれか 感想:面接にて自分の長所を“自分勝手”だと否定された。このことは、ショックだった。客観的にどうアピールするかが重要だと思いました。
○教授補足: JODYさんが 「樹が熟していないと焦ってばかりで上手く行かない。一方、樹が熟し、タイミングを見つけると可能性を広げる事が出来る。」 と仰っておられた。
そうなるためにも、ポリシーを持って行動し、1点を固める事が重要なのではないか。
●ビジネスコンテストについて
学生シンクタンクWAAVのビジネスコンテストが開催されます もし、参加希望の方は、山村がチラシを持っておりますのでご一報下さい。
|
②今週の顔 吉岡千晶 TOPIC45「ダイオキシンについて」
|
ここでは今週の顔として、ゼミ生のコラムを紹介していきます。今回は2年生吉岡千晶のTOPIC45「ダイオキシンについて」です。
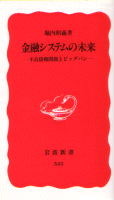 |
テキスト紹介 堀内昭義著 『金融システムの未来』 岩波新書
内容紹介 株価や通貨が世界的に動揺するなか、日本では金融機関の破綻が相次いでいる。本書はシステムの機能不全の原因として不良債権問題に焦点をあてることで、市場メカニズムの抑圧、有効な競争状態の欠如、金融行政のあり方、といった根本的欠陥を健勝するとともに、金融再編成時代の課題として、透明性と公開性を柱とする具体策を提示する。
学習方法
①ゼミ生は本ゼミまでに、指定された範囲を読み、火曜日24時00分までに掲示板に感想と論題を書きこむ。
②毎週交代で三年生が討論の司会進行をする。(司会は掲示板より論点と班分けをしてくること。)
③班別で論点整理をし、全体のディスカッションから結論を導き出す。希望者はパワーポイント等を用いたレジュメを作成してくる。また次週ゼミまでに感想を掲示板に書きこむ。
|
司会・津ヶ原正博
方法・テキストを元に、グループディスカッションを行う
①グループディスカッション、「85~92年までの金融政策の有効性」
|
A班
|
|
・85~89年5月低金利政策 →低金利政策(~89年5月)→バブル→(金融引締め:総量規制)→バブル崩壊
|
|
B班
|
|
・マネーサプライの拡大
↓
資産価格だけを見ると有効。しかし、民間の消費・投資は増加しているのか?
↑
民間の消費が増加しない事には、健全な経済状態とは言えないのでは?
⇒プラザ合意やブラック・マンデーにおいては、有効な働きをしていたが、最終的には、 経済全体の安定を見ると有効ではなかった。
|
|
C班
|
|
1985年 ・プラザ合意 ・円安是正=ドル高是正 ・経常収支黒字の縮小を目的とした政策、、、
具体的政策: ・財政再建⇒赤字削減 ・公定歩合の引き下げ→国内需要↑上昇 金利↓→資産流出→(円安)→円高
1時円安=黒字削減失敗
結果として、バブル量=資産価格↑ 円高になったが、バブルの影響の方が大きかった。
→黒字削減失敗
補足:実質経済成長率をグラフとして添付していました。
|
|
D班
|
|
GDP前年比 金利変化(公定歩合) 消費者物価指数
85年プラザ合意 87.8 A
86年 0.31331 5.00 87.8
87年 0.047565 3.00 88.9 B
88年 0.059944 2.50 91.4
89年 0.044469 - 91.4 C
90年 0.055489 3.25 94.3
91年バブル崩壊
政策:
A:金融対策としては、公定歩合を引き上げるタイミングが遅すぎた。
B:7月、8月公定歩合の0.5%ずつ引き上げ(西独)
C:日本公定歩合の初の引き上げ。(西独は既に4回引き上げていた)
|
|
E班
|
|
総量規制→バブルを終息させることが出来た。しかし、農林系統金融期間が除かれていたため、そこから、住専経由で融資拡大がすすんでしまった。
プラザ合意→マネーサプライ(M2+CD)増加(10%以上)
低金利政策 経常収支黒字の方向へ
赤字国債発行→“0”(91~93年)
→85年 金利自由化←外圧による
・ブラックマンデー→財テクブームを引き起す
・低金利政策維持→外圧(日本アンカーの役割)→世界的には世界恐慌になるのを抑えた
・セーフティーネット→市場規律が、有効に働かない。リスク選択の歯止めが利かない。
|
司会・木幡英晃
方法・テキストを元に、グループディスカッションを行う
①グループディスカッションⅡ、「金融当局が適切に銀行を監督するには、どうすればよいのか。」
|
A班
|
|
①金融当局が適切に銀行を監視可能なこと 有効性⇒具体例→累進預金準備率操作制度(仮)の導入。
・銀行経営のモラルハザード
・預金者のモラルハザードの回避
限界:銀行経営自体に口を出せない
|
|
②有効性:銀行の健全な経営を監視する役割を果たす。
・経営があぶない銀行には、警告を出すなど
限界:すべての金融機関を監視しきれない
・金融機関のすべてを監視するのは難しい
*累進預金準備率操作→流動しすぎるのを吸収する
|
|
B班
|
|
金融当局を強化するか? どのように強化するか
①監督の権限と実行力を明確にする事で責任を定義 →責任を負うべき監督が早く見分けられ対処が早くなる
②市場モニタリングの強化 →民間の研究機関との関係を強化 →市場を明確に把握できる
|
|
C班
|
|
今後のシステムはどうなっていくのかを提言する機能をつける →民間は出来ない⇒限界:モラルハザードが怒ってしまう。→市場規律の強化
*要するに、監督を強化して出来るだけ介入を避ける。
|
|
D班
|
|
セーフティーネットの制限実施 →市場規律の活性化 (市場規律へのセーフティー・ネットを金融当局が担う)
法の整備(銀行と取り付けの防止等々)
|
|
E班
|
|
ペイ・オフの金利引下げ→市場規律をより働かせる→銀行管理部分専門
・大蔵省の分割
*いざという時の加入即効性
|
|
・個人投資家を守るために、市場規律を保護する。
・東京銀行と三菱銀行が非常に成功しているが、大きくなりすぎたために意思決定が鈍ってきている
・市場自体をクリアにする必要性
・富士銀行に見る横並び
・市場規律を活性化させることが出来るのは、国際競争が定番となる市場のみ。
⇒外資参入にも耐え得るシステムは構築する事が出来ない。
|
| |
○第6章はすでに実行された金融ビッグバンのことが書いてあるので、各自でまず金融ビッグバンでどのような改革が行われたか理解してきてください、その上で来週のサブゼミで論点を発表します。
○補足としてもし自分が一億円を資産運用するなら具体的にどのように行うか掲示板に書きこんでください。
○今週のゼミの感想を掲示板に書きこんでください。
書記係山村から英語班、数学班、新人戦の書記へ
○ 木目細かなフォローのため、英語班、数学班、新人戦班の担当の方は、それぞれ記録書を作成し、PC班富田の方まで直接提出するようにお願いいたします。
* 今回の書記に関して、何かご意見がございます方は、書記係山村までお願い致します。→e100548@isc.senshu-u.ac.jp