<原論班>
| 財市場:消費と所得の関係 | |
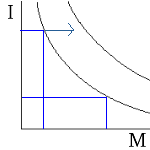 |
W=Md+Bd Md=L(Yr) Bd=w-Md 貨幣需要上昇のためには所得の上昇か利率の減少が必要。 |
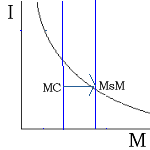 |
Y=C+I+G Y=C(Yo)+I(i)+G 消費は所得に依存する。 |
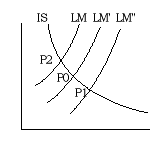 |
総需要曲線は価格と投資の関係を表す |
| <流動性のわな> 現在の状況 | |
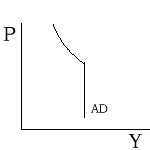 |
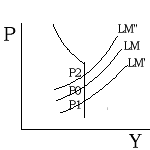 |
<データ班>
デフレ・金融面の影響
資産(①地価 ②株価 ③金利) 価値の下落
(貸し手側)金融
①土地を担保に貸し出していた。-地価の下落―不良債権の増加
②資金需要の要求、企業の資金調達手法の変化(内部資金調達の方に外部資金調達から需要がシフトした。)
(借りて側)企業・家計
・資産の持ち方 1位:土地 (家計:構成比 75%)
<ミクロ班>
今回は銀行の不良債権についてのデータを持ち寄った。しかし、具体的な話し合いにはいったっていません。
金融業界全般の概要をとらえることも行う予定だが、前回調べた財市場につなげる予定。
財市場では主に価格の動向や企業の収益面を見てきたが、今回は資産運用という大きな視点で捉え価格の引き下げがどのような状況の中でおこなわれているのかを見ようと思う。
その中で健全な企業とそうでない企業の現状を調べ、二極化ということに重点をおく。
|
<各班に要求されている資料>
|
(データ班)
・貿易収支、貨幣の流通速度、公共投資の伸び率、為替レートの推移
・インフレ率、財政赤字の推移、設備投資
以上のデータを長期と短期を区別して
(原論班)
・IS-LMモデルを開放市場等のモデルに当てはめてほしい。
・投資と利子率(内部保留の現状について)と、そのときの変化について。
(ミクロ班)
・ストック面とフロー面をバランスよく調べる。
・財務内容
・営業利益と経常利益を区別し、理論づけて。
|
書記からの連絡 |
* 今回の書記に関して、何かご意見がございます方は、書記係川嶋・辻までお願い致します。