<1班:正根寺・辻・高橋・長谷川>
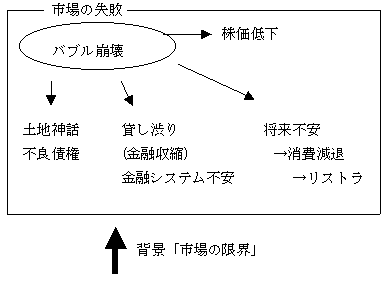
| ☆労働市場 | 労働は人間自身に付着しているもの 労働力を測るものさしが無い 所有権の衝突 |
| ☆土地市場 | 流動性が限定されている 商品としての単価が高い |
| ☆貨幣市場 | 貨幣は実体が無い →無限に信用を増大する可能性がある →信用創造の面で不安定 |
<2班:飯野・田村・高村・津が原・伊藤>
本来市場は協力・安心・信用の体制を基盤として競争が成り立ってきた。しかし、時代の流れとともに競争原理が積極的に取り入れられたが、協力・安心・信用の体制に不備が生じてしまう。そこで政府は協力・安心・信用の体制を再整備すべきだったがそれを行わ図、人間の合理的判断能力に任せようとした。つまり、市場の失敗とは人間の持つ合理的判断能力には限界があるのだが一人一人の人間の処理能力を超えるリスクを社会全体でシェアするセーフティーネットとそれにつながる制度やルールを作らないで、本来市場に見合わない本源的生産要素を競争だけにゆだねることである。
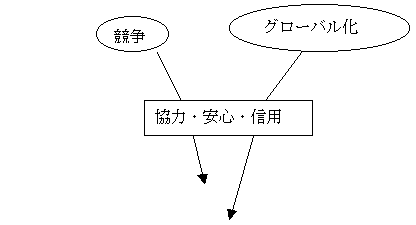
<3班:永松・鈴木・江藤・朴・原>
まず、市場万能主義経済において行われた政策にはどんなものが挙げられるかをここでは特に金融面から話し合いました。出されたものとしましては、
・小さな政府論
・規制緩和政策
・公共投資
・メインバンク制
・金融自由化
です。これらのことは全て市場万能主義経済を過信し、まかせっきりにしてしまった結果導かれた失敗と言えるのではないでしょうか。また、話し合い中に政策ではありませんが政策の失敗の産物として出されたのが以下の2つです。
*不良債権・・・銀行の企業に対する見込み・不良債権の格付けの甘さによるもの。
現在では、銀行は銀行の機能を果たしていない状態にある。
短期的な投機に銀行が走ったことで自ら仮想信用創造を作り出しバブルを招き、
次に自ら信用収縮を招きバブルを崩壊させた。
*自己責任・・・(⇒自己責任をとらなくてはいけないと思うと銀行側も経営の危ない企業だけではなく
優良企業からも資金収集を急ぐことになる理由。)
結論
金融自由化(規制緩和)
↓
過剰な信用創造(バブル)
↓
信用収縮(バブル崩壊)
↓
信用収縮の継続(貸し渋り)
<4班:三宮・吉岡・吉沢・井口>
市場原理主体の金融の自由化、それは通貨の流動的にすることで資本の有効利用、特に発展途上国に対して効率的な資本の流入が行われた。しかし一方で、短期資金の過剰な流動によって、為替売買での自国通貨のだぶつき(過剰設備投資・過剰生産性)になり、それがコスト削減(リストラ)となって「雇用不安」を引き起こした。また通貨の流動化はバブル・金融システム不安を引き起こし、貸し渋りによる銀行不安から企業へのスパイラル的な悪循環を生み出した。それが結果2重の「雇用不安」⇒「将来不安」となった。
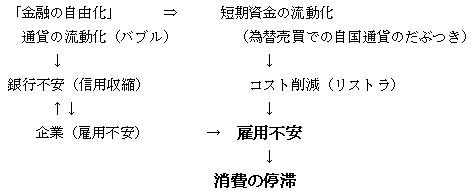
<5班:小西・稲嶺・株屋根・山村・伊藤・岡田>
バブル崩壊 → 各市場で問題発生(不良債権など)
→ 市場にそぐわない既存のシステム(二元法)を導入し、解決を試みる
→ 結果、市場の不安定化 ⇒ 市場の失敗
この流れの中で、国民の「将来不安」というものが生まれる。
しかし「将来不安」背景には、自己責任の欠如(政治への無関心さなど)というもの考えられる。
|
ディスカッション②
|
論題②「市場化の限界を踏まえたうえで、セーフティネットの必要性とは何なのか?」
<1班:正根寺・辻・高橋・長谷川>
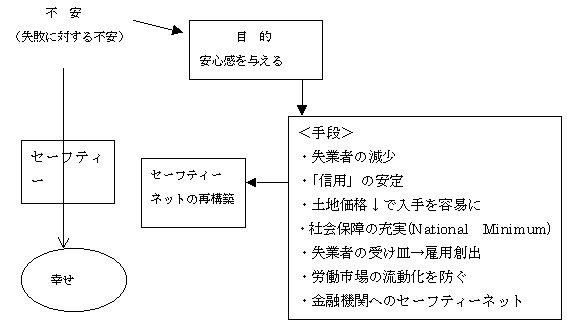
<2班:飯野・田村・高村・津が原・伊藤>
1. 本来市場にはなじまない本源的生産要素(労働・土地・貨幣)を市場で安定させる。
2. 二分法思考を拒絶し、第三の道を作る。
3. その分野での不安を軽減させる。
これらの理由によってセーフティーネットが必要であるといえる。
その結果として例えば分権化社会を構築していくというような将来が考えられる。
<3班:永松・鈴木・江藤・朴・原>
まず、バブル崩壊前にもしセーフティネットがあればバブル崩壊は防ぐことができたか?
これにつきましては、現在のように長期不況に陥るほどの大きな崩壊ではなかったかもしれないが、バブルの崩壊は発生しただろうと推測しました。これは、現在ひかれているセーフティネットがその機能を果たしておらず、ただの制度になってしまっているからです。
では、セーフティネットをひけば全く安全なのか?といえば、そうではなく大切なのはセーフティネットを何処までひくかになってきます。縦横無尽にセーフティネットを張り巡らせばモラルハザードの問題も出てくるでしょう。そこから、
救う制度だけではなく上から抑える制度も必要。
落ちてもいいやの制度ではなく落ちても自力で這い上がれる制度。
以上のように前向きなセーフティネット、またはある程度時代の先見性を持った経済政策を行うことが必要になってくる。なぜならば、セーフティネットの必要性は、経済の触れを小さくとどめることにあると考えたからです。
結論
セーフティネットの目的…経済の触れを小さくする。
㊦ 前向きなセーフティネット
・最低限度の生活保障
・雇用の流動性の確保(もし失業が起こったときなど短期間で再雇用出来る様に。職業訓練の拡充。)
㊤ 先見性を持ったマクロ経済政策
・過剰信用創造を防ぐ。
<4班:三宮・吉岡・吉沢・井口>
労働・・・労働者・経営者側の権利の衝突があるため、その保障のためにセーフティーネットの整備が必要である。
土地・・・流動性が無く、市場原理が働きにくい。価格が高く、高所得者に集中してしまう、
などの特徴がある。土地計画規制などのセーフティーネットが必要である。
貨幣・・・「信用」の危険性
本源的にこの3つの財は、市場競争に不向きなものであるために、このリスクを社会的に処理、全体でシェアする継続的な協力関係、つまりセーフティーネットの構築が必要である。また時代の流れとともに機能が失われてしまったセーフティーネットは再構築していく必要がある。
<5班:小西・稲嶺・株屋根・山村・伊藤・岡田>
労働・土地・貨幣市場の三市場は、相互に密接な関係で成り立っている。
またそれぞれの市場は常に、安定していなければならない。
なぜならば、ある市場が不安定になれば、それが他の市場に影響を及ぼす恐れがあるからである。
(不安定⇔悪循環)
<具体例>前期マクロ班のデフレの構造モデルより
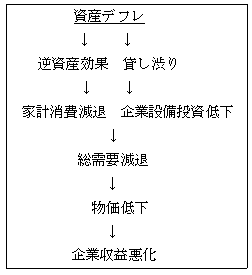
以上から、三市場を安定させるためセーフティーネットが必要となる。
|
書記からの連絡
|
* 今回の書記に関して、何かご意見がございます方は、書記係川嶋・辻までお願い致します。