2001年ゼミ活動第17回(10月4日) 書記 

| 2001年ゼミ活動第17回(10月4日) 書記  |
| <<連絡事項>> |
| ①公開ゼミについて |
| ②今後のゼミ活動予定 |
| ③『セーフティーネットの政治経済学』 4章~終章 |
|
①公開ゼミについて
|
10月11日の予定 1.教授からの言葉(10分) 2.両ゼミの活動内容 ppt 使用(10分) 3.両ゼミ長よりあいさつ(10分) 4.アンケートの配布 ・ 公開ゼミ後、「どんな人材を取るのか」ディスカッションをする ・ 当日は、4展開で行う(下記参照) ・ 通常ゼミ活動は17:10以降開始 ・ 4年生は任意参加(公開ゼミのみ) ・ 試験問題等の詳細は現在、進行中 |
|
②後期ゼミ活動予定
|
|
10月11日 公開ゼミ(95H) 1. 14:50~15:20 2. 15:30~16:00 3. 16:20~16:40 4. 16:50~17:10 ※15:20~ゼミ活動・採用について(←こちらはゼミ生以外は参加できません) 10月18日 エントリー試験(12:15~/725教室)&一次面接 10月19、20、22日 面接(20日は予備日) 10月22日 一次合格発表 10月23日 二次ディスカッション&選考 10月24日 教授と最終選考&二次合格発表 |
|
③『セーフティーネットの政治経済学』 4章~終章 司会 川島
|
|
<1班:正根寺・辻・高橋・長谷川>
|
||
労働市場 年金・医療・失業などに関する社会保障制度 年金 年金の税金化 医療 介護保険制度・地方税の充実・地方分権 失業 終身雇用・ワークシェアリング・雇用保険の給付期間の延長 中高年層の雇用促進 金融市場 中央銀行の最後の貸して機能 ネイションスタンダードの確立(BIS規制・自己資本比率) 中央銀行の最後の貸して機能 預金保険機構 土地市場 公営住宅や家族補助や住宅金融制度などの公的住宅制度 土地投機を防ぐ都市計画規制 ←土地市場が不安定 |
||
|
<2班:飯野・田村・高村・津が原・伊藤>
|
||
各市場におけるセーフティーネット 労働 税制面での優遇措置 雇用保険の給付期間延長 年金は税方式にし、経済成長スライド方式の採用 土地 低所得者への対策として、住宅購入に資金援助できる体制を整える 貨幣 国内:金融機関の健全化のために、不良債権処理を目指す 国際:不安定な金融市場に対し、アジアレベルでの協力関係をつくる |
||
|
<3班:永松・鈴木・江藤・朴・原>
|
||
これからの政策 ・ アジア通貨を作る。 ・ グローバル政策(日本独自のもの) ・ 年金を税方式に変える。 ・ BIS規制の見直し ・ 地方分権化(介護問題などを地方に任せる) 金融面 アジア通貨は必要なのか? ⇒域内貿易での協力関係を強める。 アジア諸国の経済格差・賃金格差の縮小 為替面などのリスク分散(通貨の信用問題) ⇒しかし、現実的には時間もかかるし実現するのは難しい・・・ ので、通貨バスケット(持合)を作る。 金融の自由化ではなく安定。通貨・市場の安定。 グローバル政策・・・BIS規制,ペイオフ制など アメリカの政策をそのまま取り入れるのではなく、日本の社会にあった日本独自の政策が必要。 社会保障 ・年金制度・・・積立賦課方式から税方式に変える。 ・ミニマム年金・介護保険 何故、社会保障が必要なのか? 社会保障がしっかりしていなければ将来不安を招き消費停滞につながる。では、全ては消費のためなのか? しかし今ある保証を守るためにもより多くの財源が必要とされている。社会保障が拡充しても国民の貯蓄が税金に変わっただけではないのか? 消費中心の社会保障ではなく、そうでないセーフティナットが必要。 まとめ ・通貨バスケット(持合) →通貨の安定の必要性 ・社会保障の拡充 →消費の停滞を防ぐ。 しかし、社会保障を拡充させてもその分の財源は税金なので消費は伸びないのではないか? →地方分権・財源委託 |
||
|
<4班:三宮・吉岡・吉沢・井口>
|
||
労働市場 ・雇用の安定 ワークシェアリングを含めた雇用の確保 新規雇用の創出 雇用の創出 雇用保険の給付水準を下げて期間延長 雇用の流動化政策をやめる ・年金 積み立てから税方式へ 土地市場 ・都市計画規制(住宅地を買占めや登記から守ったり環境や景観を守ったりする為) ・公的住宅制度(低所得者に対する公営住宅や家賃補助、減税政策など) 金融市場 ・アメリカスタンダードがグローバルスタンダードではなく その国の社会的背景にあったセーフティーネットが必要 |
||
|
<5班:小西・稲嶺・株屋根・山村・伊藤・岡田>
|
||
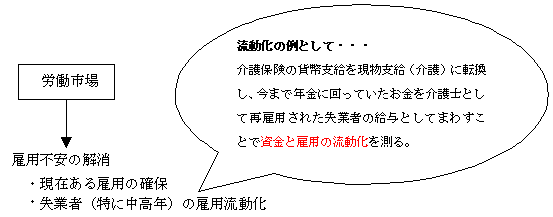
議題2 「セーフティーネットの定義」 | ||
|
<1班:正根寺・辻・高橋・長谷川>
|
||
「相互信頼を前提として、市場の不安定化に伴うリスクの増大を社会的にシェアできるような、今日の日本経済に最も適したもの。」 |
||
|
<2班:飯野・田村・高村・津が原・伊藤>
|
||
「市場化しづらい本源的生産要素市場のような個人では負いがたいリスクを社会的にシェアするという共同性に基づいて、自己決定権を保障していく制度。」 |
||
|
<3班:永松・鈴木・江藤・朴・原>
|
||
この本の中には、 ・ 市場を安定的に機能させる日市場的制度―普遍的概念 ・ 市場経済を成り立たせるための相互の信頼と協力 ・ 社会のリスクをシェアする。 とある。これらをふまえた上で、私たちの班はセーフティーネットの定義をする。 「社会・生活にかかわるだけでなく経済活動において市場リスクをシェアし、市場を安定させる制度。」 |
||
|
<4班:三宮・吉岡・吉沢・井口>
|
||
「社会的共同体」を実現する為の制度」 |
||
|
<5班:小西・稲嶺・株屋根・山村・伊藤・岡田>
|
||
この本すべて踏まえて、セーフティーネットの定義 まずキーワードをあげそこから派生させていく形をとった ・市場の限界 ・資金の流動化 ・日本的な制度 ・自己責任 ・市場の安定化 ・不安の解消 ・持続的な ・信頼と協力 ・既存のシステム ・市場競争 ・リスクのシェア ↓ 「市場競争によって生まれた不安やリスクを社会全体でシェアし市場を安定化させるもの」
「市場になじみにくい本源的要素を市場化したことによって生じた、不安やリスクを社会全体でシェアし、市場を安定させるための制度」
* 今回の書記に関して、何かご意見がございます方は、書記係岡田までお願い致します。 |