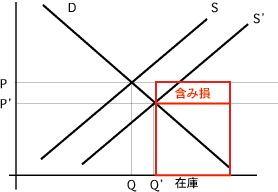| 2002年ゼミ活動第4回(5月9日) | 書記:岡田 Web:白井 | |
|
(1) 来週のゼミについて | ||
| (1) 来週のゼミについて |
||
|
教室がまだ未決定ですので、来週はは98Gで行う |
||
| (2) 今後の輪読本に関して |
||
|
輪読本用の文献が決定しましたので、MLで流すので各自確認すること |
||
| (3) 就活を終えた先輩方より一言 |
||
|
今週より高村さん、永松さん、田村さんがゼミに復帰しました。 |
||
| 「財市場から観たスラックス経済」 |
| マクロ班 |
朴、井口、原、福村、山本 | |
|
「経済成長理論」⇒ 資本ストック(K)、労働投入量(N)、技術進歩率(A)
|
||
| ミクロ班 |
伊藤(和)、白井、伊藤(瑠)、間仁田、大城 | |||||
|
フィッシャーのデット・デフレ理論
どの産業も在庫、生産、投資、稼働率とも低下傾向が見られた。 また在庫の減少は、規制緩和のため国内在庫の減少が影響と考えられ、今後考察する必要がある(在庫の国際間移動)。 前提:経済成長率↓ デフレ・資産デフレ(土地・株式) 貸し渋り−資金が生産性の低い産業に滞留 バブル以来の過剰投資・過剰設備 構成:
・
産業別成長率 |
||||||
| 国際班 |
高橋、長谷川、岡田、関、金子、島崎 | |
|
前提:国外要因が、国内の市場に与えた影響に着目すること
|
||
| 司会者 |
井口 | |
|
各班がまだ模索段階であるが、全体としてはバブル後の日本について広く分析を行い、その中でスラックスについて考えるという方向性は明確になった。これからの方向性としては、スラックスを考えていくなかで、日本経済停滞の本質的な要因というものを各班からの多角的な分析によって見つけだしていきたい。 |
||
| 書記からの連絡 |
||
|
* 今回の書記に関して、何かご意見がございます方は、書記係岡田までお願い致します。 |
||