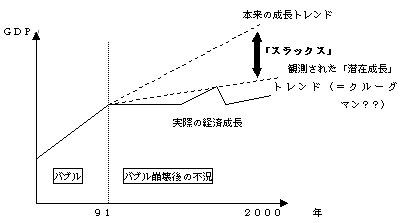| 2002年ゼミ活動第5回(5月16日) | 書記: Web: Web: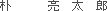 | |
| (1) 欠席者 | ||
井口(体調不良) | ||
| (2) 4年出席者 | ||
永松・田村 | ||
| (3) 連絡事項 | ||
・来週もゼミ活動は98Gで行いますので、間違えないようにしてください。 | ||
| 各班、調べてきたことを発表して下さい |
| マクロ班 | ||
GDPギャップ=実質GDP−潜在GDP/潜在GDP
| ||
| ミクロ班 | ||
設備投資→どの産業も平成9年を山に下落傾向(金融恐慌が原因か?)以後平行をたどる傾向にある。 | ||
| 国際班 | ||
・前提:財市場でのスラックスを考えていく上で、以下を前提とした。 | ||
| 今後の方針。来週のプレゼンを見越した上で発表して下さい。 |
| マクロ班 | ||
(S+T)-(I+G)=NX つまり、国内における高貯蓄は国内投資の停滞をさし、海外投資に回っていることを示す。これをスラックスととらえ、国内投資が上昇トレンドに転換しない要因をみていく。 | ||
| ミクロ班 | ||
スラックスの定義 | ||
| 国際班 | ||
問題点:では、そのスラックスを実際に生んでしまっている要因は何なのかを、国際班の観点から問題点を具体的に見ていく。
| ||
| 司会者から |
| 岡田 | ||
今後のゼミの進行方法としては、各班来週のプレゼンに向けて準備を進めるようにします。
その際には他の班の内容との繋がりを踏まえ、データや理論モデル等を使いながら作り上げていってもらいたいです。
| ||
| 白井 | ||
2週にわたり財市場におけるスラックスをそれぞれの班で考察してきましたが、先週よりも具体的に話を進めることができたのではないかと思います。スラックスの各班との関係も考えながらまとめらていましたが、ディスカッションによってそれぞれの班の持つ問題もはっきりしてきたと思います。プレゼンまでに、具体的なデータや原論を用いより説得力のある有意義なものになるよう財市場のまとめを頑張りましょう! | ||
| 書記からの連絡 |
||
|
* 今回の書記に関して、何かご意見がございます方は、書記係原までお願い致します。 |
||