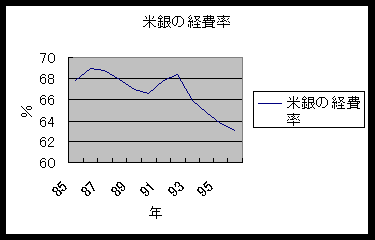
 <図1>
<図1>アメリカの金融はどのようにして変わったか?
<
目次>
序章、米国金融は、どのように再生したか?
3、情報通信革命が生み出す効果について
4、グリーンフィールド・アタッカーの躍進
<終章>日本はどうなるのであろうか?
<
参考文献>ダイヤモンド年末特集号(
12月24日号)米銀だけがなぜ強い 安田隆二、田村達也
<序章>
米国金融はどのように再生したか?アメリカの金融界は、1980年代の後半の状況から驚異的に再生した。最大の頭痛の種でもあった不良債権比率は、90年代の7%台からいまでは2%台にまで回復した。2%前後あった貸倒引当金繰入れ率は平常の0,5%台にまで下がっている。逆に収益力は高まっている。リスクや経費に見合ったプライジングの徹底、利ざや幅の大きい個人・零細企業向けの融資の拡大等によって資金利ざやは、改善されている。また経費のほうは、大胆なリストラ効果により経費率を68-69%(90年)から62%(97年)にまで引き下げるのに成功している。<図表1>
一方日本の銀行は、80年代の後半世界の金融市場における地位が向上した。格付けのトップに邦銀が並んだ。しかし90年にバブルが崩壊して以来いまだに不良債権問題すら解決できておらず、国際金融市場での信用は低下し、構造不況業種とさえ揶揄されている。そして97年には、本丸である日本の金融市場まで欧米金融資本に攻略され、買収される始末である。
アメリカでは、80年代のリスクを無視した投資などにより、多大な債務の焦げ付きを出した。その時の当初の対応は、銀行救済を目的とした問題先延ばし策であり、預金保険を当てに不良融資を続けるなどモラルハザードを引き起こした。しかし、89年RTC(整理信託後者)を設立してからは、不良行・破綻行などを次々に整理していった。また、預金者保護のため借りて支援のブリッジファイナンスのために総額で17兆もの公的資金を投入した。その一方で不良行の経営責任も厳しく追及された。こういった思い切った整理・淘汰が米銀再生の始まりであったといえる。膿を出すのを怖がり破綻行を生き長らえさせ、公的資金投入のタイミングを間違え30兆もの公的資金を使っても解決のめどが付かない日本とは大きく異なっている。銀行の整理・淘汰が進む中で米銀の数は85年の1万5000行から97年には約9700行にまで減少した。それでもまだ過剰であるといわれ今後も減りつづけるだろう。また再生する上で米銀は大きく変化もした。それまでのフォーカス戦略を転換し顧客や業務を選別しその分野に注力するようになり、かつての何でもやる銀行像とは異なってきている。商品の種類も増え収入源も多様化してきている。貸出残高に占める個人向けのローンの割合もトップ千項の銀行で27%(85年)から44%(96年)にまで増加しており、「個人は預金吸収、企業は貸出先」、という古い銀行ビジネスの構造が変化してきており、個人向けの金融サービスの拡大に伴って米銀のマーケティング能力は飛躍的に向上した。クレジットカード等で得た個人情報を蓄積し、クレジットカード等で得た個人情報を蓄積し、データベース・マーケティングを行うことは当たり前になっている。またATM・CD機の普及が進み、90年に8万台だったのが15万台に達しようとしている。テレホン・バンキングの普及も驚異的であり、いまや米国民の生活にすっかり溶け込んでいる。このような販売チャンネルの大幅なローコスト化が実現している。米銀の再生は、このように商品政策、マーケティング政策など自由化時代の競争原理に従って刷新することにより初めて効果を上げたのである。以上のようなことを踏まえ次章で詳しく考察する。
今、金融界は、激しい競争の時代である。そういった中で現在、金融界は買収、合併、提携といったことがさかんに行われるようになった。従ってどこまでダイナミックな合従連衡図を描き、夢を実現していくことができるのか、それは金融経営者の力量次第である。
いうまでもなくビックバンの敗者は、淘汰されるか、強者の配下に収められるかであろう。弱者は、生存のために相互合併で必要な規模を確保しようとするだろう。そして強者は、更なる勢力拡張を目論んで他者との合併・買収に走るだろう。しかし、この時代に必要なビジョンは、発想の枠をもって広げたものでなければならない。県(州)、業態や業界、国境の壁を越えた合従連衡の構想を持たなければ、時代のダイナミズムについていかれかねないといえる。従来は、3つのC、
company,(自社)、customer(顧客)、competitor(競争相手)をベースに戦略が考えられてきた。顧客市場をめぐり、特定の競争相手とどう戦うかがポイントであった。しかし、合従連衡時代にはもう1つCを追加する必要がある。Cooperator(協力、提携相手)である。今の競争相手はいつ手を結んで共同の敵になるのかもしれない。顧客であった他業態のプレーヤーがいつ手を結んで多様な商品のクロスセールスを提供する仲間になるかもしれない。また同様に同じ勝てると侮ってきた競争相手が他者と連合して当社に襲い掛かってくるかもしれない。このように提携、協力相手の存在が勢力を変動させる要因ともなっている。
もう1つのフレームワークとして地域軸、業務軸、国際軸などがある。こういったモノを踏まえた上でいくつかの例を見ることができる。①規模の経済を追及するリテールバンキングの合併・買収。②制約された競争市場内での生き残りをかけた合併。③フルラインによる安定性を求めた証券会社の合併・買収。こういった金融再編を得てアメリカの金融界は劇的に変化を遂げていったといえる。そしてまた、最近になって、金融界の覇者、世界の覇者になることを求めて、メガ・マージャー(超大合併)が動き始めている。また、今まではいくつかの例外を除いて、同業種、同業態の買収合併が中心であった。証券、銀行、保険業界にはいくつかの垣根があるように思われてきた。しかし、企業顧客に対する金融ニーズに答えるためにも垣根を越える必要が出てきたといえる。98年の春銀行業界の王者のシティバンクと、投資銀行・保険・証券のコングロマリットの成長株トラベラーズとの電撃的な合併は、長年のタブーを打ち破るものであった。また、グローバルな面でもオランダの国際銀行INGが英国のベアリングブラザーズを買収し、またスイスのSBCも数年の間にオコーナーの買収、英国ウォーバーグの買収などをやりもう1つスイス3大銀行の一つUBCと合併し今やグローバル金融機関のリーダの地位を手に入れたといえる。このような流れは金融勢力を根本的に塗り替えるほどの力を持っているということができる。しかし。買収・合併がうまくいかないケースもまた珍しくない。ATカーニーの調査によれば、思ったように効果が上がらず、ROE(自己資本利益率)を下げていることも少なくない。実際合併後に旨くいっているケースは50%重弱しかないといわれている。そこで、これから合従連衡の面だった例をいくつか挙げてみる。
シティバンクは以前から米国を代表する先進的な銀行である。いっぽうのトラベラーズグループも傘下に投資銀行のソロモン・スミス・バーニー、トラベラーズ生命保険、トラベラーズ損害保険、消費者金融のプライメリカ・ファイナンスサービス及びクレジット・カンパニーを抱える一大金融コングロマリットの持ち株会社である。98年の4月6日この二つが合併することとなった。これは、米国金融史に残ることだろう。まったくの異質な企業体の合併であったからである。この合併が成立した背景には、「これからの金融競争には業務の幅広さと規模が欠かせない。巨大かつ強力な金融機関のみが、世界市場をリードできる」というシティコープのジョンリード会長とトラベラーズのワイル会長の二人が共通してこの考えを持ったからである。
シティコープの中心業務である個人顧客の金融資産運用は、ますます株式や投資運用にシフトしている。米国の株式ブームや、確定拠出型個人年金「401k」の爆発的な成長もあり、自前の証券・投資分野が弱いシティのアキレス腱となっていた。クレジットカードでは、自前のブランドで圧倒的な強さを誇り、世界中に支店を持ち他を圧倒するほどのネットワークによって」個人向けの分野で圧倒的な強さを持っているシティにとっても証券資産管理サービスの強化は不可欠であった。また、一時参入を試み失敗した保険サービスでもシティの支店やテレフォンセンターを通じて、1億の顧客にクロスセルできるとするならば、その保険販売手数料は莫大なものとなり安定収入となるだろう。ただし、ブランドのある商品力と保険リスク管理に長けた保険会社をパートナーとしなければ、クリティカルマス(収益が確保される規模)に到底到達しないことも知っていた。
逆に、トラベラーズは、証券,投信、生損保というおいしい商品をもちながら顧客基盤は小さかった。ソロモン・スミスバーニーに500万、トラベラーズに1000万であり、米国や世界の中産階級に1億もの顧客基盤を持つシティコープの顧客データマーケティングを使えばビジネスは数倍に膨れ上がるだろう。
また、法人金融部門においては、シティコープはグローバル・コーポレートバンキング部門を通じ、コマーシャルバンキング部門や外貨為替、そしてキャッシュマネジメント等に、とりわけエマージングカントリーではおいて多大な成功を収めている。しかし前述のとうり
JENA(日、欧、米)部門の大企業向けの金融サービスでは苦戦していた。他方、ソロモン・スミス・バーニーは投資銀行のトップ3に入りながら、従来債券自己売買に偏っていたため法人基盤は今一つであった。その上システム面においても優位に立つことができるため、2人の経営者はGOサインを出したといえる。その他にもドイツ銀行とスタンレー・ディーンウィッターの合併もついこの間決まった。このように異業態の合併はもはや不思議ではなくなってきている。<図2>
1980年代までは、総資産でスイス第2位と3位を行き来する平凡な大手銀行だったスイス・バンク・コーポレーション(SBC)が、90年代の一連の買収を経て、今や、顧客預かり資産世界第1位、総資産第2位、株主資本では第3位のトップ・グローバルバンクへと成長した。株価の推移で見てみると、89年の終りから現在に至るまで4倍以上に増えている。ここで、SBCが買収を通じてみずからをグローバルバンクへと変革させた過程を見ていく。
SBCは、1980年代の終り頃非常に厳しい状況に追い込まれていた。英国のビックバン、87年の株式暴落、88年に始まったスイスの規制緩和にやより、法人融資マーケットは全般的に難しくなっていた。ただでさえ、母国スイスでは人口700万人の小さなマーケットに多数の銀行がひしめいていた。SBCは活路を法人融資以外の国際市場に見い出そうとした。しかし、当時融資以外でSBCが国際的に強かったのは、スイスの株式とユーロ債のみであった。まず最初に行ったのがオコーナーの買収であった。オコーナーは77年シカゴに設立された、金融機関相手のトレーディングビジネス中心のデリバディブ専門会社である。この時、SBCのトレーディング部門のヘッドであり、一連の買収の立役者であるオスペル氏はオコーナーの「高い金融技術」と「公正な能力主義」にいたく感動し、何とか提携しようと模索した。ちょうどオコーナーも資本力のあるパートナーを探しており、両者の思惑は一致した。しかし、当初の合併のときにはうまくいっていたが、両者の文化をフルに統合するため買収したときいくつか問題が起きた。例えば1つの機能・ユニットの長をSBCとオコーナーから1人ずつ、2人で行うという妥協したやり方が両者の融合をいたずらに遅れさせた。オスペル氏は、「オコーナーの経験で、買収先の融合にはスピードと決断力が何よりも大切だということを学んだ」という。この経験は以後数々の買収に生かされることとなる。オコーナーがもたらしたのは、デリバティブ技術、リスク管理技術、実力主義の文化・しくみ等多々あるが、ビジネスや顧客の収益性をみて、ターゲットを定めたマーケティングをするという、当時としては画期的な考え方をSBCにもたらした。
オコーナーの買収によりSBCの利益は向上し、国際証券市場でも名をはせるようになったが、マイナス面もあった。1つには、SBCの国際部門の収益基盤が、トレーディングビジネスになったことであった。トレーディングは儲かるときには非常に儲かるが、ロスの額も大きい、利益が乱高下するビジネスである。したがって、トレーディング中心ということは、格付けには決して好まないことでなく、ただでさえ92年半ばに、数々の融資の焦げ付きによりAAAの格付けを失ったSBCにとってこれは問題であった。そのためグローバル・インベストメントバンクとして成長するのには、顧客基盤が大切であることが強く認識された。もちろんスイス国内及び欧州では、プライベートバンキングとしての資産運用ビジネスの顧客基盤はもとからあった。しかしその他の地域、特に米国には基盤も何もない。このような背景から、SBCは収益基盤が安定しておりあ、また確固とした法人顧客基盤を持った資産運用会社を取得しようとした。国籍は米国にフォーカスにした。なぜなら、米国は6,5兆ドルの世界最大の資産運用市場であり、なおかつ伸び率も非常に高かった。そしてSBCはブリストン・パートナーズを選んだ。ブリストンを得たことにより、SBCの運用資産額は、150億ドルというスイスの金額から480億ドルに跳ね上がった。また米国はいうに及ばず、英国、日本、オーストラリアにわたる資産運用顧客基盤を手に入れた。これら優良企業、機関投資家との取引増加で、SBCのプレースメント能力が大きく向上した。これによってメリルリンチに代表されるグローバル・インベストメントバンクが当時躍起になって拡大しようしようとしていた資産運用部門を手に入れたSBCは、グローバルバンク化への道を更に1歩踏み出した。しかし、相変わらず投資銀行部門ではトレーディングに依存しており、トレーディング収入後大幅に落ちた94年には、スイス3大銀行のなかで最大の減益幅を記録した。また、その投資銀行の分野での競争が激化し、米国のプレーヤーグローバルに勢力を強めつつあった。そこでコーポレートファイナンスと株式に強い銀行、つまり顧客基盤を持つ銀行を物色し始めた。自力だけで1からグローバルな顧客基盤をつくりあげるのは、コスト的に見合わず、リスクが高いと判断した。そこで名前が挙がったのはSGウォーバーグである。SGウォーバーグは1934年に設立された、英国系のなかではきわめて若いマーチャント・バンクである。ビックバン以降、非常にアグレッシブな活動をし、ウインブルドン化の進む英国投資銀行市場で、英国系として唯一生き残る銀行とまでいわれていたのである。しかし、あまりにも急拡大したため、資本の蓄積や商品の幅がついていかず、94年には投資銀行部門で大幅な赤字を計上、業務の縮小を図るとともに、身売り先を探さざるを得ない状況になっていた。こうして95年SBCが買収することとなった。この時オスペル氏は、ウォーバーグをすぐさま有機的に取り込んだ。統合に伴うリストラクチャリングを年度内には完了することを約束した。また、最初に彼は、SBCの投資銀行部門6500人とウォーバーグの4500人のうち1000人は融合過程で職を失うことを公言した。これは、モルガン・グレンフェルを89年に買収した後、従業員が辞めるのを恐れて、子会社として独自性を持たせたドイツ銀行などとは違う。オスペル氏は、「2つの会社の融合プロセスを早く行えば行うほど、従業員はハッピーになる」といい、融合条件の5ヶ条として、①方向性、アプローチ、および組織構造をなるべく早く示す、②文化の違いはいっしょに働くことで早く乗り越えられる、③適切な給与体系とマネジメント形態が、融合を促進する、④人員削減等悪いことは早く片づけて、ベストの人々を残すようにする、⑤マネジメントとプロジェクトとプロダクション(実際に手足を動かす人々)とをはっきり分離する、を挙げている。また、早い成功を示すのが、新会社に対する人々の熱意を引き出すのに最も有効だとし、「両者の競合により取れた」と称する大きな取引を、早期にいくつか打ち上げた。この早い融合プロセスは、特にウォーバーグ側の従業員の大量退社を引き起こし、それとともに、手に入れたと思った顧客基盤をSBCは失うのかと思われたがそれほどの衝撃はなかった。この成功によりウォーバーグの既存顧客も強い商品力に裏打ちされた感じでいろいろなランキングで軒並み10位以内に名前が載るようになった。この後も、米国のディロン・リードを買収するなどますます強くなり、ついにはスイス第1位の資本力をもっていたUBCを買収するに至りついには、世界のグローバルバンクのトップの地位に就いたのである。
3、新チェース・マンハッタン
大競争時代には、2番手行や準大手証券会社は非常に苦しくなる。トップと競争するには小さすぎ、かといってニッチ市場に特化するには大きすぎる。ちょうど中途半端な存在になってしまうからである。つまり、規模の経済ではトップに差をつけられ、ブランド力を失い、他方、ビジネス分野に絞ろうにも顧客基盤が多すぎて総合金融サービスから逃れられないという罠にはまってしまう。チェース・マッハッタン、ケミカル、マニハミの3行は、80年代にこの中途半端な銀行になってしまっていた。シティコープやJPモルガン、バンガーズトラストとうまく市場を共存してきた3行も金融自由化の中で、2番手行の悲哀を味わう羽目になってしまった。不良債権に困っていただけでなくコマーシャルバンク、特にリテールバンキング部門では、シティコープの積極的な拡大戦略・価格競争戦略に押しまくられていた。中位行のケミカルバンクは法人金融や国際金融から個人金融まで幅広く活動していたがシティバンクの攻略にあって、ミドルマーケット(中小企業向け貸し出し)に焦点をあて、支店ネットワークにも「ハブ・アンド・スポーク」構想をいち早く持ち込んで生き残りを目指した。しかし、それでも法人顧客は」見捨てられないし、収益の安定性にも欠いていた。そこで法人金融と年金運用に強みをもちながらも中途半端内地で苦しんでいた信託銀行のマニハ二が良いパートナーとして浮かび上がった。マニハ二は法人金融市場の証券化が進みすっかり流れに乗り遅れていた。そして2つは合併したがそれでもぎりぎりについていけるだけでまだまだシティコープやJPモルガンに対抗していくだけの力はなかった。そこで、新たな合併相手として、チュースマンハッタンが挙がった。
チュースは、かつてはシティバンク、バンガメと並ぶ名門3大銀行であったが金融自由化対応に遅れ不良債権を蓄積させ、市場シェアを失っていた。そのような中でマニハ二との合併によりグループに入っていたケミカルはチュースと合併し一気に95年当時米国際大の銀行になった。
ところで旧チュースとケミカルとの合併は、米国銀行市場のなかでもきわめてうまく言った例とされている。合併前後の銀行の業績推移を見ると市場の伸びによる収入増加もあり確実に業務改善がされている。実際米国の買収、合併事例は増えているが、その中でも業務範囲が重なる銀行同士の合併は「イン・マーケット型」と呼ばれており、営業地域が異なり業務範囲の重複が少ないのを「アウト・オブ・マーケット型」と呼ばれている。アウト・オブ・マーケット型は、事業統合における衝突が少なく、効果の実現まで比較的時間の余裕がある。しかしイン・マーケット型の場合、しばらくの間同一業務を担当する旧組識が二重に残り、コスト削減効果を達成できない、あるいは優秀な行員や管理者、優良顧客が流出してしまうことが多い。さらに対等合併の場合どちらが主導権を握るかでけんかが絶えないため更に難しい。旧チュースとケミカルの合併は業務の重なりが大きく、かつ対等合併であったため効果を出すには思い切った組織統合が必要であったといえる。
そういった意味で経験豊かな経営陣に恵まれ、優れた合併管理モデルをもっていた上に、合併という戦略ではなく合併後の事業統合、組織統合の優れたマネージメントがあったことが成功の要因だといえる。
2.古くて新しい原点を徹底追求(コアカスタマー、コアスキル、コアカルチャー)
ここで金融競争を制するには、どのようなタイプだと考えてみると2つのタイプが挙げられる。1つのタイプは、戦略に優れ差別化に成功し、合従連衡戦略に勝ち抜いたいわゆる「賢者」である。前述した合従連衡の覇者や、後述するグリーンフィールドアタッカーなどがそれに当たるといえる。しかし、戦略面にみると競争相手とまったく異なる斬新なものを発見することはきわめて希であるといえる。これだけ情報がオープン化されていると、やるべき戦略は共通してくる。実際、どの禁輸期間の中期戦略経営を見てみてもコピーかと思うほど似ているのである。従って正しい戦略をどれだけ早く徹底してできるかということが勝負の鍵となってきている。では何を実行するのかといえば、それは「原点を見詰め直して、その表現を今の環境にあわせること」である。ここで経営の原点に立ち戻ってみると「誰が私の金融機関の顧客なのか?」という対象を明確にすることから始まる。かつて銀行は公共的存在として「みんなの銀行」を標榜してきた。しかし、これは顧客からみると、誰も彼も顧客対象とした中途半端なサービスしかきたい銀行としか移らない。顧客満足度も決して高くなく、また銀行にとっても戦線が広がりすぎて資源の集中投資ができない。そこでこれからはどの顧客を対象として扱うのかということを選択し、それに合わせる時代になってきた。米銀の「選択と集中」戦略はこうしたコアカスタマー(顧客)を定めそれに集中し競争力を高める戦略を取り始めた。そして、コアカスタマーはさらにもう一歩踏み込んで考えられ始めた。それは、「長い取引関係を持ち、銀行に収益をもたらしてくれる顧客」を意味するようになった。というのも、顧客の収益分析から約2-3割の顧客が利益の大半を生み出す一方、約3割の客は、銀行に損失をもたらす。そこでコアカスタマーを追求し、望ましくない顧客を排除すれば、収益は20-30%挙がることとなる。
さてリテールバンキングの原点はシンプルである。リテールバンキングを金融自由化と情報通信革命の状況に合わせる形で、コアスキルを追求すれば良いといえる。それには3つほどあり、1つめは、銀行は顧客サービス業だということである。かつては、着実に業務をこなし、親切に笑顔で応対していれば良かったのかもしれない。しかし商品が多様化し、顧客情報が豊富な現在では誰にどういった商品を提供するかといったマーケティング力が不可欠となる。2つめは、銀行は「リスクビジネス」ということからくる。かつては支店長の勘と経験と時間をかけた調査からきていたかもしれない。しかしこれからは、格付けやスコアリングの向上市場については、VAR(バリュー・アット・リスク)やEAR手法の導入、全体リスク管理については、ボートファリオ管理といった科学的スキルが必要になる。3つめは、銀行は「巨大の装置を持ったプロセス工場」であるということである。かつてのプロセス・オペレーションは支店業務を中心に正確な事務をもつことが肝心であった。しかし、これからは、あらゆる情報システムを生かした「リーンオペレーション・インフラ」(小人数でできる業務インフラ)が必須である。支店を代替するチャネルの開拓、業務の集中システム化が急速に進行してきている。こうしたコアスキルは「見えない格差」の最大のものである。目に見える店舗数、顧客数、資金量、営業人員などでは適も対応の仕方があるがコアスキルは敵に見えない。同じぐらいのところでも、差が出てくるのはこのコアスキルによるものである。
あともう一つコアカルチャーが挙げられる。いわゆるコアカスタマーを選びコアスキルを確立し当たり前の戦略を確実に実行する文化を持ったところである。では、実際にいくつかの金融機関の例を挙げてみるとする。
1
ネーションズバンガメ(個人・中小企業特化)ネーションズはノースカロライナ州の地元の個人や中小・中堅企業を相手とする一地方銀行であった。おりしも80年代の金融自由化のときもほかの米銀が華やかな投資銀行・証券業務に参入し国際市場に飛び出していったときもネーションズだけは違った。あくまでリテールバンキング業務のみを追随していた。そして度重なる合併を行い、97年バンガメと合併して全米一のリージョナブルバンクとなった。ここではネーションズの行った戦略についてみてみる。
まず買収合併戦略についてみてみるといくつかの基本原則があった。まずは、成長地域を狙い、ねらった地域ではナンバーワンのシェアを取ることであった。ネーションズが標的にしたものは、リテールバンキング市場の成長性が高い地域だった。そして標的とした地域では「地元銀行として預金シェア、貸金シェアのナンバーワンになること」を至上命題としてきた。というのもリテールバンキングやミドル・バンキングは、その地域内でのシェアの大きさが収益に直接的に影響したからである。従って決めた地域に進出する場合、そこの地元ナンバーワンを買収するあるいは、中小金融機関を次々と買収したりもした。実際97年時点ではネーションズが展開している州は19州にも及ぶがそのうちの11州ではシェアのトップの地位にある。まさに地域に密着した銀行ということができる。
次にネーションズバンクはリテールバンキングを中心に据える限り、規模の経済が大きく働くという信念を持っている。というのもリテールバンキングは支店網やシステムインフラ、そして、本社要員によって固定費割合の高いコスト構造になっており買収後、支店を統廃合したり、システム部門を集約したり、本部人員の重複をなくすことで規模の経済はさらにプラスに働くと考えたからである。実際経費率は買収による規模の経済の拡大に伴って着実に低下しつつある。<図3>
さて、全米一となってもネーションズはやはり愚直にリテール部門にこだわりつづけた。97年の実績を見てみると利益の3分の2がゼネラルバンク部門といわれる個人と中小零細企業を対象とした銀行部門から上がっている。4分の1がグローバル・ファイナンス部門と呼ばれる中堅企業への総合金融サービスと、特定分野の大企業向けファイナンスサービスからきている。ネーションズは顧客対象を特定する一方でその顧客市場に対しては伝統的な商業銀行業務の枠を超えてクレジットカード、資産運用サービス、証券、リース、ファクタリング等総合金融サービスを提供している。つまり総合金融化を否定してはいない。順序からすればまず顧客があり、その顧客があり、その顧客に必要な商品・サービスを揃えるという考え方である。つまり個人や中小企業向けであり、決して大企業向けではない。
ネーションズの強さについてみてみると3つある。①リテールとミドルマーケット・バンキングに必要なコアスキルの確立②それを支える情報システムインフラの整備③戦略をっ愚直なまでに実行する行員の行動力にある。実際ネーションズの顧客データベースは充実しておりそれを基に顧客を選別しそれぞれに違ったサービスを行っている。<図7>
顧客ごとに収益性を合わせて金利や手数料の水準を変更するプライシング戦略は、大きな成果を上げた。取引利益率は20%も改善され、ミドルマーケットへの収益性においても、ROEも15,6%から19%にまで向上したといわれる。
また情報通信革命の成果としてデリバリーチャンネルの刷新も行われた。古い銀行や競争力のないチャネルなどをスーパーなどのインストアブランチに、窓口業務をATMにそして将来は電話やパソコンなどを利用し安くて便利なチャネルに変えようとしている。
②、バンガメバンガメは前述したとうり米国3大銀行の一つであった。しかし金融自由化によるブームであったLBO(レバレッジド・バイ・アウト)融資や不動産といった全方位拡大主義を取った結果存続の危機になるくらいまでなった。そこで89年マネーセンターバンクへのこだわりをきっぱりと捨て、本拠であるカリホォルニア州のリテールバンキングとミドルマーケット・バンキングへ業務を絞り込んでいった。大胆なリストラを行い始めた。不要な部門を次々と売却していき、サンフランシスコにある本社ビルすらも競売にかけた。こういった思い切った改革の上、日本はじめ金融機関からの資金支援に救われ危機を脱した。
その後資産売却した資金を不良債権処理に費やすだけではなく、あえて新しいリテールバンキングの基本インフラとなる部門に投資した。また、規模の経済を追求するために、カリフォルニア州地域の金融機関を買収していった。こういったカリフォルニア回帰によりバンガメはよみがえった。
バンガメの強さについて言えば、愚直な現実主義だということができる。「現場主義」は急変には臆病であり、行員削減にも躊躇する。しかしいったん本部と現場が施策に納得すると愚直なまでにそれを徹底的に実行する力は図抜けている。従って新施策で何年か遅れても、じっさいにはバンガメのほうが普及することが多い。
さてこの2つの銀行が合併することにより、リテールとミドルマーケットを基盤とする全米1の銀行が生まれた。この両行が全米1のマルチ・リテールバンクとなったわけはリテールとミドルマーケットのエッセンスをひたすら追求し、実行してきたことである。
2、メリルリンチ
メリルリンチ証券の名は、いまや外資系証券会社の代名詞となった感がある。日本においてもなじみが深く1961年に外国証券として初めて日本進出を果たし、最近でも山一証券が自主廃業になった時も山一の社員を引き取ったことでも有名である。日本経済新聞社の「外国証券人気度ランキング」においても88年の調査以来一貫してトップの座をキープしている。メリルリンチの現状はというと、97年の段階で世界43カ国に拠点を持ち従業員も5万6千人米国だけでも1万9000人を擁し総資産も37.6兆にも達しており、ROEも26,8%にも達している超優良企業である。
メリルリンチは、87年のブラックマンデーで大きな打撃を受けた後、2つの戦略転換をした。まず、市場変動リスクの大きいビジネスに依存するのではなく、安定したビジネスとバランスを測る戦略である。次にこれまでとってきた多角化を見直し競争力も収益力もない部門から撤退した。このメリットはすぐに現れ94年にFRBが金融政策を引き締めに方向転換し債券市場が暴落した時多くの証券会社は、大幅な赤字となったが、メリルリンチはダメージを最小限にすることができた。ここでメリルリンチの主要部門の戦略についていくつか紹介する。
まず、顧客主義を貫いていたことである。メリルリンチの顧客マーケティングの根本は顧客第一主義に合った。メリルリンチは他の競争会社と比べても米国の富が集中している中高年齢層の多くの顧客層を獲得していた。こういった人たちに最良のサービスが提供できるようFC(ファイナンシャル・コンサルタント)と呼ばれる人たちを使って顧客に合わせーニスを提供し、そのサービスに見合った手数料をもらうというシステムを取っていた。いわゆる顧客との利害相反を排除し、顧客重視の理念が利益を生む仕掛けを作っていたのである。また当市銀行業務においては、英国の大手運用会社のマーキュリーなどを買収し金融商品において優位を持つ一方で調査能力と総合提案能力を強化した。メリルリンチには全世界に400人ものアナリストを抱えており他の会社が軒並みリサーチ部門を縮小させる中であえて強化に取り組んだ。それが、当市推奨や企業提携などあらゆる提案ビジネス及びリテールの分野に生かされており、他の競合他社を圧倒している。組織戦略においてもスタープレーヤーに頼りすぎることなく顧客第一主義を維持する組織を重視した。これがコアカルチャーを守るきっかけともなっている。
3、ゴールドマン・サックス
ゴールドマンサックスは、20年も前から、米国の名門インベストメントバンクの代表格であった。そして今でも世界の投資銀行業界でリーダーシップを振るう名門である。実績を挙げてみると米国企業関連のM&A仲介業務において97年は18%のシェアでトップであり、またグローバルな株式・債券引受業務においては、マーケットシェア9%でメリルリンチに告ぐ第2位である。こうした輝かしい実績をもつため巨大な資本を持つ大銀行(例として、ドイツ銀行やJPモルガン)は、ゴールドマン・サックスを目標としてきた。しかし、どこもゴールドマン・サックスのようはなりきれず、追い越すどころか、追いつきさえできない状況である。
ここで、ゴールドマンサックスの経営を見てみると、やはり独自の当市銀行観を感じることができる。第1に、投資銀行のブランドを決めるのは、「超一流企業に対して、ゴールドマンサックスしかできないサービスを提供すること」を考えていることである。ゴールドマンは、米国及び世界の超一流企業との「リレーションシップ」サービスにこだわっている。と同時にあいて企業のもつ「最も困難で複雑な課題」に対する財務アドバイザーであろうとする。ゴールドマンの顧客主義は一流のエリート意識、ファーストクラス意識に支えられている。企業トップと深く長い関係を築くリレーションシップ・マネジャーと最先端をいく個別商品のプロフェッショナル、この組み合わせが強さの源泉だといえる。第2に、投資銀行の収益を決めるのは、「数少ない黄金の鉱脈を早く掘り当て創業者利益を手にすること」と考えていることである。当市銀行業務の商品のライフサイクルは短く、次々とブームになるビジネス、商品が現れては、あっという間に模倣されコモディティ化していく。いかに早く、高付加価値商品・ビジネスを開拓し、コモディティ化される前に利益を回収するかが収益の鍵を握る。特にリスクが伴う商品については、いかに高度で確実なリスク管理を徹底するかということが収益を促進する。ゴールドマン・サックスの強さは、各商品・ビジネスに業界トップクラスの専門家を擁し、IT技術を駆使して商品開発の先端を走り、政治力を駆使してアジア・東欧の国家財務プロジェクトに早くから食い込んでいることにある。同社は多くの分野でトップクラスの評価を受けている。第3に「どれだけ優秀な人材を採用し、育成し、ベストタレントを維持し、彼らをチーム力として信用できるかにある。そのため、人材の流失は業界の中では最も低い部類にある。同時に「チーム・アプローチ」を最大限生かすように、組織運営においては、部門間の壁を低くし、前線にチーム組織やチーム活動の権限を与え、報酬も個人だけでなくチームに応じたボーナスが支払われる仕組みも作られた。こうしてゴールドマン・サックスは「超一流顧客に対するリレーション・サービス」を「複雑かつ先端の金融商品・ビジネスの開拓」によって行い、そのために「最優秀の人材を採用・教育したうえでチームで協業させていく」方式を作っていく。これが良循環の原動力になっている。
また200年守り続けてきたパートナーシップについて言えばこの制度はパートナーが毎年の報酬の大部分をパートナーシップの持ち分権の形で受け取り、個人資産の大部分を資本として会社に提
供、一種の無限責任を負うという制度である。これは大きなリスクを負う反面、退職時にはきわめて高いリターンを享受することができる。こうした「リスクとリターンの一元化」によって経営陣の共同体意識を強め、意思疎通の滞りをほぐし、意思決定の早さを支えている。こうしたものがゴールドマンの強さであるといえる。
米銀の再生は、米国版金融ビックバン(金融自由化)が生み出した自由競争による淘汰と効率化がもたらしたことは前述したとうりにわかった。しかし、もう1つ情報通信革命の効果も忘れることはできない。
大情報処理技術、柔軟な分散ネットワーク、高度なビジネスソリューションの開発、インターネットの普及、こうした情報通信革命が古い銀行のビジネスモデルを刷新し、新しいビジネスモデルを持ったニッチプレーヤーの急成長を可能にしたのである。米銀の業務効率は過去7-8年に飛躍的に向上し、リスク管理やマーケティングの新しい経営管理スキルが開発され、支店に代わる電話やパソコンバンキング等の新しい販売チャネルが次々と普及していった。米銀は、80年代の不良債権処理が終わり、再生への活動と投資を始めた時に、ちょうど情報通信革命が起こり、その先端技術をフル活用して強い銀行のしくみを作り出すことができた。
情報通信革命は、銀行の伝統的ビジネスモデルを一変させようとしている。まず「顧客ベース」を取り上げてみると、従来のモデルでは「マス」顧客からせいぜい年齢や所得属性で切った「セグメント」顧客が対象とされるくらいであった。しかし大型並列コンピューターの発展で大量の情報処理ができるようになったいまでは、個々の対象とした
ワン・トウ・ワン・マーケティングがベースとなっている。一人一人の“顧客”に合わせた商品設計やアプローチが可能になることで、顧客の選択、顧客開拓、ヒット率、顧客満足はずっと向上した。「商品開発・設計」についても、従来のモデルでは銀行商品の品揃えは限られていた。しかし、コンピューターに支えられたデータベース・マーケティング技術によって開発期間が短縮され、いろいろな付加サービスを多少自由に設計できるようになっている。
そして、最も大きなビジネスモデルの変化は「デリバリーチャンネル」であった。従来は、言うまでもなく支店、それもフルライン機能を持った荘重な支店こそが販売チャネルの要であった。ところが、いまや顧客取引接点としての支店のシェアは、五割を切った。代わりにATMやビデオキオスク、そして電話、パソコンといった情報通信チャネルに取って代わられつつある。支店が消失するわけではないが、個人店舗法人店舗等の機能分化は進展しつつある。新しいデリバリーチャネルは昔の支店よりもはるかに安く、早く、便利なチャネルである。こうした技術を活用して新しいビジネスモデルを転換することにより、小さなプレーヤーが登場してきた。
日本でも、近年テレフォンマーケティングが店舗の補完的チャネルとして開発されつつあるが、英国では既に10年近く前に、店舗をまったく持たない、電話、郵便というダイレクトチャネル専門の銀行が誕生し、大きな成果を上げている。その代表例としてミッドランド銀行の子会社、ファーストダイレクトがある。
ファーストダイレクトの取り扱う商品は、決して新しい商品ではない。ミッドランド銀行がそれまでに提供してきたものと基本的には代わらない商品である。それゆえ、極めて明確な付加価値を顧客に提供することによって実行された。第1の付加価値は低コスト構造を生かした有利な預金・ローン金利である。ダイレクトチャネル専門銀行であるファーストダイレクトは従来の銀行に比べ低コスト構造を持っているためそのメリットを最大限生かしている。第2の付加価値は、24時間365日いつでも、電話を使って現金引き出し以外のすべての取引を行えるという利便性である。さらに現金引き出しも、ミッドランド銀行の既存のネットワークを使って、広範なCD・ATMの利用を可能にしてきた。第3の付加価値は、質の高いサービスを提供するのである。現在3000人を超えるスタッフを擁しているがその大半は十分訓練されているために、顧客一人一人に関するサービスが、あたかも幅広い知識を持った専属の営業マンが常に対応しているような状態を作り上げているのである。
このハンティントンは、全米銀行ランキングでは、40位前後の小粒な銀行である。しかし業績においては、ROEが17%を超えバンガメ、ネーションズといったスーパーリージョナブルバンクと伍する水準である。なぜハンティントンがこれだけの高収益を出すのかというと、情報技術を活用した最先端銀行であるからである。それは全米ではじめてスクリーン電話を利用したホームバンキング・サービスであるスマートフォンを導入、92年全米初の試みとして、ハンティントン・ダイレクト・バンク(365日、24時間アクセス可能なテレフォンバンキングサービス)、94年テレビ電話による相談サービスといった具合に他行に先駆けて最新情報技術・機器を利用したサービスを導入している。
ハンティントンは、伝統的なチャネルから最先端のチャネルまで幅広い種類を抱えて、顧客にサービスしている。従来型の支店への来店客がどんどん減り、通販や電話でのセールスへとシフトしている。顧客調査でも「自分のお金は、他人の人手を介することなく自分で管理していきたい」という傾向はどんどん強くなってきている。そこでハンティントンは旧伝統的な支店チャネルをどんどんと閉じていった。このようにしてマルチメディア端末を使ってサービスを行う拠点を作り、コスト削減を行ってきた。こういった最新のサービスを提供することにより利益を拡大させていった。
4、グリーンフィールド・アタッカーの躍進
今、日本の金融機関は経営体力が弱まり、貸し渋りすら起こっている。金融業界自体が構造不況業種だといわれたりもしている。しかし金融市場そのものは成長企業である。老齢化とともに個人金融資産1200兆市場はますます運用商品を求めてくるはずだからである。個人の住宅・消費者ローンは年率10%近くも伸びている。中小企業の外部借入依存度は高まっており、景気回復は資金需要も大きいはずである。また大企業は証券金融へ移行しつつあり、将来の証券市場は成長することが約束されされている。また企業リストラによりストラクチャード・ファイナンス支援ニーズも高い。さらにエレクトロリック・コマースの進展は金融と商流、情報流を融合させていき、そこに新しい金融機関が生まれようとしている。成長する金融機関と低迷する伝統的な金融機関のギャップ、このギャップをチャンスとばかりに、金融市場に参入して急成長しているグリーンフィールドアタッカー(更地に自由設計で建築するような人達の意)がいる。伝統的な金融機関が、業界のタブーや内部規制のしがらみで新しい対応ができないうちに、ゼロベースの発想で新しい金融サービスを始めようとするプレーヤーである。こういったプレーヤーは前述したファーストダイレクトなどのような、情報通信革命の落し後たちもその一つであるが、流通・通信・メ-カー・不動産といった他業界からもグリーフィールドアタッカーが生まれてきている。
グリーンフィールドアタッカーの強さは発想が自由なことである。彼らは、新規市場に殴り込むにあたって決してエクセレントバンクや伝統的な銀行業のやり方を学ぼうとせず、むしろ、遅れてきた者の優位性をどう生かそうかということに思考している。彼らに共通していることは、「いかにして銀行と差別化し、銀行の旧慣習にはまらないか?」という思想を持っていることである。
GEキャピタルは1997年の総資産は2500億ドル、利益が3255万ドルであり、5年間連続で2桁の成長を続け、ROEも22%に達する。米国のエクセレントバンクでも15%前後、日本の金融機関に至っては一桁である。これからして、いかに高収益を挙げているかということがわかる。GEキャピタルの戦略はエクセレントバンクの用いている、市場を横断的に捉え、川上から川下まで「バンドル」(束ねた)した機能を持っていくことで優位性を築けるのだと思われている、こうした戦略を否定したものとなっている。まず第1にGEキャピタルは自由化によって金融市場は拡大するのではなく、より「細分化」され、機能はバンドルされるのではなく、「アンバンドル」(分解)されるものとみる。なぜなら、商品や価格が規制品ではなく自由設計品になれば、顧客の商品選択が強まり、そこで細分化されたし市場ごとの競争が始まり、個々の分野ごとで専門的な商品を求めてくる。さらに、金融技術の発展により、アンバンドルされた個別機能ごとに、独自のスキルやインフラを持つプレーヤーが活躍できる場が生まれるからである。第2に彼らは激化する競争に勝ちぬくために高い収益を上げうる金融機関は、細分化された市場におけるナンバーワンプレーヤーであり、中途半端な三番手は苦戦するというものである。また多角化を転換する場合、普通はまず既存の中核事業をテコに新規参入し、企業文化に合わせながら育成するのが成功への近道というのが、経営の常識である。つまり「小さく生んで大きく育てる」ということだ。これに対してGEキャピタルはまったく逆の発想をしている。いち早く一定規模に達するためならば、自力では間に合わない。むしろ企業を「買って育てる」というのがGEキャピタルの考え方である。買収によって企業文化の違いからくる衝突についても買収先の異文化を受け入れる企業風土を作ればよいのではないかという考え方である。こうして見ると積極買収のように思われるが、この戦略は実は育てることの方に力点が置かれている。GEキャピタルは事業部にあえて収益性と成長の両方を、それも高い目標を求めている。しかし経営困難な会社を買収をしたとしても、経営を立て直すまであまり時間はない。
買うことより育てることのほうが難しいことは言うまでもない。GEキャピタルは育てる方法を2つほど持っている。一つは、AAA格付けに象徴されるずば抜けた財務力を生かせば安い資金を大量投入し財務の改善を行う。AAA格のため、調達コストだけですぐに経費削減ができるからである。もう一つは、世界クラスのオペレーショナルの優位性を移転する力である。シックス・シグマといわれる運動で培った高品質化の追求はそのまま企業文化となっている。ところで、企業のビジネスドメイン
異業種の中でも、最も金融事業に近いとされているのが小売業であり、その代表例として、英国のテスコ・パーソナル・ファイナンスとセインズベリー・バンクがある。この二社は、なぜ金融業に参加したというとショッピング・ポイント・プログラムの成功によるものである。二社とも会員になったら1%還元するというショッピング・ポイント・プログラムを導入したところ両者とも1000万人近い会員を獲得することになった。この会員を生かす形で金融事業に手を出し始めた。もともと両者ともチャネルとして電話・郵便を中心にして低コスト構造の体制を整えた。加えてCD・ATM,もしくはインストアプランチを設置するためにも、極めて集客力のある自らのスーパーに設置すればよいのであり、採算を確保しやすいという面も持っている。
そしてこの二つの顧客獲得戦略は、極めて明確な付加価値を顧客を提供することによって実行された。まず低コストを活かして有利な預金・ローン金利を提供したことである。そして利便性である。顧客は、口座の開設からローンの申し込みに至るまで幅広い銀行取引を24時間365日いつでも電話を使って行うことができる。加えて、現金が必要な場合は合弁銀行のネットワークを広範なCD・ATMを使えるうえに、スーパーのレジでも現金を引き出せるようにした。もう一つとして、スーパーの御買い物特典に金融商品を組み合わせていることである。このようにしてうまく成功を収めた。
<終章>日本はどうなるのであろうか?
今、日本の金融業界はビックバンが始まったことによりいよいよ競争の波に飲まれていくことになった。もともと外国の金融機関が、安定な収入源があり、顧客を囲い込む手段である資産運用に力を入れている今、日本の1200兆の個人金融資産市場、および厚生年金と税制適格年金を合わせた約80兆の企業年金市場は極めて魅力的であるといえる。そのため続々と外資が参入していた。彼らは、日本の金融機関などが抱える不良債権処理などでも高収益を挙げており、またメリルリンチが山一の効率のよい店舗および人材を引きとったりGEキャピタルが東邦生命を事実上傘下に収めたりと買収も行われるようになった。こうした中、日本では、悲観論ばかり出るようになり外資に乗っ取られてしまうのではないかと心配する人もいる。実際利益は、欧米金融機関とでは比べ物にならないくらい低い。しかもシステム、商品開発、戦略面においても随分遅れているといわれている。でもそれは、外国から学ぶことによって何とかできるかもしれない。むしろ戦略面、企業文化面において変わらなければいけないところが多いようにおもえる。しかしまだ日本勢は、日本においては顧客基盤、チャネル、人材のすべてにおいて優勢を保っている。だからこそこの優位があるうちに、カルチャーを改革し人材を揃えるべきであるといえる。また米国では、弱いところはどんどんとつぶれていったが、日本では護送船団方式のせいで強い金融機関に弱い金融機関の尻拭いを指せてきた。こういったことは、金融業界の成長を阻み、競争をなくすので早急になくすべきであるように思った。
今になって、日本の金融機関も金融再編も始まりまた公的資金によって、当面の危機も回避された。今こそ奮起すべきであると考える。
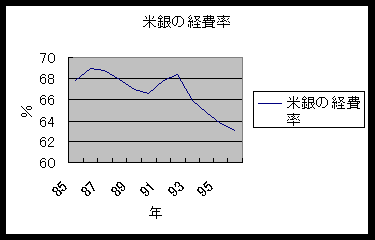
 <図1>
<図1>
<図2>
世界の主要金融機関ランキング (億ドル、97年)|
金融機関名 |
国籍 |
総資産 |
株主資産 |
純利益 |
時価評価額 |
ROE(業務ベース)% |
|
|
シティグループ |
米 |
6980 |
441 |
75 |
1350 |
36 |
|
|
バンアメリカ |
米 |
5250 |
62 |
1270 |
|||
|
AIG |
米 |
1480 |
33 |
880 |
|||
|
UBC |
スイス |
6630 |
208 |
32 |
680 |
19.9 |
|
|
チュースマンハッタン |
米 |
3660 |
217 |
24 |
570 |
30.9 |
|
|
東京三菱銀行 |
日 |
6910 |
213 |
3 |
560 |
19.4 |
|
|
HSBC |
英 |
4010 |
232 |
52 |
540 |
31.8 |
|
|
ING銀行 |
オランダ |
2780 |
207 |
83 |
530 |
12.6 |
|
|
ドイツ銀行 |
ドイツ |
5700 |
175 |
14 |
400 |
13.3 |
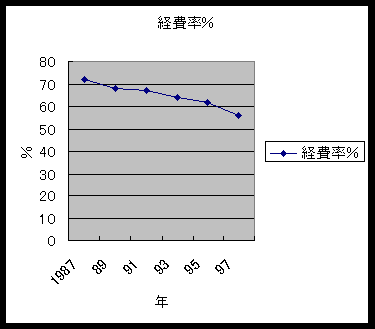 <図3>
<図3>