
新型コロナウイルスの流行により、社会全体で各種イベントの中止が見込まれる中、毎年夏に私たちが行っていたゼミナール合宿も今までの形式では実現が難しいとされました。そんな中、望月教授と川崎市のご厚意により、川崎市への課外学習という形で今年度の夏合宿が実現しました。
さて、今回の課外活動では、川崎市の方にお話を聞きに行きました。望月教授と川崎市の講師の方で毎年開講される「寄付講座(川崎市役所)」の導入及び振り返りを目的とし、学年を問わず川崎市への理解を深めました。
川崎市の方からは「環境(スマートシティ、水素自動車など)」「危機管理(コロナ対策など)」「社会福祉(引きこもり支援や高齢者支援など)」をお話しして頂きました。
また、終了後にはゼミ生の交流会を「Paz Coffee Shop」で開催し、ゼミ内での交流も活発に行いました。

密集対策→多摩区役所で30名以上入る会議室を利用し、極度に狭い空間で密集することを避けた。
密接対策→全員マスク着用とし、座る席の間隔を確保する。→席を1席以上開けて座った。
密閉対策→入口ドアは常時開放とし、十分な換気を行った。
その他対策→ 入室時にアルコール消毒液による手指の消毒を行った。
密集対策→30名以上利用可能な店舗を貸切で利用し、極度に狭い空間で不特定多数の人々と密集することを避けた。
密接対策→全員マスク着用とし、座る席の間隔を確保した。
密閉対策→お店の空調設備を活用し、適宜換気を行った。
その他対策→入店時の消毒液の使用や従業員による定期的な消毒といった感染対策に従い店内での感染予防に努めた。
各学年から代表して1人ずつ感想を掲載します。
今回、川崎市多摩区役所を訪問し、率直に感じたことは市の運営のスケールの大きさであった。小さなことから大きなことまで多岐にわたっており、私の想像をはるかに超えていて非常に興味深いものが多く見られた。時間の都合上、全ての業務を見ることは不可能であったため一部のみを今回は取り扱ったが、その内容も深堀りしていくと興味深く、大変奥が深いと感じた。
武蔵小杉のタワーマンションの話が話題に出されたことに関して、私も老朽化や住民の数の推移を考えており、これから地震などの自然災害やインフラ整備に関しては様々な方法が私の中にあった。だが今回の話を聞き、そう簡単に解決できるものではなく、事の難しさを改めて理解し、考えていかなければならないものだと思う。
また、日本の人口減少によって、当然川崎市だけではなく、東京の主要地域におけるタワーマンションの入居者までいなくなり、深刻な空き室だらけになると以前新聞で見たことを思い出した。おそらく、川崎市は東京よりも深刻なダメージを受けるのではないかと予想する。そのような状況を少しでも抑えるために、川崎市が行っている事業などを把握することができたので、これらが今後どのように貢献していくかが楽しみである。
今回、初めてこのパブリックコメントというものを知ることとなった。早速川崎市のホームページで見てみたが、意見は少なく思っていたほどではなかった。ただ、この機能に関しては市からの今後行っていく事業が詳しく書かれており、だれでも理解しやすいと思われた。当然何か事業を行っていくためには、住民の意見が大切なのではないかと考えているため、積極的に使われてほしい。そのためには住民にこのような機能があるということを知ってもらうことが不可欠であるため、宣伝していったほうが良いのではないかと思う。(2年生)
今回、川崎市の方からお話を聞く前に、昨年受講した川崎市寄付講座の内容を思い返していた。そこで強く印象に残ったのは「川崎市でも財政に余裕がある訳ではない」という内容で、今回も川崎市の方からそのような内容を聞き、今後の動向に注目して見ていきたいと思う。そして寄付講座よりも踏み込んだ話として引きこもり支援の話があり、川崎のみならず日本全体で共通して考えていく問題だと感じた。重要な問題であるのに「どの部署がどのように行うかが明確になっていない」という点にはある意味危機感を感じる。
近年出てきた新しい問題であるし、一度引きこもってしまった人を社会復帰させるのも簡単ではない。小学校、中学校などの学校生活でトラブルがあり引きこもってしまうと抜け出しづらく、なかなか相談しようともしない。このような現状を踏まえたうえで、解決につなげられる方法としては「相談しやすい環境を作る」「社会復帰につなげられる場を作る」、というような2つの手法を早急に取るべきだろう。
また、引きこもり支援だけではなく、私の興味があるスマートシティの分野に関しても東芝と川崎市の取り組み例や、パプリックコメント制度で意見を言えることがあると知った。 今回の川崎市のお話を通して、普段通っているだけである川崎市の印象が変わり、興味を持てた。後期の寄付講座もSAを担当するので、楽しみにしたい。(3年生)
夏合宿は予定通り行えませんでしたが、川崎市職員の方からお話を聞ける貴重な機会でした。準備段階として前日に川崎市がどのような取組を行っているのか個人的に調べてみました。市が積極的な環境づくりに取り組まれていることを知り、非常に魅力的に写りました。特に、臨海部の水素インフラ整備に関してはエネルギー資源の乏しい日本にとっても重要課題であり企業、海外と連携を図った取組をされているのは驚きでした。
実際に質問させていただいた際には、スピード感を持って行っているわけではなく、長期的な視野を持ってまずは市民の方に水素を使ってできることの意識づけを行っていることがわかりました。海外出張調査を行なっているデータもありこれからの川崎市臨海部が楽しみです。川崎市職員の方のお話で他に印象が強かったのは、「自助・共助・公助の連携」です。コロナ禍で生活保護を受ける人数に拍車がかかる中、自己管理を意味する自助、そして近所の方と助け合う共助の部分は今現在求められているというお言葉に共感しました。
実は今朝、牛乳配達のアルバイトがあったのですが、お一人で住まれている高齢者の方は意外といて、宅配の人との会話を楽しみにされていました。このような関係も勿論大切ですが、近所通しで関係性を持つことも意識しようと強く感じました。(4年生)
川崎市の方のお話を聞いた後、ゼミ生同士の交流会を実施しました。2年生から4年生まで、ビンゴ大会や教授にまつわるクイズなどで楽しい時間を過ごしました。
4年生の先輩方からも1人ずつお言葉を頂き、これからのゼミナール活動や就職活動に関するアドバイスをもらいました。
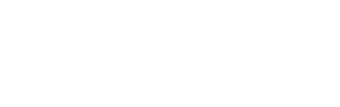
ミニクイズ: 望月ゼミのホームページは何年に開設されたでしょう?
(1)、1992年 (2)、1996年 (3)、2000年
正解はゼミHPの上部に!
今回の川崎市での課外活動を通して、普段通学している川崎市の取り組みや課題を聞くだけではなく、ゼミ生が質問することによる意見交換も行うことができました。全学年からの感想を見ると川崎市に対しての理解が深まり、望月教授が担当されている「寄付講座(川崎市役所)」の内容よりも細かいお話が聞けました。今回の課外学習を踏まえて、日頃から川崎市のホームページを参考にして情報を得るほか、市民からの意見を集うパブリックコメント制度があると市の方から教えてもらったため、大学生として考える川崎市の課題や改善案について意見を出していこうと思います。
最後に、お忙しい中講演をして下さった川崎市の方々、実現に至るまで最後まで調整をしてくださった望月教授、課外学習の許諾をして下さいました経済学部長・専修大学長に心より感謝を申し上げます。
川崎市の方からのお話で「川崎市の農業」に関しては農家の数も減少し続けていて、他の市と比べても農業を扱う組織が小さいという課題があった。確かに川崎市の農業といっても自分の中ではイメージがあまりなかった。
そこで、筆者は川崎市や神奈川県産の農産物を主に販売している「JA セレサ川崎 ファマーズマーケット セレサモス麻生店」に足を運んだ。

写真:セレサモス麻生店で購入した川崎産の品々
お店の近くである麻生区黒川で採れたりんごを使用したジャムや、同じ麻生区で採れた梨の他、ミニトマトやほうれん草など、想像よりも川崎産の農産物が多くあることが分かった。それ以外に、写真に写っている「岡上エール」というクラフトビールは、東京都町田市の和光大学と、川崎市麻生区の農園がコラボレーションして生み出した製品で、多摩区の醸造所で作られているそうだ。
私がアルバイトをしているスーパーではこうした川崎で採れた物を見る機会は無く、やはり実際に直売所へ足を運んでみた価値はあったのだと感じる。今後川崎市の農業を活気づけられるために私たちができることとしては、専修大学と川崎市の農家がコラボレーションした製品の発売や、学食で川崎産の農産物を使用したメニューを出す・購買会で販売するといった事ができるのではないか。この機会に自分自身でもできる事を考え、改めて川崎市や大学に提案してみたい。
参考:カナロコ 地元産フルーツでビール 川崎、学生らが開発
( https://www.kanaloco.jp/news/life/entry-22902.html )