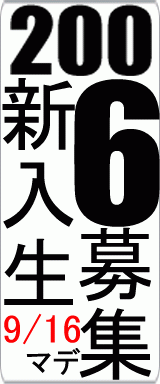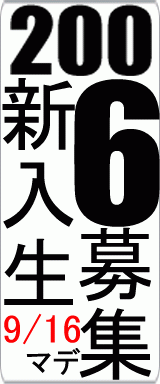|
宱嵪暘愅僛儈偱偼丄暘愅庤抜偲偟偰偺忣曬張棟媄弍偺棙梡丒宱嵪暘愅偵廳揰傪偍偒枅擭偺僥乕儅傪婎偵妶摦偟偰偄傑偡丅
梌偊傜傟偨僥乕儅偵偍偄偰宱嵪暘愅偵偍偄偰昁梫晄壜寚側抦幆乮寁検丒棟榑丒忣曬婎慴乯傪妛傫偩忋偱丄偦傟傜傪巊偄僨傿僗僇僢僔儑儞偲偄偆宍偱傾僂僩僾僢僩偟偰偄偒傑偡丅
傑偨丄杮僛儈偺摿挜偲偟偰丄傾僂僩僾僢僩廳帇偱偁傞偲偄偆揰偑忋偘傜傟傑偡丅僛儈帪娫偱偼僨傿僗僇僢僔儑儞偵偁偰傜傟傑偡丅偦偺偨傔丄帺暘偺堄尒傪敪昞偟丄懠偺堄尒傪暦偒擖傟傞偙偲偱
帺暘偺抦幆偑掕拝偟丄怺傒偑憹偟偰偄偔偙偲偑幚姶偱偒傑偡丅
傑偨丄尰嵼偺擔杮偼崙嵺壔偑恑傒宱嵪傪峫偊傞忋偱傕擔杮偩偗偱偼峫偊傞偙偲偑晄壜擻偲側偭偰偄傑偡丅偙偺崙嵺壔偺拞偱妶桇偟偰偄偗傞恖嵽傪堢惉偡傞偙偲傪栚昗偲偟偰偄傞僛儈偑
崙嵺斾妑僛儈僫乕儖偱偡丅摿挜偲偟偰偼塸岅帒椏傪岎偊偰偺斾妑丒暘愅傪峴偭偰偄傑偡丅
|
仠 2002擭搙丂丂乽僗儔僢僋僗乮帒尮偑桳岠妶梡偝傟偰偄側偄忬懺乯宱嵪乿 |
丂丂擔杮宱嵪偑僗儔僢僋僗偵娮偭偰偄傞偲偄偆擣幆偺壓丄嵿丒嬥梈丒楯摥偺俁巗応偵偮偄偰丄偦傟偧傟儅僋儘丒儈僋儘丒崙嵺偺俁斍偵暘偗偰尰忬暘愅傪偟傑偟偨丅暘愅偺恑傔曽偼丄傑偢僛儈慡懱偵偍偗傞僗儔僢僋僗偺掕媊傪妋擣偟丄奺斍撈帺偵僗儔僢僋僗傪偳偺傛偆偵暘愅偡傞偐曽恓傪寛傔丄奺帺偑帩偪婑偭偨帒椏傪傕偲偵媍榑傪恑傔丄寢榑傪摫偔偲偄偆曽朄偱偡丅寢榑偼僗儔僀僪偺宍偱慡懱偵敪昞偟丄幙媈墳摎傪峴偄丄嵟屻偵俁斍偺寢榑傪傑偲傔傑偡丅偙傟傪奺巗応偵偮偄偰峴偄丄嵟廔揑偵慡巗応偺傑偲傔傪嶌惉偟傑偡丅
丂埲忋偺暘愅偐傜摼傜傟偨寢榑偼丄妋偐偵擔杮宱嵪偼僗儔僢僋僗偵娮偭偰偍傝丄嬶懱揑偵偼乽愽嵼惉挿棪偺掅壓乮嫙媼偺尭彮乯乿偲乽俧俢俹僊儍僢僾偺敪惗乮廀梫偺尭彮乯乿偲偄偆宍偱尰傟偰偄傞偲偄偆傕偺偱偟偨丅偦傟偵傛偭偰丄擔杮婇嬈偺崙嵺嫞憟椡偑掅壓偟丄搳帒偑尭彮偟丄幐嬈偑憹壛偡傞側偳偺埆弞娐偑寽擮偝傟偰偄傑偟偨丅
丂丂恖乆偺彨棃傊偺婜懸偼丄宱嵪偵塭嬁傪梌偊傞偲偄偆慜採偺壓丄嫀擭偲摨偠傛偆偵嵿丒嬥梈丒楯摥偺俁巗応偵偮偄偰丄偦傟偧傟儅僋儘丒儈僋儘丒崙嵺偺俁斍偵暘偗偰尰忬暘愅傪偟傑偟偨丅奺帺偑帩偪婑偭偨帒椏傪傕偲偵斍偛偲偵媍榑傪恑傔丄寢榑傪摫偔偲偄偆曽朄偱偡丅寢榑偼僛儈撪偱僾儗僛儞僥乕僔儑儞傪峴偄丄幙媈墳摎丄嵟屻偵俁斍偺寢榑傪傑偲傔傑偟偨丅嶐擭偼崙嵺斾妑僛儈偲偺傾僂僩僜乕僔儞僌偺堦娐偲偟偰丄崙僛儈偵奀奜斾妑傪峴偭偰傕傜偭偰偄傑偡丅
丂楯摥巗応偱偼恖乆偺彨棃偺掅壓偑婲偙傞尨場傪丄婇嬈懁偱偼楯摥巗応偱偺栤戣傪嫇偘丄楯摥幰懁偱偼庒幰偺摥偔堄幆偺曄壔側偳傪嫇偘偰偄傑偡丅嵿巗応偱偼彨棃偺婜懸強摼偺掅壓仺徚旓掅壓丄搳帒堄梸偺掅壓側偳偵傛偭偰俧俢俹偵塭嬁偑偱偰偄傞偲偺暘愅傪峴偄傑偟偨丅
丂俀侽侽係擭搙偺僛儈妶摦偼嵿丄嬥梈丄楯摥偺嶰斍偵傢偐傟丄庡偵慜婜偼儈僋儘丄屻婜偼儅僋儘偺帇揰偐傜乽嫞憟椡乿偲偄偆僥乕儅偵偮偄偰暘愅偟偰偒傑偟偨丅
丂嵿斍偱偼慜婜偼峲嬻丄帺摦幵丄塼徎偲偄偭偨嶻嬈傪傒偰偄偒丄庡偵嫞憟椡偺尮愹偲偼丄塼徎嶻嬈偱偼廀梫偵墳偠偨岠棪壔丄惢昳嵎暿壔丄峲嬻偱偼婯惂娚榓丄宱塩帒尮偺桳岠妶梡丄帺摦幵嶻嬈偱偼丄僽儔儞僪僇儔乕偵憡墳偟偄嵎暿壔丄岠棪壔傪嫇偘偰偄傑偡丅屻婜偼惉挿榑傪巊偭偨慡梫慺惗嶻惈偺悇堏傪暘愅偟傑偟偨丅
丂嬥梈斍偱偼慜婜偱偼庡偵嬧峴峴摦偵偮偄偰暘愅偟丄婯惂娚榓側偳嫞憟揑側巗応傪惍旛偡傞偙偲偵傛傝慡懱揑偵僐僗僩嶍尭偑峴傢傟廂塿岦忋偮側偑傞丄偟偐偟尰忬偵偍偄偰偼婯柾偺宱嵪傕斖埻偺宱嵪傕桳岠偵摥偄偰偍傜偢丄嬈愌偺傛偔側偄偲偙傠傪拞怱偵慖戰偲廤拞偲偄偆怴偨側摦偒傪尒偣偰偄傑偡丅屻婜偼儅僋儘揑側帇揰偐傜壠寁偲婇嬈偺帒嶻峔惉偵偮偄偰暘愅偟丄壠寁偲婇嬈偺億乕僩僼僅儕僆偺堦抳傪幚尰偱偒傞巗応偑廳梫偱偁傝丄壠寁偲婇嬈偺峴摦偵偁偭偨嬥梈巗応偱偁傞偙偲偑廳梫偱丄偦偺偨傔偵偼姰慡巗応偱偁傞偙偲偑昁梫偱偁傞偲偺寢榑偵帄傝傑偟偨丅
丂楯摥偱偼慜婜偼婇嬈偺屬梡傪拞怱偵暘愅偟偰偒傑偟偨丅偦偺拞偱恖審旓埑弅偺攚宨偵偼丄婇嬈偑嬈嫷偵墳偠偨恖堳傪抏椡揑偵曄壔偝偣傛偆偲偡傞孹岦偑偁傝丄抏椡揑偵曄壔偡傞屬梡娐嫬偺側偐丄恖嵽棳幐側偳偺暰奞偺崕暈偲偟偰丄恖嵽偺堢惉偺嫮壔丒妋曐偑婇嬈偺乬嫞憟椡乭偵偲偭偰壽戣偲側傝傑偡丅屻婜偱偼楯摥巗応偺儈僗儅僢僠傪嫇偘丄夵慞偡傞嶔偲偟偰丄嘆嫵堢孭楙惂搙傪廩幚偝偣偰丄峔憿揑幐嬈傪夵慞偝偣傞丅嘇楯摥堏摦偺慾奞梫場偑偁傝丄廀梫懁偲嫙媼懁椉柺偵偍偄偰栤戣偲側傞擭岟彉楍宆捓嬥懱宯傪尒捈偡丅嘊楯摥堏摦傪墌妸偵偱偒傞娐嫬傪嶌傝丄偦偙偐傜堏摦偑崲擄側崅楊幰傪妶梡偟丄幐嬈栤戣偺夵慞傪恾傞偲偄偆寢榑偵帄傝傑偟偨丅
丂嫞憟椡偲偄偆奣擮偼宱嵪妛偱偼掕媊偑偝傟偰側偔丄旕忢偵擄偟偄僥乕儅偱偁傝丄嫞憟椡偲偼壗側偺偐偵偮偄偰偼堷偒懕偒暘愅偟偰偄傑偡丅
|