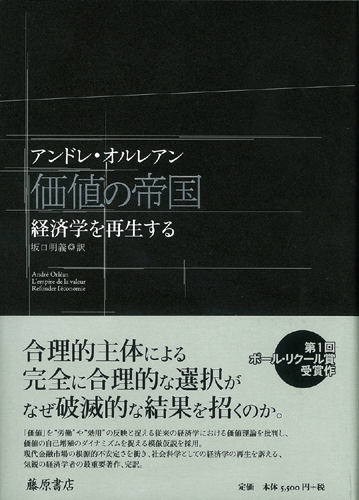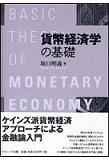■経済学の正統性危機を打開すべく,主流派(新古典派)経済学を その価値論に遡って批判し,コンヴァンシオン(慣行)理論に基づく代替理論を提示。貨幣動機で動 く現実の市場を分析するのに必要な経済学理論とはどのようなものか――読者諸氏に考えていただければ 幸いです。
■書評:『産経新聞』2014年1月12日付(田村秀男氏),『週刊東洋経済』 2014年1月18日号(橋本努氏),『図書新聞』第3154号(原田裕治氏,2014年4月12日)
■紹介:『朝日新聞』2013年12月7日付,『日本経済新聞』2013年12月7日付。