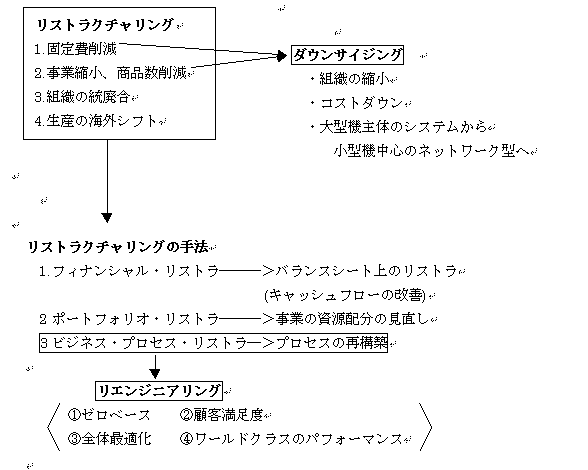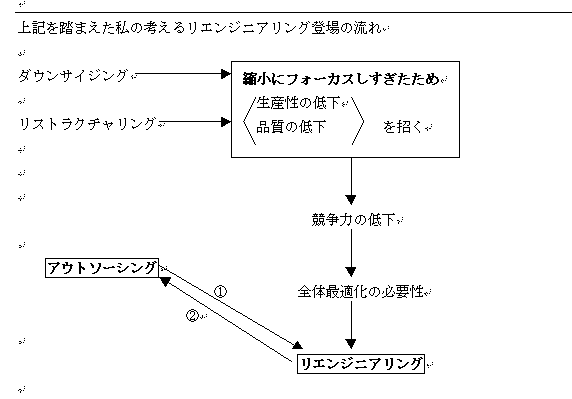最終更新日: 1998/07/18.
論点
その他
生産性、実質賃金、国際競争力の関係
akinori wakabayashi <e080123@isc.senshu-u.ac.jp>
物価上昇率(P)=名目賃金率の伸び率(W)-労働生産性の伸び率(H)と
いう式から、H=W-Pとなる。日本の場合、生産性を上げようと考えると、賃
金を上げずに価格の低下を求める傾向にある。また、H=(W/P)とも表わ
せ、生産性の伸び率=実質賃金という式が成り立つ。これは生産性があるから実
質賃金は上がるということを意味している。X=e(P/Pf)という式は、国
際競争力=実質為替レートの変化率である。e=為替レート(円の価値)、Pf
=輸入品の物価水準、P=国内の物価水準
日経NEEDSからデータを取った前に送った数値からも分かるように、eが上
昇すること(円高になること)や、国内の物価水準(P)が、輸入品の物価水準
(Pf)より上がることは、国際競争力が落ちているという事が分かる。X=e
(P/Pf)という式は、X=e+P-Pfとも表わせ、先ほどのH=W-Pの
2式から、X=e+W-H-Pfとなる。この式から国際競争力をあげるために
は、輸入品の物価水準が上がることや、生産性を上げること、円安になること、
などの条件が必要だ。では、生産性を上げるためにはどうすれば良いのだろう
か?生産性向上の決定要因は①科学知識の進歩、②企業の技術吸収力、③経済的
な技術取り込み意欲、の3つが挙げられるが、②と③が特に重要で、企業または
政府の技術吸収力が生産性向上には必要だ。専門的な分業と、柔軟な分業のとこ
ろでも考えたように、日本は柔軟であるために技術取り込み意欲や、吸収力は意
外と優秀である。しかし、日本のアメリカに対する競争力の低さや、物価が高い
ことは、労働生産性の絶対水準の低さが要因となっている。
⑧ 情報化社会で考えるべき視点について自分なりにまとめよ
●●● E080596H 糀谷 一泰
7月8日の宿題
近い将来の2001年にやってくる金融日本版ビッグバンにおいて、日本が抱えてい
る情報化社会における閉鎖性は危機迫るものがあると考えられる。まず今までは、日
本企業との間のぬるま湯にでもつかっているような、お気楽な市場で競合していたが
これからは世界の企業を適にまわさなければいけない。特に情報先進国であるアメリ
カは今まで培ってきた技術と大規模なネットワークを駆使して1200兆円ともいわ
れる日本の個人貯蓄を取り込もうと躍起になってくるであろう。このままの日本の状
態では勝ち目はないに等しい。
中でも近年における世界の通信会社のグローバリズム化・自由化は目をみはるものが
ある。情報通信機器や半導体の関税を2000年までに撤廃することを視野に入れ世
界は動いている。一ついえることは、金融・情報・通信の大競争はこれからである。
ものすごい早さで変化する情報通信技術に対応しつつ、FREE・FAIR・GRO
BALな競争の条件を整備する必要がある。そのためには情報の開示がまずは不可避
である。日本を出来るだけ早く、完全情報下にしていかねばならない。
昨今の日本の経済状態ではこの問題から取り組むのは難儀だが、早急に不良債権問題
を処理し、情報産業における抜本的な規制緩和などを推進していかなければ今後の日
本経済全体に対する行く末は危ういものと思われる。
●●● E08-0860F 大慈彌 ゆう子
情報化が進むことは、基本的にはとてもいいことだと思う。
特に日本のように市場が閉鎖的な場合、情報化し開示していくことで今よりもか
なり経済が活性化すると思う。現在の日本社会は決して情報化されているとは言
いがたいところにあり、そのために不完全な情報に基づいた意思決定、または財
の選択を行なっている。
これはある意味、日本社会は リスク・テイカーではないかと私には思われる。
このような非生産的な社会構造のままでは、日本がやっていけない事は明らかな
ので、早く情報を明確にしていくシステム作りが重要となってくると思う。
ただ、情報がある程度明確になってきたら、そこで打ち止めしても良いと思う。
それは、世の中にはリスク・テイカーとリスク・アバーターがいるからである。
リスク・アバーターにとっては、今以上100%未満の明確な情報が手に入れば、
それに基づいた意思決定をはかれば良い。また、リスクテイカーは情報の確実性
は100%ではないので、そこに投資すれば良い。
どこまで、情報化を進めるのか、そしてどこまで情報化を進められるのか、これ
は日本にとってとても大きな課題だと思う。
●●● Yadoiwa
前回の日本電信電話公社がNTTに変わった理由で、技術の進歩が規制を排除していくのだと思いました。それまで
参入するのに莫大な費用を要した産業でも、技術の進歩がそれに取って代わり、新たな企業の可能性を引き出すことに
なると思います。競争相手がいなければやはり成長はしないと思います。今回のような国による規制は、日本の電信電
話産業を弱体化してしまったことが分かりました。そのため現在、この産業の国際競争力がなくなってしまったのでし
ょう。このような政府の失敗を繰り返さないようにしなくては行けません。これからの成長産業、特に情報産業では、
過度の規制はやめて、市場の失敗起こる時のみ、適格の場所に最小限の規制をするべきだと思いました。
今回驚かされたのは、アメリカでは60年代にすでに知識産業が定義づけられ、テクノクラートが社会の中心になっ
て、情報化社会を引っ張っていくとしめされていたことです。
またその重要性から、高学歴主義の人材教育システムに換えていったいったことです。確かに日本はアメリカに比べ、
情報産業は遅れているけれど、この時間的な差を考えると、当たり前なのかもしれないと思いました。
これからは更に情報化が進むにつれて、テクノクラートの重要性は増してきます。そのためにも、日本も速い段階での
教育改革が必要だと思います。義務教育段階でコンピューターに深くなれさせることが必要だと思います。そこで基礎
をマスターさせて、大学でもっと専門的なことをする必要があるでしょう。
不完全情報のもとでの意思決定では、効用の受け止め方によって、決定の違いが出てくると分かりました。考えてみ
たら、何でも成功を収める人は、リスクテーカーなのかもしれませんが、そのような人は日本人には少ないと思いまし
た。今後の金融ビックバンでは、このようなリスクテーカーを軸にまわっていくのだろうと思いました。
●●● shunichiro mitsutake
前回の授業で、1985年にやっと通信の規制緩和が行われ、日本電信電話
公社が株式会 社になり、この規制緩和元年が大きな意味を持っていたことを知
った。しかし、実際のとこ ろ通信価格設定が高く、米国と比べると十分には下
がらず大きな価格差があったことを知っ た。
今回の授業では、不確実な情報の下での意思決定の問題で、期待効用が高く
なるような選 択を行うことが合理的であるとなった。そして効用の受け止め方
により危険に対する態度が 異なること事が分かった。自分はその中でもリスク
ァバーターであった。しかしこれからの 経済が発展していくためには、むしろ
リスクテイカーが必要なのだと思う。リスクを背負う 分だけ膨大な利益を得る
可能性があるからだ。
これは不完全情報の場合であり、情報化社会により完全情報になっていき不
確実な情報が 明確になっていくだろう。そうすれば経済効率は今までより高く
なるだろう。でも不完全情 報の場合の期待効用の理論で見られたリスクテイか
ー的な態度は今後のビックバンの成功に も必要だと思う。だからこの態度は情
報化によって完全情報になっても失ってはいけないも のだと思う。
●●●Daisuke Unpou
情報化社会は不完全情報を改善し、より完全情報の状態に近づくことが可能であ
る。完全情報の下では不完全な情報を与えられた場合より効率的な行動がとれ
る。例えば、完全情報の下では生産量が上がる。しかし、情報化社会が進む事に
より問題点もでてくる。知識を持つ人とそうでない人との格差の広がりや、情報
によってみんなが一斉に同じ方向に向くような危うい状態になる危険性も持つ。
●●● 朝賀 浩之
<情報化社会で考えるべき視点について>
これまでの不確実性の社会では、モラル・ハザードや逆選択などの経済行動をと
ることが考えられる。また、不完全情報下での非対称性の存在は、今日の日本が
直面している多くの経済問題を生み出したといえる。しかし、今後の完全情報へ
の進展(=情報化社会)は、これらによる経済効率の悪化を改善し、経済の活性
化を導き出すことが可能である。ここで注意しなければならないことは、より完
全情報に近づく情報化社会は経済の万能薬でなく、情報化によって新たな不安定
性が生じる可能性が否定できないことである。これらのことから、日本型情報化
社会の在り方について真剣に議論される時期にきているのではないだろうか。
●●● Daisuke Fukutome
情報化社会で考えるべき視点について。まず、情報化社会が進むとこれまで不確
実であった情報が改善され、そのことによって人々の意思決定が多様化していく
ことが考えられる。期待効用の理論では、不確実な情報の下での意思決定におい
て、risk taker/risk averter がある、ということが分かったが、今後情報化が
いかに進み不確実性がいかに改善されようとも人々の意思決定においては、多様
化が進むであろう。なぜなら意思を決定する際にはその人の価値観や、人生観な
どといった要素が経済効率などよりも大きなウエイトを占めているからである。
今後の情報化社会において、知識や技術といった要素ももちろん重要であると思
うが、様々な情報下での判断能力や処理能力といった要素がもっとも重要になっ
ていくと考えられる。
●●● 7月8日の宿題
Tue, 14 Jul 1998 14:18:14 -0700
Youichi kondou <e080187@isc.senshu-u.ac.jp>
前回と今回で述べられた情報化社会で考えるべき視点について自分なりにまとめよ
e080187 近藤洋一
前回の授業では規制緩和元年がとても大きな意味を持っている事を述べた。そして米国が労働生産性と実質賃金率の伸びがとても高いという事がとても良く分かった。日本は、通信価格制度において米国に比べてなかなか下がらず大きな価格差があった。大きな変化といえば、1985年(通信規制緩和元年)に日本電信電話公社が株式会社となった。米国に対応する産業において日本には通信産業があったのである。この株式会社になるということは、市場への参入が認められるわけであるがそれにもいろいろな理由があるのである。これは授業で先生が述べたとうりである。
次に今回の授業においての情報化社会では、知識産業において考えた。マッハルプという人物の役割もとても大きいものであるとわかった。そして、ダニエル・ベルという人物により脱工業化社会(Post Industrial Society)が成立し、それはテクノクラートと呼ばれる情報を扱う事に優れたじんぶつが社会の中心となっていくという仕組みができた。そして、マーク・ポラトという人物により情報化社会が成立した。これは普通はGNPを、付加価値か最終需要のどちらかとしてみていたが、この人は両方を統合してみた。そして企業内で生み出される情報産業を計算し、評価した。その他にも目に見えない影の価格を再評価して計算した。それは機会費用にも関係するものであった。このように普通とは全く違ったものである情報化社会ができた。言い忘れていたが、1967年には米国は情報化社会に入っていたのである。その後出てきたのは、ジョンシャーという人物で、「全ての産業は生産部門と情報部門を2つあわせて形成される」と唱えた。そしてその2つは切っても切れない関係であり互いに助け合って成長していくことを意味した。
日本は米国に比べて情報化社会において10年遅れている。(教育においてはもっと遅れている)。米国においては、収穫逓増の法則によって通信産業などでどんどん生産があがっている。米国では、ウィンドウズやマックがいい例である。
現在の日本では、不完全情報のもとで意思決定が行われている。それは現在金融自由化の中にある規制緩和によって不完全情報での意思決定を余儀なくされている。一種のかけのようなものになっていくのではないかと自分は思う。このように我々日本は米国に比べるとぜんぜん劣っている事を実感した。この先情報化社会においてどのように発展していくか注目してみていこうと思う。
●●● E08-0621A 高橋牧子
6/23の宿題は難しくてまだ分かりません。
7/8の宿題
情報化社会の発展は経済を活発にする。今までの社会の中で不完全情報だった部
分が情報化によって完全情報になればより効用を高めるだろう。また、不確実な
情報のもとで意思決定をするとき期待効用が高くなる選択が求められる。情報化
はこのような不確実な情報を少しでも明確にするだろう。そして企業間の競争が
より活発になり、また、経済も活発になる。
●●● 情報経済論の宿題
Wed, 15 Jul 1998 17:19:02 -0700
megumi mathunami <e080626@isc.senshu-u.ac.jp>
情報化社会で考えるべき視点
新しいものがつぎつぎと開発され、コストが下がっていくと、自然独占の領域が
こわされていく。情報の非対称性が生じると市場において、経済効率が悪くなる
からこれはいいことだと思う。ただ、わたしは、情報の非対称性があるほうが完
全情報下にあるより不公平なだけに面白いと思う。損する人と、得する人がいな
いと逆に市場が成り立たないのではないだろうか。
完全情報はありえないとは思うが不完全な情報でないと成り立たないさんぎょう
もある。例えばパチンコ屋、宝くじ、競馬などである。どこまで情報化を進める
かはこれからの大きな問題であると思った。
⑦、1ネットワークの組織と市場に与える影響を検討せよ。また、2ネットワークの外部性とは何か説明せよ。
●●● "Yositaka Uda"
情報経済論の宿題
<ネットワークの組織と市場に与える影響を検討せよ。>
ネットワーク化の組織と市場のバランスにどう影響するかを考えてみる。従来は調整コストにおいては、組織<市場であり、生産コストにおいては組織>市場であった。そして現在のネットワーク化は複雑化した現代社会において、調整コストそのものを低減させる効果をもたらした。生産コストに関しては組織>市場という構図を崩すようになった。組織内で自ら生産するより、ネットワークを利用して市場で購入する方がコストダウンにつながるからである。よってアウトソーシングを推進する「アドホクラシー」のような組織の出現が予想される。
<ネットワークの外部性とは>
ネットワークの外部性とは多くの構成員がいることによって、市場を通すことなく他のネットワークに経済効果を発揮することができることである。外部性(プラスの効果)を発生させるのはシェアの大きさと技術力であろう。
●●● Yoshiki Kishida
1.現代社会において、複雑化する産業活動を円滑に行うためには、コンピューターによるネットワーク化が、必要不可欠となってくる。その効果としては、調整コストの低減効果であり、調整集約的な構造を求める現代では最大の武器である。また、調整コストは組織よりも市場での方が大きくなるのに対して、生産コストは組織の方が大きくなる。従って、ここでネットワーク化が起きると、調整コストを下げるので、市場と組織のバランスが崩れ、組織内で生産するよりも、市場で購入することが増えるので、市場の活性化が起こりうる。
2.ネットワークの外部性とは、実際に発生してくる機会コストと大きく関係し、情報社会における意思決定の機会損失を減らそうとするものである。
●●● megumi mathunami
1.ネットワークの組織と市場に与える影響
ネットワークの組織が市場に与える影響はとても大きく、代替効果、需要増加、
経済構造全体に波及する。コンピュータの導入される前の企業形態がいちばん調
整コストがすくなかった。コンピュータが導入され、一番調整コストが少なくは
なくなった。情報技術の発達は、生産性をあげるためのものだった。ネットワー
クは、消費者の行動を即時に分析し、そのニーズにいち早く対応することを可能
にした。ネットワークは市場を介さないので日本特有の卸売業の必要性がなくな
る。そうすると、中間マージンの減少が考えられる。いろいろな部分で無駄を省
くことができるとおもう。
2.ネットワークの外部性
外部性とはより多くの構成員からなる為、市場を介さずに他のネットワークに経
済効果を発揮することができることである。これは、機会費用との関わりがつよ
く、時に人は、情報に振りまわされ、安定性にかける。
感想
機会費用についてはわかりやすかったです。でも宿題となるとなかなか難しくて
いつも困ったりしています。今回の宿題は、入力ミスで、昨日出したのが戻って
きていたのでもう一度出します。
●●● Yasuyuki Kina
6月17日の宿題
<ネットワークの組織と市場に与える影響を検討せよ>
コンピューターを導入しネットワーク化する事により不必要な調整コストを低
減する事が出来る。ローゼンブルス国際同盟の例を挙げて考える。日本からスイ
スに行く時に直行便がなく個々の会社がバラバラでネットワークが組まれていな
い場合、例えば日本からまずフランスに行き、またそこで新たにスイス行きのチ
ケットを買って行くと言う手間のかかる方法を取らなければならないが、ネット
ワーク化が組まれていれば、初めからフランスを経由スイス行きのチケットを買
う事が出来たりと手間や余計なコストを使わずにすむ。外部の組織同士がネット
ワーク化する事によって余計なコストを削減する事が出来る。
しかし、コンピューターによって調整コストを低減すると、今までの市場より
も組織の中で生産を重視して来たバランスが崩れ、組織内で自ら生産するよりも
市場で購入する事が増えてくると考えられる。その結果、市場化の進展であり、
アウトソーシングの推進であり、大型の垂直統合型の従来型組織からより小規模
なモノへの変換であり、アドホクラシーの登場である。このように考えると生産
コスト、調整コストの両方とも市場に委ねた方がよいと思う。そうする事にで、
ネットワークにより市場が活性化し、アドホクラシーのような組織が出現してく
る。しかし、アドホクラシーするためには情報技術により組織が柔らかくされて
いて、それに参加する人がある程度のレベルを要していると言う条件が必要であ
る。
<ネットワークの外部性とは何か>
ネットワークの外部性とは普通とは違い市場を通さない形である。つまり、生
産から販売に直接結びつく事です。機会費用をふまえてネットワークの外部性を
考えるとネットワーク選択コスト=限界生産費用+機会費用という式が成り立
つ。
●●● 6/17の課題 E08-0621A 高橋牧子
1.ネットワーク化によってコンピュータは生産者間や生産者消費者間でのコミ
ュニケーションを活発にし、また不必要な調整コストを削減し、調整集約的であ
る。ネットワークの交通技術は1.代替効果 2.需要増加 3.経済構造全体へ
の波及がある。このようなネットワーク化によるコンピュータの調整コスト削減
は、組織と市場のバランスを崩してしまう。それは調整コストは市場で大きくな
り、生産コストは組織で大きくなり、お互いのバランスをとっているためであ
る。調整コストの削減に伴う生産コスト削減のためにはより柔軟な組織化が求め
られる。
2.ネットワークの外部性はそのネットワークか多くの人から構成されていると
き、さまざまな状況における行動選択の差の幅が広がってしまう。外部性は機会
費用に大きな影響を与える。
●●● 近藤洋一
(1) ネットワークの組織と市場に与える影響を検討せよ
ネットワークにおける市場と組織においては、ウィリアムソン(人名)によっ
て説明されている。市場(マーケット)と組織(ヒエラルキー)は代替関係にあ
り生産コスト>調整コストということが成り立つ。生産コストにおいても調整コ
ストにおいても、組織>市場が成り立ち、市場に依存した方がコストが安くお金
がかからなかった。調整コストを考えても馬鹿にならない額であった。例を挙げ
ると銀行業において、生産者>需要者という式が成り立っていたのが、ネットワ
ークによって生産者<需要者(生産者と需要者が同じ値からになってくる事)に
変化した。先ほど述べた組織(ヒエラルキー)になぜするかというと、コンピュ
ータが入る前のシステムでは調整コストが最も少ないからである。そしてコンピ
ュータが入ってくると、調整コストの仕組みが変わってくる。その結果、情報技
術が十分に組織を柔らかくしているということが出来る。
次は、ネットワークの外部制について述べたいと思う。普通は市場を通して生
産と販売を結ぶが、市場を通さない形(外部経済・外部不経済)のことを外部性
と言う。日本はこれを昔から問題としており現在でも環境問題としてその形を残
している。そこでは、機会費用と呼ばれる実際には存在しない費用が発生する。
その事について人間について述べると、「自分たちの払う金には機会費用が入っ
ていて人間は情報に振り回されている」と言うことが出来る。機会費用を含めて
ネットワークの外部性を考えると、ネットワーク選択コスト(市場で発生する)
=限界生産費+機会費用(市場では発生しない)と言う式が成立する。自分も、
機会費用と言うものが自分のすぐ真近で発生しているとは意識もしなかったし分
からなかった。言われてみれば、靴を買う時に店では2万5千円であったのが、
雑誌では2万円なんて事が良くあるのを覚えている。後ではとても悔しい思いを
したことも数知れずである。これからはそのようなことに注意すると共に、機会
費用が発生していてネットワークが組織と市場に与える影響などを少しでも考え
て生活していけたらいいと思う。
(2) ネットワークとは?
ネットワークとは、産業構造の中で大きな役割を果たすものである。(組織に多
大な影響を与える)。単刀直入にいうと、情報処理技術のことであるネットワー
クにおける経済は調整集約的(cordination)である。交通技術の進歩に関して
は、3つの効果が大きく挙げられる。まず代替効果(コンピューターが人間の何
倍もの力を持っている)、次に、需要増加によって新たな需要が出てくる、最後
は経済構造全体への波及である。このネットワークに関しては無知な自分にとっ
てもどれだけ重要で大切であるかが分かる。これからも多種多様に変化して人間
生活にとってかけがいのないもでありつづけることにまちがいないであろう。
●●● Daisuke Fukutome
1.ネットワークが市場と組織に与える影響を検討する。まず、従来の産業社会
では垂直統合型の組織であり”横の競争(世界全体を市場と考えた場合)”があ
まりなく、よって現在のように”横のコミュニケーション”が重要視されていな
かった。だから従来の産業社会ではネットワーク化が進まなかった。しかし、現
在のようにグローバル化が進んだ世界では”横のコミュニケーション”が非常に
大事であり不必要な調整コストを下げるのは競争を勝ち抜くためには避けては通
れない。そのための技術としてネットワークは必需品といえる。だから、情報社
会が進む流れの中でネットワークは非常に重要な役割を果たしたといえるのでは
ないだろうか
2.まず一口に外部性といっても”正の外部性”と”負の外部性”が考えられ
る。ネットワークの外部性を考えた場合、その導入によりネットワーク間の相対
的な機会費用に影響を与えることが、OS間の争いなどのモデルからも理解する
ことができる。つまり、ネットワークの外部性とは市場をかいさずにお互いに影
響を与えることをいうのではないだろうか。
●●● 青木 誠
1.ネットワークが組織と市場に与える影響として調整コストの低減がまず挙げ
られる。産業にコンピュータが用いられ始められると、コンピュータは競争する
生産者同士や生産者と消費者をネットワーク化していった。これにより、大幅に
調整コストを減らすことが可能となった。次に組織と市場の場合を考えてみる。
それまでは調整コスト:組織<市場、生産コスト:組織>市場というバランスだ
った。しかし、コンピュータの投入により、そのバランスが崩れ、結果として市
場の発展につながった。2.ネットワークの外部性とはネットワークそれ自体が
他のネットワークに影響してしまうということである。また、現代のような情報
化社会では、人間が機会費用で動いている。そのため、ネットワークを選択する
場合のコストは限界生産費+機会費用となる。
●●● masahiro yadoiwa
1、ネットワークが組織と市場に与える影響は、代替効果、需要増加、経済構造
全体への波及がある。代替効果は、単に労働者の代わりにコンピューターを導入
するというのではなく、仕事の優先順位を決めたり、適材適所に仕事を割り振
り、仕事の効率をよくする。また、そのようなことから、仕事の範囲は広がり、
それに応じて、消費者のニーズも広がる。それが需要増かにもつながる。これは
同時に、ネットワークの拡大を求められ、その調整費を上げることになるが、そ
れ以上に利益を上げることができる。経済構造全体への波及の例を挙げると、あ
る小売店がネットワークと導入すると、供給者や、卸売り店が、その小売店の中
の1つの存在になってしまうことや、ある産業全体がつながっている時、大会
社、中小会社、関係なく生産余力のある会社に需要が行くようになる。国際的に
は、ローゼンブルス国際同盟がある。
また製造業など、コンピューターを導入することにより、調整費を下げ、それ
にともない外生化が進んでいる。そのため、企業は世界中から、最も良い、最も
安いものを手に入れられ、結果世界中で、企業の垂直統合がなくなっている。
2、外部性とは、機会費用と呼ばれるものである。(間違い)これは、本来得られるべき利
益が上げられないということで、情報化により、今まで知らなかったさまざまな
情報が入ってくることによりあらわれる。この結果行動をしてからでは遅いと考
え、情報に振り回されてしまう時がある。
感想 ネットワーク技術がいかに企業に貢献しているかがわかりました。しかし
このような外部性の問題を解決するにはどうしたら良いのか考えさせられまし
た。今まで感じなかった費用なので、結局は心の持ちようですが、そう簡単には
割り切れないような気がします。
●●● 庄司
①ネットワークの組織は調整集約的である。市場に与える影響はまず、代替効果、つ
ぎに、需要増加、そして、経済構造全体への波及があげられる。市場と組織の関係は
代替的で理論的にも一致する。情報技術は調整コストを下げる作用があるので、組
織、ヒエラルキーを破壊し、市場を重視し、活性化させる。
②ネットワークの外部性とは市場を介せずに影響を与え、それは大きければ大きいほ
どよい。ネットワークによって、調整コストが減少し、効率的になり、組織を変容さ
せ、アドホクラシーのようなことが可能になってくる。
●●● 三村
ネットワーク導入前の市場と組織の関係は、生産コストでは市場<組織、調整コストでは市場>組織であり、部品の製造などは、同じ組織内の系列会社に任せるという状態であった。ネットワークの組織に与える影響は、調整コストを削減するということである。これにより、生産コスト、調整コスト両面でも市場<組織という関係になり、組織から市場中心となり、垂直統合の減少、系列会社中心から、世界市場での競争になるだろう。 また、アドホクラシーのような新しい組織形態もできるであろう。
また、外部性とは、市場を通さない経済主体間の直接的相互影響である。 ネットワー
クの普及はこの外部性が大きな要因である。 外部性とは、マーケットシェア、
技術的優位性によって決定される。技術的に優位で、多数の人が使っているネッ
トワークを 消費者は選び利用するであろう。 これにより、マーケットシェアは
さらに拡大し、このネットワークの普及度はさらにあがるであろう。
●●● 情報経済論の宿題
megumi mathunami
1.ネットワークの組織と市場に与える影響
ネットワークの組織が市場に与える影響はとても大きく、代替効果、需要増加、
経済構造全体に波及する。コンピュータの導入される前の企業形態がいちばん調
整コストがすくなかった。コンピュータが導入され、一番調整コストが少なくは
なくなった。情報技術の発達は、生産性をあげるためのものだった。ネットワー
クは、消費者の行動を即時に分析し、そのニーズにいち早く対応することを可能
にした。ネットワークは市場を介さないので日本特有の卸売業の必要性がなくな
る。そうすると、中間マージンの減少が考えられる。いろいろな部分で無駄を省
くことができるとおもう。
2.ネットワークの外部性
外部性とはより多くの構成員からなる為、市場を介さずに他のネットワークに経
済効果を発揮することができることである。これは、機会費用との関わりがつよ
く、時に人は、情報に振りまわされ、安定性にかける。
感想
機会費用についてはわかりやすかったです。でも宿題となるとなかなか難しくて
いつも困ったりしています。今回の宿題は、入力ミスで、昨日出したのが戻って
きていたのでもう一度出します。
●●● 矢作 敏和
①ネットワークの組織に与える影響は調整コストの削減、組織内での横のコミ
ュニケーションの充実、作業の簡略化・時間節約などさまざまある。
次に市場に対する影響である。コンピューターが調整コストを低減するとすれ
ば市場で一番良いものを買ったほうが自社で生産するより良いわけである。これ
は市場競争を推進させる働きがあるわけだから市場は活性化する。また市場に構
えている企業でもネットワークを導入する事により作業のスピード化や、先ほど
も述べたように横のコミュニケーションの充実がはかれるのである。
②ネットワークそれ自体が他のネットワークに対し市場を介さない経済効果を
持っている事。
●●● 朝賀 浩之
①:ネットワークの組織と市場に与える影響は、コンピューターの特性である調
整コストの低減効果が関係している。コンピューターは、これまで不必要であっ
た調整コストを最小限に抑えることができ、調整集約的な構造への転換を可能に
する。コンピューターの導入によるネットワーク化は、調整コスト=市場>組
織、生産コスト=市場<組織であった従来のバランスを崩すことを意味する。結
果的に外生化(組織内での生産⇒市場での購入)が起こり、市場は多様化し、活
性化するといえる。それによって、大型の垂直統合型の従来型組織は機能しなく
なり、小規模で柔軟性を持った組織が求められる。つまり、ネットワークは市場
化の進展、それによるアドホクラシ-などのより柔軟な組織の誕生を導くといえ
る。
②:外部性とは市場を介さない経済効果であり、ネットワーク自体も強い外部効
果を発揮する。ネットワークの外部効果は機会費用に大きな影響を与え、ネット
ワーク選択コスト=限界生産費+機会費用であることもわかる。また、ネットワ
ーク化によって社会が情報への依存度を強めていくと、人々は機会費用によって
行動を決定することになる。
●●● 情報経済論 6月17日の宿題
Wed, 15 Jul 1998 13:48:07 -0700
Daisuke Unpou <e080345@isc.senshu-u.ac.jp>
ネットワークが組織と市場に与える影響には、調整コストの低減効果が挙げられる。コンピューターによるコミュニケーションコストを含む調整コストの低減は、複雑な現代社会を調整集約的な構造へと促進させた。そして、調整コストの低減は市場を活性化することができる。組織内で自ら生産する生産コストと、市場で購入する時の調整コストがあるが、調整コストの低減によって市場で購入することの方に積極的になるからである。これによって、垂直統合型の従来の組織から小規模への変換やアドホクラシーの登場が起こった。ネットワークの外部性とは、より多くの構成員からなるネットワークそれ自体が市場を介さずに他のネットワークに影響を与えることである。この外部効果は、ネットワーク間の相対的な機会費用に大きな影響を与える。
●●● 6/17の宿題
Tue, 14 Jul 1998 13:06:19 -0700
akinori wakabayashi <e080123@isc.senshu-u.ac.jp>
①《ネットワークの組織と市場に与える影響》
ネットワークの組織と市場に与える影響は①代替効果②需要増加③経済構造全
体への波及である。ネットワークの発達は、WALMARTの例であるように、
購買部の人員を削減できた。これはコンピューターの導入により、物が売れるた
びに供給者が商品を補充するシステムになったからだ。このようにネットワーク
化は、調整コストの大幅な削減を可能とした。市場(マーケット)と組織(ヒエ
ラルキー)は代替関係で、生産コスト:組織>市場
調整コスト:組織<市場というバランスを保っていた。しかし、ネットワーク化
による調整コストの低減でそのバランスは崩れ、組織(ヒエラルキー)よりも市
場(マーケット)を重視するようになり、市場は活性化した。これは、企業の垂
直統合がなくなり、アドホクラシーの出現を意味している。しかし、アドホクラ
シーの出現に際しては、柔軟な組織化が求められている。
②《ネットワークの外部制》
ネットワークの外部生とは、生産から販売に直接結びつくことで、市場を介さ
ずに経済効果を生み出すことである。そこでは、実際には存在しない機会費用が
発生し、ネットワークの外部性を機会費用を含めて考えると、
ネットワーク選択コスト=限界生産費+機会費用という式が成立する。
●●● sakai hayato
Wed, 08 Jul 1998 17:42:03 -0700
<ネットワークが組織と市場に与える影響を考える>
組織と市場のバランスはネットワーク化することでどうなるのか?調整コストに
ついては、組織、市場でした。ネットワーク化することで複雑な経路をとうらず
に販売できるので、コストを確実に、削減することが出来る。このような動きが
あると[アドホクラシー]喉の組織などが現れる。
ネットワークの外部性は、生産から販売に直接結びつくことをいいます。
これは、ネットワーク選択コスト+限界効用+機会費用式が成り立つ。
●●● 6/17情報経済論の課題 中村晃司
Wed, 08 Jul 1998 14:26:25 -0700
① ネットワークの組織と市場に与える影響
現代のネットワーク化により、組織と市場に多くの効果をもたらした。その効果
は、調整コストの低減効果であり、様々な産業間の取り引きに伴うコストを大幅
に削減する。不必要な調整コストを削減する。また調整コストと生産コストがネ
ットワーク化により、組織と市場のバランスが崩れ、市場の頻度が増え、活性化
につながった。ネットワーク化は市場の活性化を進めるのに役立つ。
② ネットワークの外部性について
外部性とは、私的な経済活動が他の経済主体に影響を及ぼす事である。ネット
ワークの外部性は、目に見えない経済効果である。これは機会費用に似るものが
ある。これはコンピューターのOSのように、あるOSがシェアを増やすと、他のOS
に負の影響が出る事である。ネットワークの外部性は市場を介さずに、他のネッ
トワークに経済効果を与えるものである。
感想:情報伝達(ネットワーク化)により、世界の経済が発展していった。ネッ
トワーク化が、現代に大きく役立っている事を今回の講義で再度認識した。
情報を使いこなすものが、今後も更に発展していくだろうと思った。
●●● junji kurihara <e080103@isc.senshu-u.ac.jp>
ネットワークの組織と市場に与える影響は3つあります。まず1つめは代替効果
で、これは仕事の流れをスムーズにするために、どの企業にこの仕事を任せたら
一番効果が上がるだろうかということや、どのような順序で仕事を構成していく
べきかなどを決定します。このような代替効果の結果、より仕事の効率が上が
り、消費者による需要も増加します。ネットワークの組織と市場に与える影響の
2つめは、この需要増加となります。3つめは、経済構造全体の波及で、これ
は、ネットワークの導入により、大、中、小の企業がつながっている場合にどの
企業でも関係なく適所に需要が行き渡り、その企業全体で需要増加の効果を得る
ことが出来ます。しかしこのようなネットワークの導入は、同時に調整費を上げ
ることとなります。このあがった調整費よりも大きい成果を上げるために、ネッ
トワークが持つ力を最大限に引き出させることが重要な問題ではないでしょう
か。
ネットワークの外部性とは多くの構成員によって形成されているため、一般と違
い、市場を通すことなく経済効果を発揮する事が出来るということです。
E080103J 栗原淳二
●●● 6月17日の課題
Wed, 08 Jul 1998 13:55:28 -0700
shunichiro mitsutake <e080533@isc.senshu-u.ac.jp>
1、ネットワークの組織と市場に与える影響は、コンピューターの持つ調整
コストの低減 効果が挙げられる。コンピューターのこのコストの低減効果
は、現代の産業経済にとって 非常に大きいものである。しかし、コンピュー
ターによる調整コストの低減により、今ま で、調整コストの割合は組織より
市場が大きく、生産コストの割合は市場より組織が大きかったバランスを崩
してしまうのである。バランスが崩れると、組織の中で自ら生産するよ
り、市場においての購入が増えてくると考えられる。このように、結果的には、
外生化が起こり、市場化が進展し、大型の垂直統合型の従来型組織は機能
しないようになり、小規模なものへ変換され、アドホクラシーのような柔
軟な組織を登場させるのである。
2、ネットワークの外部性とは、ネットワークそれ自体が市場を介さず、他
のネットワークに影響してしまうことである。またネットワークの外部性
は、機会費用にも大きな影響を与える。ネットワーク選択コスト=限界生産
費+機会費用であることからも分かる。
●●● 情報経済論6月17日の宿題
Wed, 08 Jul 1998 13:44:53 -0700
Daisuke Unpou <e080345@isc.senshu-u.ac.jp>
ネットワークが組織と市場に与える影響には、調整コストの低減効果が挙げられ
る。コンピューターによるコミュニケーションコストを含む調整コストの低減
は、複雑な現代社会を調整集約的な構造へと促進させた。そして、調整コストの
低減は市場を活性化することができる。組織内で自ら生産する生産コストと、市
場で購入する時の調整コストがあるが、調整コストの低減によって市場で購入す
ることの方に積極的になるからである。これによって、垂直統合型の従来の組織
から小規模への変換やアドホクラシーの登場が起こった。
ネットワークの外部性とは、より多くの構成員からなるネットワークそれ自体が
市場を介さずに他のネットワークに影響を与えることである。この外部効果は、
ネットワーク間の相対的な機会費用に大きな影響を与える。
⑥サービス産業における情報技術の役割と影響を検討した後で、情報技術のこれまでの技術との違いを検討せよ。
●●● junji kurihara
サービス産業において、情報技術の導入される前は、意思決定において中央集権
化と分散化の2つに1つを選ぶといった状態でした。そしてこの形は、企業の末
端から情報を本店に送る際、中間企業を通ってから送られるので大変時間がかか
っていました。しかし情報技術の導入によってオンライン化されたあとは、企業
の末端から中間を飛ばして本店へ情報を送れるだけでなく、末端だけでも情報処
理を行えるようになりました。また、意思決定の集権化と分散化の同時進行も可
能となりました。このように、技術導入前と後では、システムの統合による違い
が大きいと思います。それによって、補完関係の機能が強化されたり、代替関係
の機能が更に整理されるといった逆分業がおこりました。このようなシステムの
統合は、確率性、連続性、抽象性といった性質を作り出すことに成りました。し
かし、エラーをした時のリスクは、大きなものとなります。
このように情報技術は変化していき、より高度なものとなってきましたが、パー
フェクトのものではないと思います。多少のエラーでも揺るがないようなシステ
ムを開発することは難しいけれども、それがサービス産業をより大きくするもの
であると思います。
E080103J 栗原淳二
●●● 6/10情報経済論の課題 E08-0203C 中村晃司
サービス産業において、オンラインによるシステムの統合は、末端から案件に応
じて様々な部門に多くの情報を流す事ができ、案件の内容により末端が処理でき
るようになった。このことは意思決定システムの分散化を起こすようになった。
さらに、末端から処理できない事を支店へ通さず、直接本店に依頼する意思決定
の中央集権化にもなり、組織の水平化になりうることになった。
銀行業においては、第三次オンラインにおける金融の自由化、国際化により
様々な銀行の統合化が起き、そして一つの取り引きにより即座に多くの処理が完
了し、エラー原因についても分析できるようになった。
コンピューターの導入、オンライン化によりシステムが統合され、他部門の取
り引きも容易になるし、代替効果を得る事ができる。さらにコンピューターの処
理能力を早くし、エラーの減少をする事により、信用性の利益を生むだろう。だ
がコンピューターの停止におけるすべての機能に影響を及ぼすというマイナスの
めんを考えないといけない。
感想 コンピューターのオンライン化による効果は多大なものであった。情報
技術が産業に入る事により様々な効果が生まれ、今後更に情報技術が進歩してい
くので、さらに多大な効果が得られると思う。だがそうすると情報技術の進歩と
共に人間も能力を高め進歩していくことが必要になるだろう。
●●● akinori wakabayashi
サービス産業における技術の導入は、生命保険の例では、オンライン化により
末端の営業マンでも苦情などの案件を処理できるようになった。また、直接情報
を本社に送れることから、支店では処理できない案件を本社に頼むことも出来る
ようになった。このように、技術の導入(オンライン化)は、意思決定の分散化
と、集権化を同時に可能とした。その影響として、専門家以外でも容易に業務が
こなせることからゼネラリストの必要性が強まった。銀行業の例では、第3次オ
ンラインにより、国内の業務と海外の業務の連携が可能となり、システムの統合
が行われた。この統合こそが、情報技術とこれまでの技術の違いだ。統合により
情報技術では、連続性、確率性、抽象性という特徴を備え、機能間における補完
関係は強化され、代替関係と重複の整理が図られたことにより、生産性は向上し
た。しかし、連続性という特徴から、システムをチェックする能力が必要とな
り、ミスが許されなく、コンピューターの故障などによる仕事への影響や、確率
性という特徴から、仕事の単純化による人間の能力の低下というマイナス面もあ
るのだ。
●●● Daisuke Unpou
情報技術が与える影響をサービス産業において考えてみる。まず、オンライン化
によって意思決定の中央集権化と分散化が同時に見られるようになった。本店に
つなげる場合や、案件によっては末端や支店で解決する事もできるようになっ
た。そして、情報技術のこれまでの技術との一番の違いは、システムの統合化で
ある。統合化によって、機能の補完強化や代替、重複の整理がおこなわれた。そ
して、業務は連続性、確率性、抽象性を持つようになった。これにより、労働者
はより広いプロセスを理解する事が必要になった。
●●● shunichiro mitsutake
サービス産業における情報技術の導入は、まず生命保険業界の例でもわ
かるように、 意思決定の中央集権化と分散化が同時に行われるようになった。
また本店と支店を瞬時に結 び容易にデーターのやり取りが行なわれるようにな
った。それから銀行業の例では、今まで 部門毎にやっていたシステムが統合さ
れ、国内の業務と海外の業務との連携が可能になった 。これによる影響は、専
門家があまり必要なくなったことと一つの処理を瞬時に終わらせる ことであ
る。
情報技術とこれまでの技術との違いは、連続性、確率性、抽象性という特徴
を備えたことである。
●●● 朝賀 浩之
情報技術はサービス産業において、意思決定システムに大きな影響を与えたと
いえる。これまで組織の意思決定には分散化と集権化のどちらかを選択しなけれ
ばならなかった。しかし、情報技術の導入によるオンライン化は、意思決定の分
散化と集権化を同時に行うことを可能にした。組織は集権化と分散化のそれぞれ
のメリットを得ることができるようになった。サービス産業では広い範囲での市
場(本社での処理)と細分化された市場(現場での処理)それぞれ即時の意思決
定が必要であり、情報技術はそれを可能にすることができる。
情報技術とこれまでの技術との決定的な違いは、システムの統合を可能にした
ことである。分断されていた分業体系は情報技術の導入により、その効果として
補完の強化、代替、重複の整理が図られ分業の再統合(逆分業)を導いた。この
統合により、情報技術はこれまでの技術には存在しなかった連続性、確率性、抽
象性という特徴を備えたといえる。
また、情報技術の登場によって、「リエンジニアリング」による生産性の向上
という可能性が生みだされたのではないのだろうか。
●●● 近藤洋一
まずサービス産業について例を挙げて情報技術の役割と影響について例を挙げ
て考えたいと思う。まず大きな発展としての1つめは、第一生命のHome
Office
についてである。1969年にオンラインシステムが出来てから様々な変化を遂げて
きた。ここであげる大きな変化といえば、2次、3次における意思決定システム
の変化であろう。これは、Home Officeから74の支店に分離しそれがまた、135に
も及ぶ販売拠点に分離する流れの中で、コンピュータ化によってその支店や販売
拠点を飛ばすという水平化が可能になったことである。それらのような事によ
り、中央集権化と分散化という事をプラスして考えられるようになった。後の
1983年には完全なコンピューター化が完成した。
2つめの大きな発展は、銀行業を例に挙げて考える。銀行業は、1950年代の中頃
に、オートメーシヨン化をとげ1965年にオンライン化をとげた。1970年から1972
年の間に第一次オイルショックと第二次オイルショックがおこり日本自体の経済
が下降するがすぐに立ち直った。これについては前の授業で述べたように徹底的
な省エネ化によるものであった。そして銀行業もコンピュータを導入せざるを得
なくなった。日銀中心の全銀システムにより、ネットワークが出来上がり始めて
のオンライン化が成功した。そして住友銀行が良い例である第三次オンライン化
が起こった。それにより、金融市場の自由化と金融市場の国際化が銀行に求めら
れるようになった。第三次オンライン化による一番の結果は外国の国々とのシス
テムのINTEGRATIONによってお金が合わなくなるような事が少なくなった。今ま
での情報技術からはかなり大きい進歩と言えるであろう。そしてコンピューター
化により様々な変化が起きた。まずオンライン化によってgeneralistになれなく
てもspecialistになれるようになった。そして仕事の上でも仕事が安易になっ
た。技術の導入によって分業(意志、階屋、人間の能力)の3つが成り立つよう
になった。
まとめると、INTEGURATIONの効果は補完関係の機能が更に強化され代替関係の
機能が整理され同じ関係の機能も整理された事である。その技術は、連続性を持
ち確率的であり工場でもオフィスワークでも同じ事が言える事に成る。これらの
事を見ると、サービス産業における情報技術によって(コンピュータの発展によ
って)色々な事が変わってきていて進歩してきている事を実感しました。しかも
サービス産業によるものがここまで大きな影響を与えている事は知りませんでし
た。これからはそれらのような事を頭に入れながら、銀行などを見ていこうと思
います。
●●● 青木 誠
情報技術の導入によって、サービス産業に様々な変化がもたらされた。例えば生
命保険業の場合、意思決定の中央集権化と分散化が同時に行われた。処理案件の
性質によって、その意思決定を本店が行ったり、支店または営業マンが行ったり
することが可能になった。また、銀行業の場合では、第3次オンラインによりシ
ステムの統合が行われ、国内業務と海外業務の連携が可能になった。これによ
り、タイムロスが減り、業務が簡略化され専門家の必要性が少なくなった。サー
ビス産業における情報技術の導入は、結果としておもに「統合」を推し進めた。
それにより人間は選択の幅が広がり、いろいろな可能性が増えた。また、情報技
術はそれまでの技術とは違った性質(連続性、確率性など)を持つため、仕事に
求められる性質も変化した。
●●● 鈴木 6月10日の課題(情報経済論)
今までの情報技術は、組織の水平化が行われた。コンピュータの導入により、市場産業は組織の統合が為され様々の分野においても分散化が進んだ。サービス産業を見てみると、
オンライン化により、意思決定機能にも影響を及ぼした。また、組織の連続化がなされた。
これは、統合からの連続化と言えるのではないだろうか。連続化によって一瞬での案件の処理が可能になったと言う利点も大きいが、逆にそれにより行程システムにおいてミスが許されないと言う不安も増大した。だからこそ、逆分業を進めることによってまだまだ可能性は見えてくるだろう。
授業の感想
情報技術もいろんな形で進化してきたが、やはりその組織においての適応性が重要だと思った。オンライン化によって進化したとはいえパーフェクトではない。だからこそ、進化してゆく未来が楽しみである。
●●● 情報経済論 6/10宿題 三村和則
今までの産業では、情報化により組織の水平化、意思決定の分散化がおきた。
サービス産業では、オンラインにより、今まで本店によって処理されていた案件がデーターベースなどの利用により支店でも処理可能となり意思決定の分散化が進んだが、支店では処理できない案件を直接本店に送り処理を頼むといった意思決定の集権化も同時に進んだ。
またこれらのオンラインは、サービス業においては一つの組織内だけでなく、他の組織とも結ばれ産業内にも浸透していった。これにより、産業内での情報の共有、システム間の相互補完を強化し代替機能整理による生産性の向上につながった。しかし、このシステムは業務を連続的、確率的、抽象的にし、一つのエラーによってすべての仕事に支障を来たすという危険性も増大した。
●●● masahiro yadoiwa
これまでの情報技術は、組織の水平化を導いた。その結果、中間管理職が行っ
ていた情報管理は、コンピューターに変り、いくつかのプロセスは統合された。
また新技術は、若い高学歴の労働者に対する需要を高め、経験と腕にもとづく階
層組織を崩壊させ、柔らかい分業を促進させた。
サービス産業における情報技術は、その業界自体の水平化をもたらしたように
おもえる。
オンライン化により、案件の情報を直接本社に送れたり、末端でも処理できる
ようになったり、意思決定の中央集権化と、分散化が同時に起こった。また、そ
の業界自体や、海外の支店とオンライン化をすることにより、業務が連続化さ
れ、一瞬で案件などの処理が可能になった。
サービス産業では、その他の産業に比べて、オンライン化することによって、
分散化が進んだようにおもえます。
感想
コンピューターのネットワーク化が、いかに仕事を早くするかがわかりまし
た。ただ目に見えないところで、連続して仕事が進むので、ミスや、故障したと
きが大変だと学び、完璧なものはやはり、簡単ではないと思いました。
●●● 宇多 6月10日
情報技術の役割と影響について考えると業務の連続化といえる。その連続性によ
って、一つの処理がスムーズに行えるのである。これをふまえて、これまでの技
術との違いを検討すると連続性を本にして、意志・階層・人間の能力と言った分
野で統合(補完・代替)がなされた。その結果、このような状況ゆえに末端部門
で処理できる案件も出てきた。つまり、集権化と分散化が同時に存在するように
なったのが一番の違いである。
●●● 6/10の課題 E080621 高橋牧子
サービス産業においての情報技術の導入は、本店と多くの支店を一瞬にして結
ぶことによってさまざまなデータのやり取りが容易にできるようになる。また、
意思決定の中央集権化と分散化が同時に行えるようになった。それは技術や生産
性がミクロのレベルにまで進んでいる。
これまでの情報技術によって組織は水平化されたが、サービス産業においての
情報技術はそれらを統合するものである。そしてその統合化がサービス産業内で
の業務をスムーズに進めるだろう。
●●● Yasuyuki Kina <e080468@isc.senshu-u.ac.jp>
6月10日の宿題
サービス産業においてオンライン化は決定システムに影響を与えた。業務の連
続化によって瞬時に1つの処理が完結する事、専門家でなくても容易に業務をこ
なせるようになった事に加え、CAREER
PATHという専門職、一般職、
地域限定職などのキャリア選択制度の導入などさまざまな影響を受けた。第三次
オンラインによってシステムが統合され、経済性は各ジョブの中にある様々な機
能間における補完の強化、代替、重複の整理が図られる。統合によって情報技術
はこれまでの技術とは異なる連続性(CONTINVOVS
EVENT)、確
率性(STOCHASTIC
EVENT)、抽象性(ABSTRAG EVE
NT)という特徴を備えるようになった。しかし、現在の情報社会では一度コン
ピューターが麻痺してしまったら、何も出来なくなり仕事自体も麻痺してしまう
と言うマイナスの要素も含んでいる。
感想
確かに、以前の日本人の新しい技術の導入に対する意欲は終身雇用と言う存在
が大きかったと思います。日本人の性格と言うか風土上、これが必要ですとか大
事ですと言われると不満を漏らしながらも勉強して習得しようとします。しか
し、終身雇用制度が崩壊してしまった現在において日本人労働者の技術導入に対
しての考えも変わってきているのではないかと思います。
●●● 糀谷一泰
膨大化した仕事を瞬時にこなすという上で、情報技術の導入は、いまでは絶対的
存在となっている。また、部門間の統廃合が進み人員削減やだれでも簡単に仕事
をこなせるようになったという点で経費削減にもつながる。人件費がかさむサー
ビス産業において、仕事の合理化はまさに死活問題といって良い。当然、人を減
らしても今までかそれ以上の生産力を上げたいところである。サービス産業にお
ける情報技術の導入の影響は、今までのケースとは多少異なり、意思決定システ
ムにみられるような確実性・分析力や解析力などに特に強い能力を求められる点
である。現代において、不測の事態がおきた場合でも的確な処理を下せなければ
顧客は他に逃げてしまう。情報のより迅速な解析こそがサービス産業に要求され
るものと考える。
●●● Daisuke Fukutome
サービス産業における情報技術の役割は、銀行の例でも明らかだが「オンライン
化によるシステムの統合」という一言につきる。これによって国内のみならず海
外市場ともつながった。金融の自由化、国際化の中で、情報技術の役割はかかせ
ないものになっている。また、これによる影響として考えられることは、キャリ
ア選択制度のほかに、優秀なゼネラリストの必要性が一層強まったことなどが考
えられるのではないかと思った。また、これまでの技術との違いは、連続性、確
立制、抽象性などの特徴が挙げられるが、自分が思ったのは、物事を客観的に見
て、問題を発見し解決する能力が最も必要とされるようになったことがこれまで
とはおおきく異なるのではないかと思う
●●● 矢作 敏和
生命保険会社の場合で言えばコンピュータの役割は企業を
オンラインで結ぶことであると思う。つまり企業の上から下
までをネットワークで結ぶことで営業の促進化を図ることで
あろう。
それまではオンラインではなかったために一番下の子会社
はその上の直営の会社にしかネットがつながらなかった。し
かしオンライン化により子会社でもその場で本社に接続でき
るわけだから仕事の効率がよく、また連続的になり専門職が
あまり必要でなくなった。
これまでは情報技術は人一人の仕事を簡単にするための道
具としてしか見られていなかったが、今では企業単位の仕事
をも楽にしている。
●●● 大前 コンピューターの導入によって、連続性と統合(INTEGRATION)の効果を考えると、まず、第1に補完関係の機能が強化され、第2に代替え関係の機能が整理され、最後に重複関係に機能が整理されたことがいえる。この結果、効率上がったといえる。
さらには、知識の重要性がました。
このことからも、技術の導入は企業にとって大切なことである。
また、過去の日本の技術導入への積極的な態度は終身雇用にあったともいえる。
今後、終身雇用が崩壊するだろうといわれるなか、日本は日本は技術導入に積極的な態度をとることができるのであろうか。
感想:
今回の授業で、コンピューターの導入により組織と技術の同化にどのような
影響を与えたのかということが良く分かりました。
この授業を聞くたびに思うことが、企業による、効率を考えることは本当に
面白いなということです。そのためには、コンピューターの導入は不可欠で
あるし、企業にシステム全体を考えることも不可欠である。これからの授業
が楽しみです。
●●● 水沢 1998.6.10 宿題
サービス業において技術の導入(on line化)は、仕事、意思決定の分散と中央
集権を生んでいる。
オンラインネットワーク化は、情報の共有により中央で行われていた仕事を各
端末で行われる分散された仕事にしていることがある。 (例)スカンジナビア
航空では、苦情処理業務は本社で集中処理されていたが、苦情は各端末の窓口で
対応できることが望ましく、同社では苦情処理業務を分散させ、端末で対処する
ようにした。これはオンラインネットワークによる情報の共有がトラブルがどの
ようにおこったかを端末で調べることを可能にし、苦情処理業務のマニュアルを
データベース化することによって、スペシャリスト以外でも仕事を容易にこなせ
るようになったことによる。
一方で分散されていた仕事、意思決定権を中央集権化させることもある。銀行
ではオンラインネットワーク化により、各支店での取引は瞬時に中央に計上さ
れ、各支店での経営管理の多くは中央に吸収され、集権化されている。これによ
って各支店では、より顧客に深く対応できるようになっている。
このようにサービス業における技術の導入(on line化)は、仕事、意思決定を
分散させたり、中央集権化させ、顧客に密に対応できることを可能にしている。
●●● "Yoshiki Kishida"
サービス産業における情報技術の導入は、意思決定の中央集権化と分散化を同時に行えることを可能にした。例えば、案件の処理を支店では対応しきれなかった場合に、その意思決定を本店に任すことにより、スムーズな仕事が可能になった。また、第3次オンラインにより、国内と国外の業務の連携がおこり、金融市場の自由化や、国際化が図られた。これらの、情報技術の効果としては、補完の強化、代替と重複の整理で、このような統合により、連続性、確率性、抽象性という特徴を備え、仕事の性質も変化し、逆分業という矛盾も、矛盾ではなくなり、生産性を上げる要因となった。
●●● megumi mathunami
サービス産業にをける情報技術の役割はとても重要な位置を占めており今では情報
なしでは成り立たない産業であるともいえる。わたしがバイトをしているコンビ
ニでも、何十代の人が何を買っているのかという統計はボタン一つで出てくるよ
うになっている。その統計や次の日の天気予報を元に商品を発注している。この
ようなものは、本当にここ十年足らずで発達してきており、この情報技術の発達
は、これまでと違い、その地域や状況に応じた事ができるようになった。
●●● 庄司
情報技術のこれまでの技術との違いは統合である。それによって、瞬時にわかるよう
になり、意思決定を中央集権化と分散化で同時にできるようになった。そして、補完
関係の機能が更に強化され、代替関係の機能が更に整理された。すなわち、連続性、
確立性、抽象性がもたらされた。しかし、それとともに危険度も増した。人間の能力
に関しても、情報技術の導入によって仕事を単純化し人間の能力をDe-Skillingされ
たが、逆に、問題を指摘する能力、解決する能力、Handlingする能力、幅広い知識の
重要性(前行程と後行程のプロセスがわかる)、が必要になってきた。
●●● 08-0597k 横田真紀
サービス業における情報技術の役割と影響は、オンライン化による意思決定と分
散化と中央集権を同時に実現とシステムの統合ということである。第一生命の場
合では、本店と支店、末端を直接結び、データのやり取りが簡単になり今までか
かっていたコストと時間が大幅に縮少できた。そして末端の意見も直接上に届く
というシステムになった。銀行業では1970年の第3次オンラインで金融市場の自
由化と国際化を進めた。サービス業における情報技術の導入は産業ないでの情報
の共有と業務の連続性を高めた。
これまでの技術と情報経済の違いはサービス業においては、オンライン化によ
って、意志を自由に伝えられ顧客によりはやく対応できるということである。こ
れからますます情報化が進み、意志の疎通が早まり、サービスを受ける側が主体
になる。消費者主体で多種多様なサービスが必要となってくるであろう。
●●● サービス産業における情報技術
Wed, 15 Jul 1998 17:49:37 -0700
daisuke sekiguchi <e080491@isc.senshu-u.ac.jp>
サービス産業における情報技術の役割は、意思決定に関する事だと思う。それま
では意思決定は中央集権だった。そのため一つの意思決定に多くの無駄な時間と
労力を費やした。しかし、第一生命ではオンライン化することにより、意思決定
を中央集権化と分散型とを同時に行う事に成功した。その結果無駄な時間と労力
を減らす事ができ、意思決定をスムーズに行う事ができるようになった。その結
果組織の水平化が進んだ。
●●● sakai hayato
Wed, 08 Jul 1998 15:39:16 -0700
サービス産業における情報技術の導入は、生命保険において、オンライン化する
ことで、末端のサラリーマン、営業マンでも苦情などの案件を処理することがで
きるようになった。情報を安易に送れるので、難しい案件などは、本社に任せた
り出来るようになった。
銀行においては、いままでは難しかった。国内、海外の業務の提携が出来るよう
になった。つまりシステムの統合である。これにより情報技術では、連続性、確
立制、抽象性、特色を持ち機関における補欠関係はより強い者となった。これに
より生産力もあがった。
サービス産業では、オンライン化は、意志決定の分散化、集権化を同時に可能と
した。その影響で容易に業務がこなせることから、ゼネラリストが非常に必要と
なった。
銀行業においては、ミスすることが許されなく コンピュータが故障したりする
と業務がまったくおこなえないなど仕事が単純化してしまい人間の能力の低下に
結びついている。
●●● 6月10日情報経済論の課題 E08-0265E 内山ゆう子
Wed, 08 Jul 1998 14:20:18 -0700
サービス産業における情報技術の導入は、オンライン化で本店と多くの支店を一
瞬にして結ぶことにより意思決定の中央集権化と分散化を同時に行うことを可能
にした。
また国内だけでなく、海外支店等との連携が可能となったことにより、業務が連
続化され、瞬時に1つの処理が完結することを可能にした。
これらの影響で、経験や知識を多く必要とする専門家の必要性は少なくなった。
また、これまでの技術との違いは、統合による連続性、確率性、抽象性という特
徴を備えることである。しかし、利点も多いが1つのミス、エラー、ウイルスが
許されないという不安もある。
感想
オンライン化ということで,POSレジ?を思い浮かべました。情報技術を導入
し活用することで、私達のちょっとした行動も情報となるのだなとふと思いまし
た。
●●● 大慈彌
⑥サービス産業における情報技術の役割と影響を検討した後で、情報技術のこれまでの技術との違いを検討せよ。
サービス産業では、オンライン化することで末端でも業務を処理できるという意思決定の分散化と、末端では処理不可能な業務を本部に依頼するという意思決定の中央集権化が同時におこった。つまり、情報化によって組織の水平化と意思決定の分散化がおこった。
また、オンラインによる効果は、サービス産業の生産性を向上させるとともに、業務上のミスは仕事全体にストップをかけてしまうというリスクを背負うことになった。
●●● junji kurihara
ソフトウェア生産における専門性に基ずく分業とは、アメリカのように1つ1つの
部門が完全に分断され、個人はその分断された部門の中の1つの仕事だけを専門
的に行っていくことです。実際には、立法、行政、司法といったように、
SD,PROGRAMIMING,TESTERといったそれぞれの部門が独立し、他の2つの部門には
まったく関与しないということになります。すると1つ1つの部門の質は高くな
り、結果的に、より良いものを生み出せるようになる可能性も高くなります。そ
の反面、エラーの発生率は高くなります。なぜなら、自分が気がつかなかったミ
スを、他人に指摘されるといったわれわれの日常のことでもあるように、その部
門で起こったエラーはその部門内の人では気ずきにくいということがあるからで
す。その点日本が行ってきた柔らかい分業では、アメリカのように完全に部門部
門が決まっていて、1つの仕事だけをしていくわけではなく、同時に他の部門に
も目を通せるためエラーの発見生は高く、そういった意味で、エラーは少ないも
のとなります。しかし1つの仕事に対する理解度が曖昧なものになってしまうと
いった点で、アメリカよりは生産性は低くなります。
したがってこの2つの分業は、どちらが最適かと言うのは、一概には言えませ
ん。これらはそれぞれの国で効果を上げた結果、どちらの国でも現在に至る成長
を遂げているのです。結論として、一番大切なのは、その国、その時に応じた風
土に合った分業体制を見つけることだと思います。
●●● 石田
ソフトウェア生産 における専門性に基づく分業と、柔らかい分業についてであるが、日本においてアメリカ式の専門的な分業体系を実践するにはいくつか問題点が挙げられる。
1 アメリカと比べてソフトを制作する人の絶対数が足りないのではないか?
2 柔らかい分業のためソフトのエラーチェックが正確に行われない(時間がかかる)
3 今現在では、アメリカの絶対的な力を持つ企業のソフトに打ち負けてしまう。
と、こんなふうに問題点は挙げられるが、日本の企業にとって良い面も見られる。
例えば、去年から話題になっているメールソフト、PostPetは日本の企業のものだし、
今でこそワープロソフトはmicrosoftのWARDであるが、1.2年前に流行った一太郎が日本の企業のものである。これらの日本の企業のソフトの成功のカギは、やはり日本人の感覚にあったものを作り出した ということではなかろうか?これは、いくらアメリカの企業が頑張っても勝つのは難しいのである。
しかし、このままで日本の企業が良いかと言われると、答えは・/FONT>NO狽ナある。それは現在
日本のソフトウェア会社がエラー率の少ないものを作っているというが、それはアメリカの企業と比べた場合、明らかにそのソフトにかける時間が長いのである。時間をかければエラーの発生が妨げられるかもしれない、しかしソフトウェア関連はこれからの時代の担い手となっていく分野であり、さらに急速なスピードで進歩をとげていく分野であるためこのような日本の方式では追いついていけないし、また制作を急ぐあまりエラーが発生したりするであろう。
ということは、これからの日本のソフトウェア産業はどういった道を選択すれば良いのか?僕が考えるに、日本もアメリカと同じような質、量を持つソフトを制作したいと考えるなら、やはり日本もアメリカ式にすべきなのではないだろうか?しかし、今現在ではまだそのような体制も整ってないし、絶対的な制者人数が足りないという問題が生じる。だから、当面は日本の得意とする分野に焦点をしぼり、性能が良くアメリカソフトとは異なる日本人に適したソフトを作っていくしかないだろう。そこから徐々にアメリカ式に移行していきつつその都度両者の良い面と悪い面を取り入れていき、ソフト制作に良い環境を作りだすことが大切である。
●●● Daisuke Unpou
アメリカはSDとProgrammingとTesterに完全に分かれていて
専門性にもとづく分業が行われている。一人一人の仕事がはっきりしているため
生産性は高い。また、外部労働市場によってアメリカのソフトウェア市場は発展
している。しかし、専門的分業のため労働者の向上心が低いことや創造性が発揮
しにくいという問題もある。日本は未分化な分業制で、部門間の境界はあいまい
である。このことが生産性が低い一つの要因になっている。では、日本も専門的
分業を取り入れてはどうかと考えられるが、労働者の向上心の低下や日本の社会
風土にあわないなど問題がおこってくる。また、社内生産が多い内部労働市場の
ため国内の市場が発展しない。日本の良いところは、エラーの発生率など品質管
理において非常に優れていることである。これは、内部労働市場や柔軟な分業制
にもよるものである。このように日本の分業制は長所と短所をあわせもってい
る。それぞれの国によって風土や環境が違うのだから、日本にあったやり方を探
せばいいと思う。
●●● 小野智之
アメリカのソフトウエア産業は、専門性に基づく分業により、立法・行政・司法
が分離していてそれぞれが、専門家になっているので、生産性はとても高い。
日本では、これらが未分化のままであり、生産性はあまり高くない。
しかもソフトウエア産業に対しても、アメリカは政府の資金投入があったのに対
し、日本では民間主体でしかも大手メーカーの下請けが多いことも日本のソフトウエ
ア産業の伸び悩みの一つである。
しかし日本の特徴である柔らかい分業の下で、労働者たちは終身雇用などによ
り、労働意欲は高く、ゲームソフトなどの創造的な分野で力を発揮したり、エラー率の低さが世界でもトップクラスの製品を作ることができるので、日本は無理してアメリカの
真似をやらずに、日本の風土に適合したアメリカのいいところを取り入れ、日本独自のスタイルで行けばいいと思います。
提出が遅れてすみません。
●●● 論点5 田辺健太
専門性に基づく分業と柔らかい分業の功罪は前回の論点で述べた通り。これをソフトウェア業界という視点で考えるとき注意しなければならないのがバグ発見時の処理方法であろう。今まではアメリカ式の分業では、その場で処理ができないという問題があったがこれもITの進歩により情報の共有化が実現し、その弊害がなくなったと考えられる。具体的には進捗状況の共有化が可能となったことである。これによりバグが発見されると瞬時にすべての人間がそれを知ることが可能となったのである。すべての人間が知らなくてもプロジェクトリーダーさえ知れば的確の処置がとれるシステムが完成した。また、ここで日本の優位性が消えた。労働者のキャリアデベロップメントに関してはOJTで補うという考え方もできるが、基本的に日本もアメリカも個人の適正を会社が判断してしまうというのは変わらないようであり、適正を個人が判断する制度も必要であろう。
結論、ITの進歩により進捗状況の共有化が可能になったため、アメリカ型の方が効率、コストを考えても優れているといわざるを得ない。
●●● Ogawa 6月3日の宿題
アメリカ型の縦割りの産業システムんの特徴は、1つ1つの役割がはっきりしていって専門性が高い、日本型のシステムの特徴は柔軟なシステムでいくつかの工程が重なっていると授業で教わった。この特徴を踏まえてソフトウェア産業を考えてみると、現在はアメリカの方が数段発展しているが、システム的に見て日本のシステムでも十分に対応できると思う。ソフトウエアは、様々な人間が使うものだと思う。だからソフトウェアはその1人1人の要求に対応できなければならない。アメリカ型のようなシステムだと専門性が強く、ある1つの分野に対しては専門的な意見を言えるが、トータルでそのソフトに対する意見を言えないのではないかと思う。やはり、それなりの知識がある人の意見をたくさん取り入れて試行錯誤して制作した方がいいソフトが制作できると思う。その点、それぞれの過程を担当している人でも自分の担当以外の分野にも意見できる日本のシステムはソフトウェア制作に適しているのではないだろうか?
●●● masahiro yadoiwa
専門性にもとずく分業は、SD、プログラマー、テスター、つまり立法、行
政、司法がきっちり3つに分かれて、それぞれがその道のプロにより行われるの
で、お互いが管理し会い、生産性が高く、優れたソフトを作れる。しかし、きっ
ちり分けられているがゆえ、労働者が、その仕事だけをやっていれば良いと考え
てしまう場合があるので、労働者の向上心を伸ばすには向いていない。
柔らかい分業は、立法、行政、司法がはっきりしていないので、互いの仕事の
管理があいまいになり、生産性や、内容も低いものにしてしまう。しかし、長期
的には、SDがプログラマーにもなれるなど、労働者の仕事への向上心を伸ばす
ことが出来る。
アメリカのように、労働者が、決められた仕事以外はしないという時は、前者
になり、日本のように柔らかい分業が風土になっているような国は後者になる。
これからにほんのソフトを発展させるには、ソフトが、ハードの附録という考
え方をなくすことが重要におもえる。
感想
形のないソフトを価値のある者とみなすのは、何か難しいと思いました。
●●●6月3日の課題,suzuki
ソフトウェア産業においての専門性に基づく分業は、それぞれの行程をプロが担当するため、まさに三権分立がしっかり行われているため生産率がアップし、機能性の優れたソフトが作られる。しかし、独立企業のため強い企業しか残ることが出来ないし、外部労働市場のため企業データが漏れてしまうという欠点がある。それに対して柔らかい分業は、米国のように分割はしっかりしてないが、仕事区分が確立してないため、長い目で見た場合に労働者に向上心が生まれる。また、社内生産による内部労働市場のため、データは内部に蓄積され品質においては世界トップの実績を持つ。しかし、日本は知的生産物に対して弱い。これは、プロ集団が存在しないためである。
現在、日本のソフトウェア産業は完全に米国に負けているし、これからも追い越すことはないだろう。そのためには、組織風土を変えなければいけない。しかし、未来は誰にも分からない。
授業の感想
やはり、どちらの分業が良いとは一概に言えない。それぞれのメリット、デメリットを考えながらの分業が一番良い方法であると思う。この鍵を握るのもやはりそれぞれの風土ではないかと思う。
●●●6/3の宿題 E080182
"Yoshiki Kishida"
アメリカのソフトウェア産業は、SD・Programming・Testerの3つの独立した分業のもとで専門性を重視しているため、ハードの場合と比べると、非常に高い生
産性をもち、外部労働市場を対象としているので需要も多いし、政府もバックアップしている。
これに対して、日本のソフトウェア産業は、アメリカで見られた3つの分業が、交じり合い、未分化していて、生産性も低い。そして、内部労働市場であることか
ら産業としては、まだまだ未成熟である。しかし、日本にこれらの分業の独立を求めた場合、恐らく労働者の向上心は損なわれるだろう。また、日本はあえて未分
化にすることで、ゲームソフトのようなエラー率の少ないソフトでさらに生産力を活性化させることができるだろう。
<授業の感想>インターネットからの取り込み作業でまた遅れをとってしまって友人からコピーさせてもらうことになった。いい加減、パソコンにも慣れてきたの
で今度は自分で出来るようにしたい。
●●●宇多 6月3日
まず専門性に基づく分業においては、授業の内容に促して言えば、SD、
Programming,Testerがはっきり分離されているということである。これは分業の
効率化をねらったもので、スペシャリストになることによって生産性が向上する
というメリットがある。一方、柔らかい分業では未分化であるといえる。これは
逆に生産性は下がるが、仕事に関するモチベーションはSD部門への飛躍が可能な
ため高い。どちらが良いとは言えないのである。それは各国の文化・国民性の違
いによるからである。国民によって分業最適化のグラフの曲線の傾きの数値が異
なると言うことであろう。
●●●糀谷 一泰
アメリカは古くからソフトウェア産業というものが成熟し、一つの市場として機
能している。
そこでは、授業でも扱ったように国を挙げてとりくんでおり、有能なOSソフト
などを世界に送り出した。その理由として、専門的分業によってスペシャリスト
が養成され、ソフトウェアの全体のレベルを押し上げていると考えられる。特に
優秀なスペシャリストは、各企業からヘッドハンティングされ、しのぎを削って
いるからではないだろうか。
一方、日本ではソフトウェア産業の歴史がまだアメリカと比べると浅く、肩を
ならべるまでにはなっていない。ソフトウェア産業にも日本的労働慣行をもちこ
み、柔らかな分業をおこなっているせいか、アメリカソフトとの国際競争力では
大きく水をあけられている。
しかし、指摘されたようにゲームソフトという面では、話は別である。日本で
はコンピューター=ゲームというような形で浸透している事からも解るように、
需要は大変に多い。必然的に力を注ぐのもゲームソフトとなってしまう。そこで
日本の場合は、スペシャリストだけというよりも企業が一丸となって開発してい
る事が多い。創造性や斬新なものを求められるゲーム業界においては、むしろ柔
らかい分業のほうが機能している。これから急激にアメリカナイズされていいた
時、日本の個性を無くさないようにしなければならないだろう。
●●●6月3日の課題
shunichiro mitsutake
専門性に基づく分業は、SD,プログラマー、テスター、つまり立法、行政、
司法が3つに
分かれていて、それぞれの部門がきっちりと独立しているので
生産性は高い。しかし、こ
のように各部門がはっきりと分かれているので、
長期的に考えると、労働者の向上心を奪 ってしまっている。
柔らかい分業は、専門的な分業とは違って、立法、行政、司法が交じり合
い未分化であ
る。そのため生産性も低い。しかし、長期的には、ソフトウエ
ア労働者の動機付けの面か
らは未分化の方が良いように思える。また質の面
でも、終身雇用制のため、エラー率が少 ない。
このように見ると、どちらが良いともいえない。だからその国にあった風
土によって分 業は行われるべきだと思う。
授業の感想
今回の授業で日本ではとても質の高いソフトが作られている事が分かった。
●●●Daisuke Fukutome
ソフトウエア産業における分業についてその功罪についてだが、アメリカのよう
に生産を分離することによって生産性を上げるというのは、確かに”功”の部分
であると思うが、だからといって日本の柔らかい分業が”罪”であるというのは
まったく違うことだと思う。それは、風土や文化の違いという観点からも説明す
ることができるし短期、長期という時間的な観点からも説明することが出来るの
ではないだろうか。むしろここで問題になるのは、国の対応ではないだろうか。
アメリカは国防省などの政府資金の投入があったのに、日本は民間主体であり産
業が成熟しなかった。
「授業の感想」前回の感想でも述べたが、インターネットからのデータの取り込
みの説明がはやすぎてなかなかついていけない。一応言われたとうりにやっては
いるがもう少し詳しくやさしく説明していただければありがたい。
●●● Daisuke Unpou
アメリカはSDとProgrammingとTesterに完全に分かれていて
専門性にもとづく分業が行われている。一人一人の仕事がはっきりしているため
生産性は高い。また、外部労働市場によってアメリカのソフトウェア市場は発展
している。しかし、専門的分業のため労働者の向上心が低いことや創造性が発揮
しにくいという問題もある。日本は未分化な分業制で、部門間の境界はあいまい
である。このことが生産性が低い一つの要因になっている。では、日本も専門的
分業を取り入れてはどうかと考えられるが、労働者の向上心の低下や日本の社会
風土にあわないなど問題がおこってくる。また、社内生産が多い内部労働市場の
ため国内の市場が発展しない。日本の良いところは、エラーの発生率など品質管
理において非常に優れていることである。これは、内部労働市場や柔軟な分業制
にもよるものである。このように日本の分業制は長所と短所をあわせもってい
る。それぞれの国によって風土や環境が違うのだから、日本にあったやり方を探
せばいいと思う。
●●● 情報経済の課題⑤ E08-0265 内山ゆう子
ソフトウエア生産における分業について、専門性を重視したアメリカでは、それぞれの分野,SD,PROGERAMMINNG,TESTERが完全に分離し、それぞれが独立している為、効率的で、生産性は高い。しかし、最後のテストのとき、ミスを発見した場合、そこで処置できないのでSDに戻したり、PROGRAMMINGに戻したりと非効率的である。
一方、日本のような柔らかい分業の場合、分業があいまいで短期的に見ると生産性が低い。しかし、分業があいまいで混ざり合っているためミスが見つかったら、すぐに処置できる。
また、終身雇用、内部労働市場の下で、エラー率の低い高品質のソフトを作ることができる。
感想
どちらのやり方がいいとは一概にいえず、日米それぞれの風土に合った分業をおこなえばいいと思いました。
●●● 大慈彌
⑤ソフトウエア産業における専門性に基づく分業と、柔らかい分業とを比べ、
その功罪を述べよ
アメリカのソフトウエア産業では、システムデザイナー、プログラマー、テスターの仕事がそれぞれ専門化し、司法、立法、行政のようにそれぞれまったく別の仕事として成り立っている。その結果、生産性が高くなる。
一方、日本では、この3つの異なる業種を一人でこなしている。そのため入力ミスがあってもなかなか発見しずらく、トライアンドエラーを繰り返し時間のロスが大きい。したがって、生産性は低くなる。
このように、生産性の面から見てみるとアメリカの専門性に基づく分業の方が効率的に思えるが、品質の面から見てみると、日本のソフトウエアや、ゲームソフトのエラー発生率は世界一低く品質面ではアメリカよりも優れているということができる。
このことから、アメリカの専門性に基づく分業と日本の柔らかい分業はどちらがいいと決めることはできないと思う。同じ物を生産するにしてもその国の風土や国民性にあったやり方があり、その方法を用いて生産性が上がればそれで良いと思う。
●●● 5/27の課題 E08-0294B 奥澤 啓之
日本の柔らかい分業では新技術を取り込みやすい風土が確立していたとあるが、私
はアメリカの専門別分業にも新技術の導入はあると思う。ただ、新技術の導入後に
アメリカと日本では差が生まれたのだと考える。
日本は給与体制の中に生産性の向上による利益増加分を労働者にも還元できるシス
テム(給与の2割が生産性によって左右される)であったために、生産性を上げる
ために新技術を導入しようとした。そこで労働者は、さらに効率よく生産性を上げ
ようと考えその結果、すべての人間が一連の作業を行えるといった、日本的な柔ら
かい分業が出来たのではないかと考える。要するに、新技術導入によって一連の作
業全体の効率化が図られたのではないかと考える。
一方、アメリカにも新技術の導入はあったと考えるが、専門別であったために一つ
一つの行程での新技術の効率化ははかられたと思うが、一連の作業工程ではそれら
がかみ合わず、生産性の向上にはつながらなかったのではないだろうか。また、生
産性に賃金が左右されないとすれば、労働者の労働意欲の低下で生産性が上がらな
いと言うことも考えられると思う。
以上が私の仮定である。
授業の感想
日本的な柔らかい分業が良いのか、アメリカ的な専門的な分業がよいのかという問
題があるが私は、各産業、企業に応じた分業があると思います。一概にどちらか一
方に絞るべきではないと思うのですが。
●●● 大慈彌
④専門別分業と柔らかい分業について
日本の柔らかい分業というのは、自分の仕事はこれと決まっているわけでなく、また他人の仕事が遅れていればそれも手伝うので、誰か1人がかけてもお互いに補っていけるので、仕事の進行にはあまり影響を与えないという利点がある。
アメリカの専門別分業は各自の専門が決まっているため、1人が欠けてしまうと仕事全体がストップしてしまう事もあるだろう。つまり、一人一人はそれしか出来ないという事かもしれないが、見方を変えればスペシャリストという事が出来るわけで、日本の柔らかい分業とアメリカの専門別分業は一概にどちらが良いかは、言えないと思った。また、それぞれの方法で向く産業、向かない産業が必ずあると思った。
●●● Makiko Takahashi
6/3の課題 E08-0621A 高橋牧子
アメリカにおける専門性を重視した分業では効率性があがり、コストも削減で
き、生産性が向上する。しかし、はっきりとそれぞれの部門が分かれてその部門
内で専門性が高いため、それぞれの部門でトラブルが生じた時にその部門の人で
しか、解決できないということが起きてしまう。一方で、日本は柔らかい分業の
ため生産性はアメリカに比べると低い。しかし、ソフトウエア産業においてエラ
ーの少ない専門性をより向上していけば生産性は高くなるだろう。
●●● 課題 Suzuki
日本の柔らかい分業は、自分の仕事以上の仕事をするため、他に対しての適応性は優れている。だから、労働生産性3原則のもとに相乗効果を生みながら積極的に新技術を導入した結果、分断されていた分業が逆分業なされ、高度成長の要因となった。それに対し、アメリカの専門別分業は、自分の仕事しか行わず他の仕事に対しての適応は出来ない。しかし、そのため自分の仕事の能率は上がり、スペシャリストが存在するのだろう。時と場合によっての適応性が異なるため、また組織風土も関わり、どちらがおい分業とは一律にはいえないだろう。
授業の感想
様々なデータをグラフ化する。分かり難いデータもグラフ化することで、見やすく理解もしやすくなるだろう。これから色々な授業でもこのグラフ化を役立たせていきたい。
●●● 論点4 田辺健太
確かにリエンジニアリングという概念がアメリカで普及する前までは、アメリカの専門別分業はコミュニケーション不足という弊害が存在した。これが生産性向上という視点でアダムスミスの唱えた分業論の効率性という点で種々の問題を生み出していたことは事実であり、日本の方がトータルで見た業務効率という点で優位性が存在していたかもしれない。しかし、アメリカはリエンジニアリングによりこの点が劇的に改善された。この点を如実に証明しているのが「時間あたりの価値生産性(ECONOMIST February 13,1993)」である。アメリカを100とした場合、全産業で日本は58、強いといわれる製造業ですら80でしかない。こうして見ると日本の緩やかな分業はアメリカと比べてもはや優位性を持っているとは言えないのではないか。日本の分業を支えてきたのは労働生産性に代表される就社意識で、アメリカの専門別分業を支えてきたのはキャリア意識である。アメリカの従業員はJob Descriptionにより仕事が規定されている。これがコミュニケーション不足やIt・/FONT>s not my business.などという言葉を生み出したと考えられる。しかし、ITの進歩がその弊害を打ち破った。ITの進歩は情報の一方通行から双方向のコミュニケーションを可能にし、情報の共有化を実現した。これにより今まで言われていたアメリカの分業制度の弊害はなくなった。アメリカの分業はキャリア意識にのみ支えられているため企業としての統制がとれず、それが生産性を抑制する作用になるのではないかという批判があるかもしれないが、アメリカの企業は明確なミッションが存在し、全従業員がこれを共有し、誰もが即座に答えられるような状態にある。このミッションにより企業としての統制が取れているためこうした批判は当てはまらないと考えられる。
こうして考えてくると労働三原則による就社意識に支えられている日本企業はどうしても優位性を保てないのではなかろうか。特にこれからの不確実性の高い時代において、これまでの固定的な労働市場から流動的な市場への変貌が予期されるような状態ではますますその傾向が強くなるといえる。
これからの時代は経済のソフト化・サービス化に伴いホワイトカラー層の増加が予想される。そうなるとホワイトカラーの2極分化が起こってくるものと私は考える。これからのホワイトカラーに必要とされる能力は①語学(グローバル化に伴い必然的に必要になる)、②アカウンティング(会計基準の高度化にともない財務担当に任せていればいいという時代は終わり、これが理解できないと経営判断ができない時代に突入)、③マネジメント能力。こうした能力を身につけていない人は2極の下位層に位置付けられるようになり、身につけている人は上位層に位置付けられると考えられる。つまりホワイトカラーは真のホワイトカラーとブルーカラー化したホワイトカラーに二極分化されると思われる。そうした時代のもとではスペシャリストやゼネラリストといったカテゴリーでの分割は無意味なものになってくるのではなかろうか。これから要求されるホワイトカラーのあり方はゼネラリストの要素を持ったスペシャリストであると考えられる。確かにリエンジニアリングによりスペシャリストは必要なくなったかもしれないが、それは過渡的なものではないかと考える。マーケットのグローバル化に伴うメガ・コンペティションの中でCSなどを追求して生き残りを考えていくとしたら、どんな単純労働の中にも専門性の需要は出てくると私は考える。もし、それが誰にでもできるシステムであるとするならその業務はアウトソーシング化が起こると考えられる。なぜならそうした業務は自社で抱え込むよりスケールメリットを生かせるベンダーに任せたほうが生産性、投資効率が上がると考えられるからである。また、労働者がキャリアデベロップメントを考えるのであれば、これからの経営の高度化に対応していくためにゼネラリストとスペシャリストを合わせたマルチな能力が要求されると思う。これが私の考えるホワイトカラー二極化の根拠である。もちろん前者がブルーカラー化したホワイトカラーで後者が真のホワイトカラー。
こうして考えると日本の労働三原則に支えられた分業制度ではもはや新技術導入に対するメリットはなくなったと考えられる。労働三原則を守れるような時代ではもはやなくなってしまったから。アメリカの分業制度のほうが労働者がキャリア意識とミッションに支えられ、明確なJob Descriptionが存在しているため新技術を導入しやすいと考える。何より、リエンジニアリングにより今までの弊害を取り除くことが可能になったのだから。
以上、専門的分業と柔らかい分業が今後の技術導入に対してどうかという視点で考えてみました。
●●● 大慈彌
④専門別分業と柔らかい分業について
日本の柔らかい分業というのは、自分の仕事はこれと決まっているわけでなく、また他人の仕事が遅れていればそれも手伝うので、誰か1人がかけてもお互いに補っていけるので、仕事の進行にはあまり影響を与えないという利点がある。
アメリカの専門別分業は各自の専門が決まっているため、1人が欠けてしまうと仕事全体がストップしてしまう事もあるだろう。つまり、一人一人はそれしか出来ないという事かもしれないが、見方を変えればスペシャリストという事が出来るわけで、日本の柔らかい分業とアメリカの専門別分業は一概にどちらが良いかは、言えないと思った。また、それぞれの方法で向く産業、向かない産業が必ずあると思った。
●●● リエンジニアリング、リストラ、組織の水平化の違い
Kaoru Fujita <e070991@isc.senshu-u.ac.jp>
e070991H Kaoru Fujita
リストラとは、人員削減や、不必要事業所、不必要増資等、不採算要素の、切り捨てであり、組織の水平化とは、企業の情報管理、中継の役割を果たしていた人員(中間管理職)を、コンピューターを導入することによって、人員の削減、スリム化にし、企業を水平にすることである。リエンジニアリングとは、プロセスの見直しあり、各部門ごとの、リエンジニアリング及び、全部門を通じたリエンジニアリングは、企業にとって、大変効率よくなり、スリムになると、思います。
●●● 鶴田 素秀
Wed, 13 May 1998 14:26:09 -0700
この間の授業で、先生が述べた意見は現代における分業の盲点をうまくカバー
したものだとおもう。なぜなら、現代の欠点としてコミュニケーションの問題が
あるが、コンピューターをただ入れただけでは、抜本的な改革にならないことが良く分かった。
この点から情報器具のより合理的な使い方が重要な時代ではないかと痛感し
た。
●●● 5月6日の宿題
Date:
Thu, 18 Jun 1998 13:29:31 -0700
From:
junji kurihara
分業と逆分業の矛盾についてうまく考えがまとまりませんでした。なぜなら分業
と逆分業のどちらが生産性の向上にとって良いものなのかをずっと考えていたか
らです。しかし、これは大きな間違えであり、これら2つを別々に考えるのでは
なく仕事の過程により変化させれば良かったのです。つまり、分業を行ってい
て、その分業の最高分業点まで到達したら、そこからは逆分業を行っていったら
良ということです。ですから、1番大切なのは、分業と逆分業との境目の最適分
業点を見つけていくことだと思います。
とっくに送ったつもりでしたが先生の下にメールが届いてなかったみたいなの
で、もう一度打ち直しました。遅れてすいませんでした。
e080103J 栗原 淳二
●●● 4月22日の宿題
Date:
Thu, 18 Jun 1998 14:08:21 -0700
From:
junji kurihara <e080103@isc.senshu-u.ac.jp>
私はファミリーレストランでバイトをしています。働き始めてもう三年になり、
店の様子もすっかり変わりましたが、一番変わったのが、コンピュ-ターの導入
によって仕事が簡略化されたことです。これは、営業管理に大きく関わり、一時
間かかっていた仕事が約半分の時間で出来るようになりました。また、三人でや
っていた仕事を一人で行えるようになりました。その結果、今日入ったお客の統
計を計る人、一日の収支の計算をする人というように、それぞれ別々の仕事をし
なくてもよくなりました。つまり、一人一人の役割が決まっているのが分業なの
ではないかと思います。そして、コンピューターの導入により、それらの仕事を
効率よく上げられるといったことが逆分業を行っているということなのではない
かと思います。
E080103J 栗原淳二
●●● Mizusawa
分業と逆分業について再度検討
アダム・スミスの「国富論」における分業が生産性を向上させると言う考え以
来、各企業は仕事を細部にわたり分化させ、大量生産・大量供給と言う図式を可
能にしてきた。しかしあまりの分業の行き過ぎは各部門間を孤立させその調整に
支払われるコストは分業の進行に伴い増加し、ある段階で生産性は下降線を描
く。そこで分業が細部にまで浸透していった企業は逆分業、部門間の統合をし、
調整コストを減らして生産性を拡大する必要があった。つまり、分業は個々の労
働者の技巧を高め、作業間の移動の際に失われる時間の節約を産むだけでなく分
化された仕事間の調整を必要とする。よって、分業は生産性を向上させる普遍的
な考えではなく行き過ぎの分業には仕事を統合する逆分業が必要とされる。
●●● E08-0621A 高橋牧子
1.「分業」と「逆分業」の矛盾について
一人一人が専門的に一つの役割を果たし、次へ送るという分業発達は効率性が向
上し、さらにそれによって生産性も上昇する。しかしその発達が行き過ぎると逆
に生産性が下がる。たとえば、1~5のだんかいがあるとする。3において何ら
かのトラブルがあった場合後の4.5の作業がストップしてしまう。逆分業によっ
て最適分業点を見つけることが必要である。
遅れてすみませんでした。