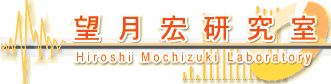所得格差を税制面、社会保障に分けて考察。
[税体系]国に納める→国税
地方公共団体に納める→地方税
[国税の割合]所得税が30%、法人税が次ぐ。
所得税は累進課税制度(所得に応じて納税率が増える制度。個人が収益を得たときに納める税金。
[所得税率の税構造の推移]最高税率は次第に低くなっている。
平成11年度最高税率の引き下げ→高所得者の優遇
[法人税]法人の所得に課せられる国税。現在の基本税率は30%。
↓
高所得者や大企業への優遇がされた。
[歴史的背景]
・ 中曽根改革→大型減税と規制緩和による消費の活性化を図った政策。
・ 竹下改革→個人所得税、個人住民税での累進税率の大幅緩和。
[社会保障]年金・医療・生活保護
低所得者層の保護ということで生活保護に着目。
[生活保護]生活保護により地方税・住民税・国民年金・上下水道基本料・公立高校授業料など免除。
[世帯別保護世帯数]平成7年以降保護世帯は増加。高齢者世帯の増加によるもの。ただし、障害者世帯は減少。
北海道・大阪に保護を受けている世帯多い。
[結論]税制面では中曽根・竹下内閣の税制政策が高所得者に対しては優遇、低所得者にとっては厳しい物になった。
また、社会保障の面からの考察は高齢化になりつつあるため、今後セーフティネットが増えてその結果財政負担が増加してしまう。
|