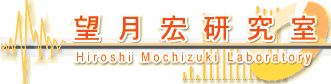[税制面からのアプローチ]
ジニ係数の現状
→現在格差をあらわすジニ係数を考察してゆくと、当初所得においてではさほど世代間格差は表れないが、所得再分配後では高齢者の格差が増大することが分かった。
税制と社会保障の所得再分配の寄与度について
→まず、個別のベータを見ると社会保障では当初所得ジニ係数と再分配後のジニ係数はそれほど差が見られなかった。また、税に関しても同じようなことがいえる。次に社会保障の再分配の効果なのですが、社会保障によって再分配されることによってジニ係数が0.1%の大きな差が見られた。このことにより、社会保障は所得再分配に効果があった。最後に税と社会保障の改善度について考察すると、1981年以降社会保障の改善度が税の改善度を超えて、2003年にいたるまで改善度には開きがで、最新のデータでは社会保障の改善度寄与度が23パーセント、税の所得分配による改善度は1パーセントとなっている。このことによって、所得分配は社会保障に最近は改善度が高いといえる。
所得税についての考察
日本における所得税の変化は昭和61年以降税構造の簡素化が起こり15段階から5段階亜へと変化した。そのことによっては国民にとって高所得者にとっては税負担が軽くなり、低所得者に対してはきつい税体系に変化した。
[社会保障について]
年金について
→年金について年金には終身または一定期間にわたり、毎年定期的に一定の金額を給付するする制度で、支給される金銭である。年金の目的には、老年・障害。死亡などによる補償を目的とするものである。公的年金に関しては、国すべてが国民の面倒を見る制度ではなくて、長生きしすぎたことに対する保険である。年金はどんなに長生きしても死ぬまで定期収入として受け取れるメリットがある。
年金での問題
→現在メディアで騒がれているように年金での問題点は、年金の未納率、保険料の徴収不能が上昇しているこのことの一因としては、やはり低所得者が増加し、保険料を支払えない人が増加したのではないかと考えられる。
年金での世代間格差の問題について
→1960年代の当初の計画では本格的な年金給付ではなく、楽観的な見通しだったが、保険料を低く見積もってしまったのは、成長率と割引率の想定を間違ってしまったことがあったからだ、また、ゼロ成長時においては、ありえない高い割引率であった。また人口の高齢化を著しく過小評価してしまったそのことによって、世代間での格差が生まれてくる要因となったのだ。
年金のこれからの対策
→これから、国家財政がきつくなる中で私たちは2つの提案をしようと思います。一つ目は年金の支給年齢を引き上げて年金額の支給額を7割程度までに減らすこと。二つ目としては、保健負担者を増やすことがあげられる。この具体的な方法としては、女性労働率を高め、また高齢者の労働率を高めて、また外国人労働者にも制度をしっかり整備し保険料を徴収できるようなシステムが必要とされる。
生活保護について<br>
→生活保護に関しては、憲法25条に即して国民は最低限度の生活が保護されている。そのことが生活保護の意義である。現在生活保護者世帯は増加となっている。バブル時期のときは一時期減少傾向にあったのでが、経済が停滞していったバブル後から生活保護の件数が増加したことが分かった。またその時期に保護の給付水準が引き下げられたことも要因として挙げられる。世帯別に考察すると、高齢者への生活保護支給は年々増加している。しかし、注目すべき点は障害者に対しての生活保護が平成7年以降に減少していることである。これは、介護の段階的な格付けによって補償額が変わったことが一因としてあがるのではないかと考える。
[結論]
今回の分析によって、政府の再分配効果は税制よりも社会保障に寄与していた。また、今後年金を支給年度をあげる必要性、また保険料を徴収する負担数を増やさなければならない。今回分析して、国の財政政策にどのような風に使われているのかなど、幅広い分析をしてゆかないといかないと感じました。
|