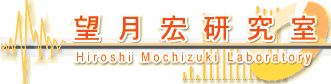|
■① 前回設定した目標
所得税の家族構成別の計算。そこから所得税の仕組みについての理解を深める。子供手当給付と扶養控除制度の改正に伴う負担の変化をみていく。
■② 今週の本ゼミでの成果
子ども手当の算入方法に不備があったことを指摘された点が一番の収穫であった。子ども手当は現在の国会での議論では、所得として算入され課税対象となるかどうか未定である。つまりこの手当がどのような扱いをされるかを明記した法律が成立していない。もし所得となるならば雑所得に算入され、結局増税となる可能性がある。民主党は参院選前に子ども手当の給付開始を目指している。前期の活動中に新たな問題が出てくる可能性もあるので、日々の情報の変化を確実に把握していく必要がある。
■③ 来週の本ゼミでの目標
来週からは今までの理解をもとに、所得税の問題点を探していく。難題であることは間違いない。しかし今後の日本の発展を考えるためには歳入の改革、つまり税制度の改革は避けては通れない問題である。そのためにも少しずつ、また確実に税制度の抱える問題点を洗い出していく。
|