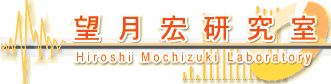◆
■① 前回設定した目標
医療保険制度の歴史的理解。
■② 今週の本ゼミでの成果
高度成長期が終わった時期から顕著になってきた高齢化の進展により、高齢者医療費の増大が国民健康保険(国民健保)などの財政の逼迫をもたらし始めた。そこで1983年に老人保健制度が導入され、以前の老人医療費無料が廃止になり高齢者も医療費の一部負担をすることになった。一方で高齢者や低所得者が多く加入し、脆弱だった財政基盤を強化すべく1984年に退職者医療制度が創設され、財政調整が行われるようになり財政破綻を回避する。
1990年代に入ると医療費が毎年1兆円ペースで増加していき、再び医療保険財政の悪化が目立つようになった。そこで老人保健制度と退職者医療制度を廃止し、65~74歳までの人を前期高齢者として国民健保か被用者保険(共済健保など3つ)に加入し、制度間の前期高齢者の偏在による医療費負担の不均衡の調整方式を導入すること(財政調整)とした。また75歳以上の人を後期高齢者とし、後期高齢者から新たに徴収する保険料や被用者保険からの支援と公費で賄う後期高齢者医療制度が創設された。
■③ 来週の本ゼミでの目標
現在の医療保険制度の問題点を探る。
|