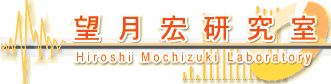■① 今週の本ゼミでの成果
フランスは失業手当と職業訓練に多額の支出があり、それぞれどのような政策にあてられているのかを調査した。失業手当は雇用復帰支援政策というものに使われている。この政策は、失業した後の所得保障から雇用復帰のための求職支援のための政策である。フランスの失業者の多くは、失業してもこの政策があるがゆえに安心してしまい、失業に対する危機感がない。職業訓練は若年層に限ってみていくと、職業訓練制と特殊雇用契約の2つのルートがある。職業訓練制は職業資格の獲得を目的とするもので、特殊雇用契約は失業者の再就職を支援するためのものである。日本との比較では、失業手当については日本の失業手当額はフランスのよりも断然少ない。日本の失業保険の受給資格が厳しく、OECD加入国の中の先進国で最低額だ。職業訓練についてはフランスの職業訓練は日本でいうトライアル雇用とOJTを組み合わせたようなもので、雇用のミスマッチ問題と職業訓練不足問題を1度で解消できるので、日本もフランスの職業訓練を見習ってみるのもひとつの手ではないかと分析をすすめた。
■② 来週の本ゼミでの目標
イギリスの若年雇用の問題について調査し、日本の対策と比較・分析を行う。
|