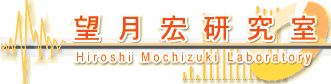■① 前回設定した目標
筋道の明確な総括資料の作成・発表をし、前回の反省点を活かした提言案を打ち出す。提言案は、不透明な宇宙産業の中で、可能な限り具体性と根拠のある内容に仕上げる。
無事に総括発表を終える。
■② 今週のゼミでの成果
総括資料作成を通して、今までの分析の総おさらいを行った。
宇宙産業は世界的には成長産業であるが、日本国内だけを見るとまだ不安定な産業である。世界市場が上がり目に対して、日本の宇宙産業の9割強は内需で輸出はほとんどなされていない。また、宇宙先進国の中でも軍需や内需が極端に低く、ほぼ官需頼りという実態であった。
宇宙産業は主に宇宙機器産業を指し、宇宙機器産業は大別すると、フライトセグメント・宇宙輸送システム・地上設備に分けられる。我々宇宙班では、宇宙とのコネクションに着目し、宇宙輸送システム、すなわちロケットにスポットを当てて分析を進めてきた。日本の基幹ロケットは現在、三菱重工がそのほとんどを担っており、製造に関しては膨大な部品が使用され、それに応じて企業の数も大きな規模を持っていた。一方で宇宙産業に関わる企業は別分野の技術を有する場合が多く、宇宙産業はそれ自体で確立しているものではなかった。
日本のロケットを海外と比較すると、コスト面や販売力についての弱みを持っていた。高品質・高信頼性を有しているものの実績と価格が足を引っ張っている状況である。しかし、制度や政府の取り組みと照らし合わせて考えると、宇宙産業は軍事的側面をぬぐいきれず、容易に技術や部品・製粉の輸出等を推進していくことは難しかった。
宇宙産業は多くの場合、国家的大規模事業として見られることが多いが、民間企業の小型ロケット製造や、大学・中小企業などの衛星開発もここ数年で見られるようになってきている。その先駆的成功例としては、ベンチャーからスタートしたイーロンマスクのスペースX社があげられる。日本でも大型とはいかずとも小型ロケットの開発が進んでおり、新たな市場開拓を予感させた。
この1年ないし、3年で日本の宇宙産業はターニングポイントが期待できる状況に差し掛かっている。産業としてはまだ将来的で、先行きの見通しが難しいが、政府の働きや、企業の方向性によって、今後の分析においては新しい側面が生まれるに違いない。
総括としては北海道の産業集積を主題とした。北海道は現時点では宇宙産業を展開できるだけの土壌はないが、日本各地と比較すると、もっとも宇宙との距離感が近いといえる。他県にも衛星などを研究する機関があるが、こと中・小型ロケットにおいては、日本で最も進んだ技術を有している土地といって良いだろう。また、発射地・スペースポートとしての立地的魅力もあり、将来が楽しみである。
半期を通して、分析はまだ宇宙産業すべてを網羅できてはいないため、これですべてを終わりにするのではなく、周辺産業や経済の仕組みを学習していくうえで新たな分析や見解につなげていくべきであると感じた。
■③ 来週のゼミでの目標
後期分析お疲れさまでした。
|