専修大学文学部考古学研究室
Department of Archaeology, School of Letters, Senshu University
|
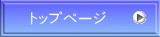
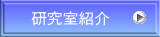
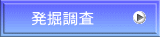
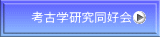
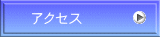
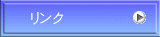
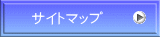
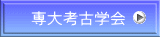
専修大学文学部考古学研究室では創設以来、さまざまな発掘調査をおこなってきました。発掘調査には2年生以上の考古学ゼミナール所属の学生だけでなく、発掘に興味のある1年生や他のゼミに所属する学生も参加しています。
現在は、考古学実習1・2の夏期学外授業として、8~9月に群馬県高崎市内で発掘調査をおこなっています。また、2~3月には神奈川県川崎市内で川崎市教育委員会・日本大学・鶴見大学・國學院大學とともに合同発掘調査をおこなっています。
以下では、専修大学がおこなった発掘調査の成果をご紹介します。
漆山古墳は、高崎市下佐野町に位置する 6 世紀後半に築造された前方後円墳です。2016 年から現在に至るまで発掘調査をおこなっています。漆山古墳の前方部は宅地造成によって削り取られてしまっており、現存する後円部の墳丘規模は、東西約
38m、南北約 30mです。
2016~2019年の調査では、後円部の西側と南西側で周堀が検出され、その外側に外提、区画溝がめぐることが確認されました。従来、墳丘全長は約70mと考えられていましたが、墳丘全長が約90mと推定され、周堀・区画溝などの周辺施設を含めると約115mとなり、6世紀後半の群馬県域では有数の大きさを持つ古墳であることが分かりました。
調査で検出した葺石の多くは元の位置を保っておらず、墳丘は後世の破壊を受けていました。しかし、後円部上部の盗掘坑内から出土した埴輪からみて、墳頂部には家形埴輪と器財埴輪を中心に配置する当該地域における典型的な埴輪配列を採用していたと考えられています。
【報告書】
・専修大学考古学研究室2022「高崎市漆山古墳発掘調査概報」『専修考古学』第16号、専修大学考古学会

 2025年度の漆山古墳発掘調査では、高崎市片岡町の MUST WIN HOTEL(旧・高崎シルバーホテル)を貸切で利用しました。
2025年度の漆山古墳発掘調査では、高崎市片岡町の MUST WIN HOTEL(旧・高崎シルバーホテル)を貸切で利用しました。
夜のミーティングは、MUST WIN HOTELのミーティングルームをお借りすることができ、大人数でも対面で実施することができました。
初めての利用であるのもかかわらず、心温かく迎えていただき、こちらの要望にも柔軟に対応していただきました。
学校の合宿など、団体の宿泊に最適です。
MUST WIN HOTEL:https://mustwin-hotel.com/

 2025年度 漆山古墳発掘調査のご案内(終了しました。)
2025年度 漆山古墳発掘調査のご案内(終了しました。)
 2024年度 漆山古墳現地説明会資料(終了しました。)
2024年度 漆山古墳現地説明会資料(終了しました。)
 2024年度 漆山古墳発掘調査のご案内(終了しました。)
2024年度 漆山古墳発掘調査のご案内(終了しました。)
 2024年度 漆山古墳現地説明会のご案内(終了しました。)
2024年度 漆山古墳現地説明会のご案内(終了しました。)
蟹ヶ谷古墳群は神奈川県川崎市高津区に所在する古墳群です。2013年から10年間調査を実施しました。当初は専修大学・日本大学・川崎市市民ミュージアムの三者が合同で調査をおこなっていましたが、その後は川崎市市民ミュージアムから川崎市教育委員会に変わり、國學院大学と鶴見大学が加わって発掘調査をおこないました。
当古墳群は台地上に形成され、調査によって3基の古墳と須恵器散布地が確認されました。1・2・3号墳の埋葬主体部は確認できませんでしたが、1号墳からは埴輪片が多く出土し、2号墳の周溝では陸橋が確認されました。また、2号墳では墳丘盛土に対する詳細な調査をおこなうことができました。古墳群に隣接して縄文時代から古代まで続く神庭遺跡があり、当古墳群の造営集団の集落である可能性があります。また、周辺の崖部には7世紀代の横穴墓群が、北西側には橘樹官衙遺跡群があり、本古墳群との関連性が注目されます。現在、発掘調査報告書刊行に向けて大学合同で整理作業を進めています。
【報告書】
・蟹ヶ谷古墳群発掘調査団2017『蟹ヶ谷古墳群』川崎市市民ミュージアム考古学叢書8、蟹ヶ谷古墳群発掘調査団・川崎市市民ミュージアム
山名伊勢塚古墳は、群馬県高崎市山名町に位置する墳丘全長約70mの前方後円墳です。山名古墳群の中で唯一の前方後円墳であり、盟主墳と比定されています。築造時期は副葬された土器などの年代から6世紀後半と推定されています。
本研究室では、2002年から2006年にかけておもに墳丘主軸及び前方部テラス面の確認を行いました。その結果、墳丘は2段築成で構成されており、埴輪列を有することが分かりました。2008年には発掘調査報告書を刊行しました。
発掘調査では横穴式石室も検出されており、調査によって明らかになった石材の加工技術などは、群馬県における石室構築技術の推移や多様性に関する位置づけなどを考える上で、重要な資料と言えます。
また前方部の調査では、墳丘下段に付け基壇工法によるテラス面の存在を確認するとともに、前方部構築時の一端を示す石積み施設およびその外側を併行するように配置された埴輪列、テラス面に施された敷石から成る前方部テラス面の構造を確認しました。これらの成果から古墳祭祀の復元を試み、盟主墳クラスの古墳祭祀を考える上では欠かすことの出来ない重要な古墳であることが分かりました。
【報告書】
・土生田純之ほか2008『山名伊勢塚古墳-前方後円墳の確認調査-』専修大学文学部考古学研究報告第2 冊、専修大学文学部考古学研究室
剣崎長瀞西遺跡は、群馬県高崎市剣崎町に所在する遺跡です。本研究室はこの遺跡の調査を1996年から1999年まで実施しました。当遺跡は弥生時代から続く集落遺跡と複数からなる群集墳(剣崎長瀞西古墳群)から構成されており、この中で最大の剣崎長瀞西古墳は円墳で直径33mの規模を誇ります。埋葬主体部は、墳頂部の竪穴系埋葬施設と南側テラス部の小石槨の2つで、後者の小石槨は剣崎長瀞西古墳群の周縁部に点在する大陸人の墓とされる積石塚との類似性が見られます。さらにこの遺跡からは、半島由来とされる馬具や金製の耳飾り、土器が出土していることから、渡来人が居住した遺跡であると考えられています。
本研究室では5・27・35号墳及びそれに付随する遺構群の調査を行いました。いずれの箇所からも多くの遺物や遺構を検出しており、なかでも5号墳出土の太刀、35号墳出土馬具、13号土坑出土の馬骨と一体となった馬具類はその出土状況から大陸由来の物がこの地に持ち込まれ、使用がなされたと考えられる遺物で、渡来人と現地人の融合や古墳築造を中心とした社会構成、首長の権力を考えるうえで重要な資料になるものです。尚、昭和7年(1932)に開墾の際に剣崎長瀞西古墳より不時発見された鉄製三角板革綴短甲、捩文鏡、滑石製模造品などの副葬品は、東京帝室博物館(現東京国立博物館)に収蔵されています。

〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1 専修大学生田キャンパス
copyright©2023 Department of Archaeology, School of Letters, Senshu University all rights reserved.
|
![]()
![]() 2025年度の漆山古墳発掘調査では、高崎市片岡町の MUST WIN HOTEL(旧・高崎シルバーホテル)を貸切で利用しました。
2025年度の漆山古墳発掘調査では、高崎市片岡町の MUST WIN HOTEL(旧・高崎シルバーホテル)を貸切で利用しました。
![]() 2025年度 漆山古墳発掘調査のご案内(終了しました。)
2025年度 漆山古墳発掘調査のご案内(終了しました。)![]() 2024年度 漆山古墳現地説明会資料(終了しました。)
2024年度 漆山古墳現地説明会資料(終了しました。)![]() 2024年度 漆山古墳発掘調査のご案内(終了しました。)
2024年度 漆山古墳発掘調査のご案内(終了しました。)![]() 2024年度 漆山古墳現地説明会のご案内(終了しました。)
2024年度 漆山古墳現地説明会のご案内(終了しました。)