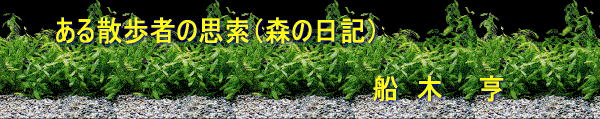
森の日記―――書を捨てて森に入ろう
平成22年8月10日
ことばとは何と薄っぺらいものでしょうか。わたしたちは、ことばを聞き、それを理解し、それに応答できるようになるだけで、何かが分かった気になってしまいます。
わたしは西洋哲学史を講義しているくらいですから、ライプニッツが何をいっているかは知っていました。すべては「モナド(魂をもつ分子)」であり、それらはみな違っており、それぞれに力が与えられ、組みあわされて機械状のものを作っている。わたしもひとつのモナドであり、ほかのモナドに直接出会うことはできない(モナドは窓がない)が、ちょうど水車小屋のなかにいるようなもので、わたしはわたしに与えられた表象の部分部分の相互関係から、その全体の仕組について数学的に推理できる。そうしても間違ってないといえるわけは、神が存在し、神がすべてのモナドを知っていて、神が知っているということは、その全モナドの集まった巨大な個体としての宇宙が、確固とした秩序あるものとして必然的に作動して、神の栄光を実現するように働かされている、そういう「予定調和」があるということだ。
いまは、そんなことをいうまでもないと思います。森に出かけていくと、ここそこに、まさにモナドたちがいることが分かります。それは知覚できないほど微細なものですが、感じとることができるのです(神の話までする必要はなかったのにと思います)。
パスカルの「繊細の精神」を思いだします。デカルト的な「幾何学の精神」も大事だけれども、それでは大雑把な見取り図しか描けないだろう、微細なものを感じとる精神も重要だと、かれはいいました。
哲学者たちのすごさについては、かれらのことばをいくら覚えても、実感となるまでは、何も分かってはいないのです。哲学者たちが感じとって語ったことは、哲学書を読んで分かる程度のものではなく、もっとずっと深い。かれらは、普通の生活をしていては、考えられないほどの深い体験をすることのできたひとたちだったのです。