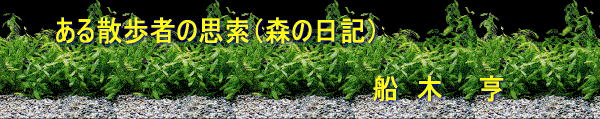
森の日記―――書を捨てて森に入ろう
平成22年8月13日
森はほかの風景とどこが違うのか。森に入ると力が抜ける。森は、緊張でこわばったからだの力を抜いてくれる。森の外には、人間の作った建物や道路や電線や塔が見えるが、そこには、幾何学ばかりがある。人間は、幾何学が好きである。直線も曲線も、みな幾何学的で、森のように乱雑なものは何ひとつない。どれも植物のように精妙ではないくせに、全体としては押し付けがましくできている。ガウディの建築のように、森に溶け込みそうな建築は、技術的には難しいのだろうか。
このことは、ちょうど言葉と文字にも当てはまる。言葉は言の葉と書くように、樹木の葉っぱに似ている。たくさんあって、それぞれがどれも似ていて、しかしどこにどれがどのようにあるかで、その樹の全体像が決まってくるように、話もたくさんの言葉を身にまとうことによって結局何をいいたいかが決まってくる。
ところが文字は何と幾何学的なのだろう。アルファベットやハングルやカタカナを見よ。直線と曲線の組みあわせで成りたっている。森を見るときには何もかもくっきりしているように見えるのに、それとおなじ距離に文字があって、「さあ読んでみろ」といわれると読めなかったりするのは、文字が異様に精度の高い視力を要求するということだ。文字は、それだけわれわれから遠くにあるということだろう。文字がない時代には、視力など、だれも気にせずに生きていたに違いない。
日本文字のうちのひらがなは、くねくねと曲がって、植物の茎のような形をしている。女性が作りだしといわれているのもうなずける。同様に、ペルシア語もくねくねしているが、イスラム思想も植物的なのだろうか。