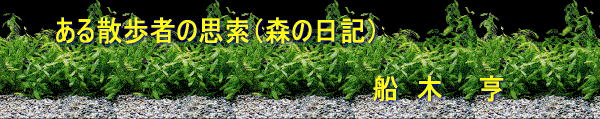
森の日記―――書を捨てて森に入ろう
平成22年8月14日
今日は昨日の午後、体がとてもつらかったので、たっぷり森に行こうと思ったが、そういう目的をすらもっていてはいけないということが最初に分かった。いつものように、ひとりでに発見するような受動的な姿勢ができていないみたいだった。
それでも小川のせせらぎの音やせみ時雨の音が耳に心地よく響いてきました。そして、人間の作る音楽など、つまならいものだ、と思いました。特に、打楽器の音がいっぱい入ったテンポを刻む音楽は、連隊の進軍を促すものだし、平和を訴える美しいメロディですら、ひとびとの連帯を促して一つの方向に進ませようとする。自然には、行進のコマンドがないばかりでなく、何のメッセージもない。
そのうち、足下の雑草にいっぱい水滴がついているのを見つけてしゃがみこんだ。これが朝露というものだろう。なぜある草たちにはいっぱいついていて、全然ついていない草もあるのだろう。ついてない草は水を吸収してしまい、水をはじきたい草に朝露がつくのかもしれない。
遊歩道を進んでいって、柵のなかにある大きくてきれいな花をつけた草よりも、柵からはみ出しながら群生している雑草たちが、よく見ないと見つからないほど小さな白い花をいっぱいつけているのに気がついた。そこにはやはり、小さな蝶が何匹も飛び回っており、そばによると、アリたちが行ったり来たりしているのが見えた。人間が栽培して人為選択してできた、名前のある大きな立派な花よりも、そういう小さな勝手に咲いている花の方がきれいだと思った。
森を出るとどうしても人工的な構築物に出会う。森のそばに空き地があって売りに出されているが、こんなに広いのなら何億円もするのだろう。そこに何とか森となじんでしまえるような家を建てて住むことができればいいな、と思った。人工的なものは直線だらけ、きれいな曲線だらけだ。理想の家はどんな家だろう。ガウディの作ったようなくねくねの家だろうか。そこで思い出したのは、ロラン・バルトのいっていた日本の昔ながらの家だ。柱がぽんぽんと立っているだけで、障子に囲まれてはいるが、ひろい廊下が取り巻いていて、障子を開け放てば、森と素通しになってしまうような建物。昔の日本人はすごいと思った。