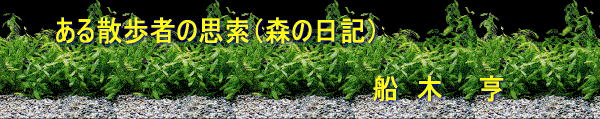
森の日記―――書を捨てて森に入ろう
平成22年8月22日

今日は森がお休みなので、逆方向に小川の傍の道から公園に向かった。小川には、覆いかぶさるように樹の枝が突き出ているが、枝の先のほうにだけ小さな枝がいっぱい出て、たくさんの葉っぱをつけている。まるで手のひらのようだな、と思った。以前に葉っぱの一枚を手のひらに比べたから、いい加減なものだと思ったが、逆に、手のひらが樹の枝や葉っぱのようなものだと考えてはどうだろうと思った。腕は、体という幹から出ている枝なのだとね。
植物を誉めてばかりいるが、あまり好きでない草もある。とくに川辺に気持ちの悪い草が群生していたりする。どうして気持悪いのか、自分でもよく分からない。いつも見るようにしていれば、そのうちきれいだと思うようになるのかな。
最近は、友だちの樹が増えたので、森が休みでもいろんなところを回っていかなければならないから、結構時間がかかる。こちらは挨拶しに行くのだが、樹にはぼくが見えない。ぼくは樹と対話しながら、「見えないもの」になりたいと思った。見えないとはどういうことか、犬に出会っても、寄ってこられもせず吠えられもせず、猫やカラスは、逃げもせずに勝手なことをし続ける。人間は、そこにだれもいないかのようにしてくれる。そんなひとになりたい。
森に行くようになったきっかけは、勝手に力をいれる眼の周りの筋肉を緩めて、左右の視野のバランスを取るためだったが、最近、顔の筋肉をゆるめるのがとても難しいことだということが分かってきた。というのも、ぼくはいつのまにか愛想よい、あるいは格好いい顔にしようとしている。顔の筋肉の力を抜くと、ぶすっとした愛想のない顔になりそうだ。力を抜いていても、にこっと穏やかな顔になれないかな。
見えないということは、そういう表情のことかもしれない。わたしは無害です、というような。考えてみると、ぼくはいつも見られることを意識してきた。そんな顔や体やことばや行動をしてきた。でも、いまは、見えない方がもっとすごいと思える。
ぼくは森のなかで、いろんな発見をしてきたが、それらはそれまでぼくには見えないものだった。発見するためには、論理的にいって、まず「見えない」ことが必要だ。樹木や草花は、ぼくが見なくても決して怒らない。ただ無関心にそこにいて、ぼくにたまたま見させてくれるから感謝。ぼくもそのようにありたい。
公園のいつもベンチには、男のひとが座っていて、横笛を吹いていた。ぼくが行くと、演奏をやめて、たばこを吸ったり、蚊を追い払ったり、お茶を飲んだりと、ちょっと笛の音とは不調和で面白かった。かれがもう一度吹きはじめると、その音色は、自動車の音とは違って、とても樹木たちとマッチしていた。人間のすることなのに不思議だなと思った。そうか、自動車の音がどうしてもなじめないのは、その音には「目的」の音色がついているからではないかな。