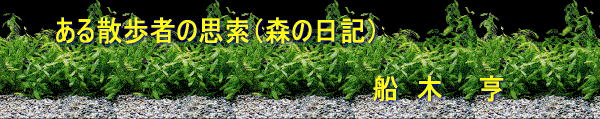
森の日記―――書を捨てて森に入ろう
平成22年8月27日
昨日も森には行ったのですが、考え事があって、虫食いの葉が多いなくらいのことしか発見できませんでした。考え事というのは、大事なひとたちのことです。かれらがうまくやっていけるのか、心配になります。どう、何をいってあげればいいのか。
今日も似たような状況かな、と思いながら、小川の傍を歩いて行くと、樹々のあいだから、ひとが立ち入ることのできないようなところに立っている樹木を見ました。かれらは見られることを一切気にしていません。ぼくもそのように立っていることができればな、と思いました。

公園に着いて、寝ぐせの樹に会って優しそうな顔をされました。近寄っていくと、その幹の何と立派なこと。写真にでも撮らないと説明できませんが、白っぽい皮の部分や緑がかった苔のついているような部分や節くれだった部分と、大変にぎやかです。何十年とかかってできてきた荘厳さみたいなものがあります。根から分かれた子どもを連れていることも、はじめて気づきました。
以前、樹の幹の色が全部違うと感動したことがありましたが、いろんな樹に近づいてみると、そのひとつひとつの幹が単色ではなく、複雑な模様の組み合わせになっていることが分かります。それぞれにまた美しく、立派です。

なかには、蔦が絡まり、それに覆われている幹もあります。大多数の樹はそうではないのに、なぜその樹だけ、と思います。蔦は、何十年もかけて立ち上がってきた樹をよじ登ってあっという間に高みに到達するのですから、ずるい奴なのかな。でもそのような見方をするのは、ずるいことをしあう人間たちです。
大事なひとたちに思うことは、ぼくがいろいろ上手にできることがあって、それと同じように、あるいはそれ以上に上手にやれるようになって、ぼくに「どうだい」といって欲しい、ということです。でも、そう考えるぼくは、自分が上手にできると思っているだけ高慢なのかもしれません。ひとの通らないところにひっそりと立ち、虫に喰われるのなら喰わせてやり、蔦に絡まれるなら絡ませてやり、自分が倒れなければそれでいい、というような樹もあります。ぼくに、そんなことができるかな。