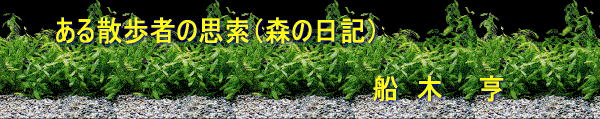
森の日記―――書を捨てて森に入ろう
平成22年8月28日
以前水際のある種の植物は好きになれないと書きました。そのおなじ植物が普通の地面にも生えていた。そんなに違和感がなかった。とすれば、気になる理由は水際という場所によるのでしょう。山中湖の波打ち際と同様に、土と水の境い目には、なにか怪しい怖さがある。幾何学の明るさと、それを支えるような冥さがある。
風景は360度違っているが、同時に24時間違っている。光の強さや角度が少し異なっただけで、違う風景が生まれてきます。おなじ森でありながら、いつも何かを発見させてくれるのは、光の違いによるのだろう。「光があたる」という表現があるが、「光があたらない」ことからも、あらたな風景が生まれてくるのだ。
草木の葉っぱを見て回ると、茎に並んでついているのと、交互についているのがあることが分かります。なるほど、植物学者がそうやって誕生するんでしょうね。そして、植物たちが教えてくれていることを忘れて、幾何学の、あらぬ方へと進んでいってしまうのだろう。

ときどき一本の小さな樹が立っているのを見る。どんな理由でどこから種子が運ばれてきたのか。孤独に立っている小さな樹。大樹になる前の樹なのか、それで十分高くなった樹なのか。いや、もっと小さな樹の芽が地面に見える。あの大樹も、昔はこんなにかわいかったのかもしれないね。
今日はケータイをもっていってたくさん写真を撮ったのだが、ケータイを構えると手に蚊がとまるし、靴の底にはガムがつくし、と散々だった。歩く速度も、いつもより早かった。やはり、「写真は撮るな」と叱られているのかな。有頂天になったりがっくりしたり、どうして精神はこんなに揺れやすいものなんだろう。