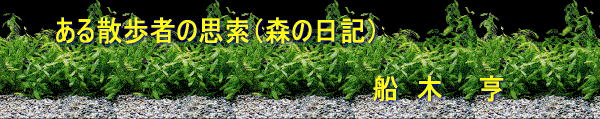
森の日記―――書を捨てて森に入ろう
平成22年9月5日
 森に入ってさまざまな覗き穴から森を見つめ、あるいは足もとの草をぼんやりと見ます。そして、つぎつぎにきれいなもの、よいものを見つけます。汚いと見ていたものもきれいに見えはじめます。森では、よいものだけを見ればいいのです。そのことは、おそらくは自分が社会的価値の善美から解放されることなのでしょう。
森に入ってさまざまな覗き穴から森を見つめ、あるいは足もとの草をぼんやりと見ます。そして、つぎつぎにきれいなもの、よいものを見つけます。汚いと見ていたものもきれいに見えはじめます。森では、よいものだけを見ればいいのです。そのことは、おそらくは自分が社会的価値の善美から解放されることなのでしょう。森で見るものは、形でも色でもありません。それだけなら写真や絵画で見れば十分です。大樹を見て見るのは長い時間、草花を見て見るのは短い時間です。日本人は人生を花に喩えてきましたが、何と比べて儚いのか。その散り方を讃えるのは、どうしてなのだろう、もっと考えてみることにしよう。
西欧人たちは、時間を運動に対して捉えていました。だけど、運動にあるのは空間だけで、すべてはいま眼のまえの空間で起こるから運動なのです。いや、動物ならみな、そうした捉え方をするのでしょう。加速と減速を知覚するのでしょう。そうしたことをするのは獲物であるか、狩猟者なのですから。
とはいえ、森も変化しています。ただあまりに小さな変化、微細な粒子の変化なので、どこが変わったか知覚できないけれど、そうしたモナドをひとは感じることができるのです。そして、ときたまハラリと眼のまえに葉っぱが落ちてきます。偶然には違いないのですが、森がそのことを教えようとしているようだ。
森を散歩して、シャワーをかかり、それからこれを書いて、そのあと、ようやく執筆活動です。毎日哲学書を読んでいますが、どうしても暗い気分になります。明るい哲学書ってないのかな、深くなくてはだめですが。哲学者のなかには長い憂鬱の時期があったひとも多いようですが、ぼくもそれに伝染されてしまいます。