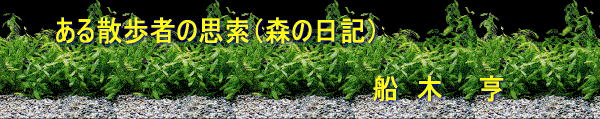
森の日記―――書を捨てて森に入ろう
平成22年9月12日
孤立して立っている小さな樹や背の高い草があります。群生しているのが普通なのに、どうしてそうなったのか、何となく気になる。自分がそうだからかな。川辺の草が刈られる理由は、きっとその勢いのものすごさによるのでしょう。小さな草の群れは残してありました。
草が刈られたことによって、川には多くの土が両辺にあって、水の流れがそのあいだをくねくね曲がっているのが見えるようになりました。水だってくねくねするのが好きなのだろう。
イギリスの道はくねくねしていますが、古代ケルト人が作った道だそうです。ローマ帝国の支配下になって、まっすぐの道が作られました。古代人は野蛮人といわれましたが、植物に倣うことを知っていた。ローマ人は文明人ですが、幾何学が好きだった、ということかな。
樹々の葉っぱのなかに、黄緑色のものがあります。新芽と枯れかかったのと、似たような色なのに、どうして区別ができるのだろう。どこに違いがあるのだろう。
道には、えもいわれぬ美しい落ち葉を何枚か見つけました。赤と黄色と茶色と濃緑の彩、形も微妙に捩れていたり、小さな穴があいていたり。どんな芸術作品よりも美しい。持って帰ろうとしましたが、やめました。あっというまにただの茶色い紙になって、散りじりに砕けてしまうことでしょう。何という、つかの間の美。シンデレラのかぼちゃの馬車のように、それはある種の魔法です。芸術作品は、その美を数百年ほど見させ続けるように制作されてきたのでしょうけれど、たったの数百年だ。