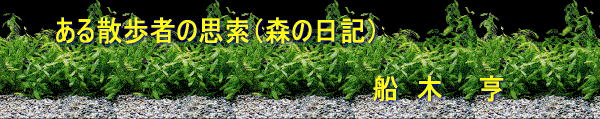
森の日記―――書を捨てて森に入ろう
平成22年9月20日
昨日、おとついとゼミ合宿で山中湖に行っていました。散歩するような状況ではありませんでしたので、3日ぶりの森でした。
森には黄色くなった葉が増えていましたし、これだけ落葉があるのだから当然かもしれませんが、ちょっと「すきすき」になっていました。覗ける場所が広がっていて、増えていて、驚きました。たった3日のあいだの変化。この辺の紅葉は12月はじめころだけど、こうやって毎日少しずつ変化しているのに、いままで気づかなかった。
枝ぶりや、すべてが上向きの葉っぱを見て思いました。この形、ひとびとは、樹の内部に理由があって、折れないように、太陽の光をいっぱい受けるように進化してきたと説明します。「環境への適応」です。
ですが、この形を生みだしたのは、光と雨と風と重力だともいえます。それらの均衡として、それらの境界線としてこの形があるともいえるのではないでしょうか。それらは絶えず変化しますから、境界線というよりは、包絡線といった方がいいかもしれない。ぼくらが枝ぶりを見るときは、光と雨と風と重力を見ている。
ひとびとは、昆虫たちの行動を見て「本能」だといいます。意識がない、プログラムされた機械のように動いているといいたいのです。昆虫たちの方が、人類よりもうまく助けあって生きている。人間たちの社会がいつもごたごたしている「いいわけ」か。
植物については、本能ということがあまりいわれないですが、昆虫に本能があるなら、植物にもあるはずです。動く植物もあるし、微速度撮影して見てみれば分かるように、どんな植物も超低スピードで、「もぞもぞ」、「うねうね」と動いています。植物に本能がないなら、昆虫にもないはず・・・どっちがいい?