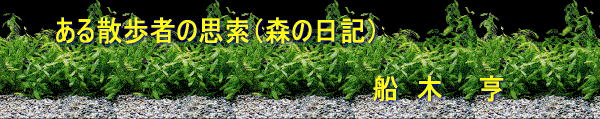
森の日記―――書を捨てて森に入ろう
平成22年9月24日
土があり、たくさんの落葉があり、苔があり、大小さまざまな草が生えていて、小さな樹、中くらいの樹、そして見上げれば、大樹が散在している。見慣れてくれば、いつもの風景、何だかコンビニのようだな、と思った。コンビニほど整然とはしていないけれども。コンビニも上中下の視線によって商品を配列してあり、ひとは無数の商品から、自分の欲しいもの、関心を引くものを見つけだす。
10万年のあいだの人類は、列を作って森に分け入り、適当な宿営地を見つけては、コンビニのようにして、水や食べられる草や木の実を見つけ、小動物や魚をとってしばらく暮らしていたに違いない。大体そこがどんな場所か分かったという時点で、つぎの宿営地をめざして出発する。ときどき、人間を食べる猛獣が飛びだしてくるからね。
思考が人間の行動を強気にもすれば弱気にもする。しかしまた、体調や状況が人間の思考の強度や内容を変化させる。どんな体調でもおなじ正しい思考ができるとはいえそうにない。何が正しい思考かも分からない。懐疑論すら、元気な体調の思考だ。正しい思考と呼べるのは、生きている身体の要請によって生じ、危険を避け、体調を整えるために何をすべきかを推理するような思考なのかな。進化論的にはそうなる。
こうやってたくさんの緑に囲まれたとき、これだけ緑であるにも関わらず、その無数の色あいの違いが多様なものを発見させてくれる。その黄色がかったり、赤っぽかったりする色の多様性は、視神経細胞の種類に応じて、赤青黄色の三原色の合成物だと説明される。だが、純粋な緑色がないということは、かえって強烈な感じがする。森の生活者からすると、すべての色は緑色からのずれとして理解した方が、色を捉えることができそうだ。