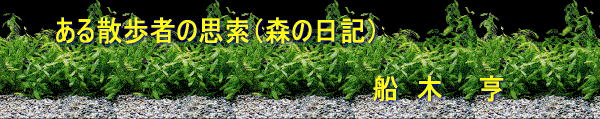
森の日記―――書を捨てて森に入ろう
平成22年9月28日
しとしと雨のなか、傘をさしてでかけました。すべてが濡れています。木の葉、枝、幹、草、地面。いつもとは色が違っていて、くっきりしている。とくに樹の幹は、おなじものとは思えないほど違って見えます。とはいえ、おなじ樹であるに違いありません。樹は夜中に歩いたりしないからね。「いつもそこにいる」ということの安心観、「お母さん」に似ている。
人間を植物の何に喩えるべきか、一枚の葉? 一本の枝? 一本の樹? あるいは花? 多くの日本人が自分を花に喩えてきましたが、非植物学的にいって、花とは何のことでしょうか。世阿弥は「枯れ木の花」などといっています。何か、はっとさせるものが森のなかにある。理由は分からないし、それは一瞬のことで、つぎの日にはなくなっていたりする。ぼくも今日は、ほとんど葉を失った枝の先に数枚ついていた枯れかかっていた葉に、はっとする美しさを感じました。
植物たちは、地形や地面の状態や日照や雨の量などに応じて、多様な種として繁茂します。どんな植物がそこにあるかというだけで、どんな自然状態か分かりそうです。植物たちは、つねに領域の拡大へと向かっていますが、そのやり方は、幾何学を使って領域を拡大していく帝国とは随分と違います。
古来、人間、特に西欧人たちは、動物と自分とを比較し、理性によって区別できると誇ってきました。それによると、動物たちは、ただ野蛮な痴呆者です。それに対し、植物と自分とを比較すると、どういうことになるのでしょうか。人間にあって、植物にないもの。植物にあって、人間にないもの。帝国は野蛮だと思います、本来は帝国のことを文明と呼んでいたのですが。
0度から100度という、絶対零度から太陽の温度までの幅からするとほんのかすかな幅に液体としての水があります。その薄氷のような幅のあいだに気温が収まってきた地球の歴史は、その意味で生命の歴史です。水がなければすべての生物は死に絶えるでしょう。とすれば、帝国は、すべてを固体のように凍てつかせようとしている死の勢力かもしれない、自然とは異なる境界線を引こうとして、ひとびとを戦争に駆り立てる。