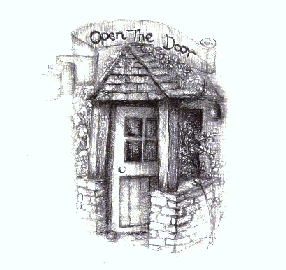
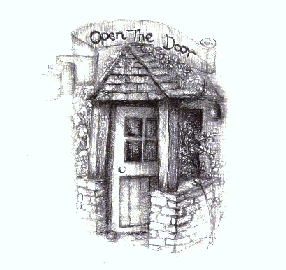
経済の世界「政府の勘定・プライマリー・バランス・ドーマー条件」(07/07/26)
経済統計学・経済の世界「四半期別GDP統計(QE)」(14/11/1)
経済統計学・経済の世界「国民経済計算入門」(14/11/1)
経済統計学・経済の世界「物価指数と実質化」(14/11/1)
経済統計学・経済の世界「無償労働の貨幣評価」(14/11/1)
経済の世界「政府部門を含む閉鎖経済の乗数効果」(06/10/05)
経済統計学「消費者物価指数の作成方法と寄与度・寄与率の計算」(14/11/1)

※当日14:40〜に同じ教室で行われる「外国書講読」(「外国経済事情(英語)」)の講義でも英国の国鉄民営化の失敗についてレクチャーする予定です。聴講を歓迎します。
※参考資料をここからダウンロードできます。
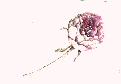
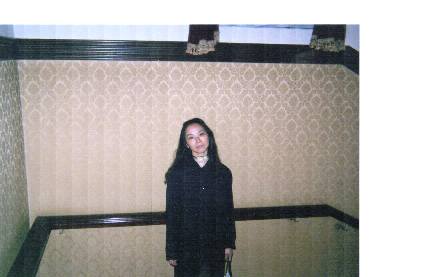

| No. | テーマ | 日時 | 場所 | 掲示された予告内容 |
| 1 | 加藤尚武『環境倫理学のすすめ』第2章を読む | 1998年4月18日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | 加藤尚武『環境倫理学のすすめ』(丸善ライブラリー、1991年)第2章「中之島ブルース―または人間に対する自然の権利」を読みます。小倉久直君(経済学部4年)の報告をもとにディスカッションを行ないます。プリント教材を用意します。 |
| 2 | ポパーと経済学 | 1998年5月 9日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | 近代経済学の方法論としての「反証主義」で有名なカール・ポパーの思想について考えてみます。作間がレクチャーします。プリント教材を用意します。[資料は、ここでダウンロードできます。] |
| 3 | 佐和隆光『地球温暖化を防ぐ』を読む | 1998年5月23日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | 佐和隆光『地球温暖化を防ぐ』(岩波新書、1997年)第3章「温暖化防止対策を考える」を取り上げます。ゼミ生の報告をもとにディスカッションを行ないます。上記教材を用意のうえ、ご参加ください。 |
| 4 | なだいなだ『民族という名の宗教』を読む | 1998年6月 6日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | なだいなだ『民族という名の宗教』(岩波新書、1992年)を取り上げます。たまには、ナショナリズムについて考えてみましょう。ゼミ生の報告をもとにディスカッションを行ないます。上記教材を用意のうえ、ご参加ください。 |
| 5 | 無償労働の推計をめぐって | 1998年6月20日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | 昨年(1997年)、経済企画庁が公表した無償労働の貨幣評価は、マスコミでも話題になりました。作間は、経済企画庁の無償労働研究会のメンバーとして推計にかかわりました。報告を作間が行ない、ディスカッションします。プリント教材を用意します。[資料(一太郎ファイルを圧縮してあります)は、ここでダウンロードできます。なお、訂正がありますので、ここでダウンロードしてください。] |
| 6 | 国籍条項をめぐって | 1998年7月 4日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | 地方公務員の任用をめぐるいわゆる「国籍条項」の廃止をめぐって、川崎市の「川崎方式」が注目されています。川崎市職員の川村肇さん(2部経済学部4年、学士入学、専修大学 商学部・法学部卒)が報告し、ディスカッションします。 |
| 7 | 無償労働の推計をめぐって 2 | 1998年9月26日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | 前期にも同じテーマで作間が報告していますが、今回は、ゼミ生が下記の資料を報告し、ディスカッションします。資料は、配布します。資料:佐藤勢津子「家計における無償労働の貨幣評価と家計生産についての一考察」『季刊国民経済計算』第113号、1997年12月。 |
| 8 | ロナルド・ドーア「橋本『行革』と新自由主義への疑問」を読む | 1998年10月3日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | ロナルド・ドーア「橋本『行革』と新自由主義への疑問」『中央公論』1997年11月号を取り上げます。現在の経済と社会とを考えてゆくうえで、保守主義=新自由主義に対する考察は欠かせません。ゼミ生が上記資料を報告し、そのうえで、ディスカッションします。なお、資料は、配布します。 |
| 9 | 日本経済は今どうなっているのだろう? | 1998年10月24日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | 吉川洋氏の論文「日本経済の現状とマクロ経済政策」をゼミ生(二部、川村肇さん、川崎市役所勤務)が報告し、ディスカッションします。資料は、当日、配布します。 |
| 10 | 卒論中間発表 | 1998年10月31日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | ゼミ生(一部4年次生)小倉久直君の卒論の中間発表です。テーマは、「指定流通機構による環境手数料導入の一考察」(仮題)です。岡野裕介君(院生)が討論します。なお、後日提出された小倉君の卒論は、ここからダウンロードできます。ブラウザとしてIEをお使いの方は、図・表を、ここで見られます。図・表の圧縮版は、ここにあります。 |
| 11 | "ケイパビリティー"で考えてみよう | 1998年11月14日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | インド人の経済学者アマルティア・センが今年度のノーベル経済学賞を受賞しました。「ケイパビリティー(潜在能力)」は、センによって創造された重要な概念です。現在、リベラリズムを考えてゆくうえで、不可欠な概念であるといえると思います。作間がレクチャーします。[資料は、ここでダウンロードできます。] |
| 12 | 景気対策を考えてみよう! | 1998年11月28日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | 最近の新聞記事(『日本経済新聞』経済教室欄など)のコピーを何点か配布し、それに基づいて景気対策を考えてみたいと思います。とくに、報告者は指名しません。なお、二部の私のゼミの応募状況により予定を変更する可能性があります |
| 13 | 卒論中間発表 | 1998年12月12日(土)18:20〜 | 神田校舎54ゼミ | ゼミ生(二部)、川村肇さん(川崎市役所勤務)の卒業論文の中間報告です。タイトルは、「今日の川崎市都市政策」。なお、当日、新ゼミ生と在籍生との初会合がありますので、公開ゼミの開始予定時間を繰り下げております |
| 14 | 橘木俊詔著『日本の経済格差』を読む | 1999年1月 9日(土)17:50〜 | 神田校舎54ゼミ | 橘木俊詔著『日本の経済格差――所得と資産から考える――』(岩波新書、1998年)を取り上げます。最近、日本は急速に不平等化しています。橘木氏(京都大学)による上掲書は、そのことを明確に示しています。一度、考えてみるべき問題だとは思いませんか?橘木氏の著書の前半部分をゼミ生が報告し、その報告をもとにディスカッションをします。なお、今年度の公開ゼミは、これが最終回です。 |
| 99-1 | 無償労働の推計をめぐって 3 | 1999年4月17日(土)18:00〜 | 神田校舎 55ゼミ | 経済企画庁国民経済計算部編『あなたの家事の値段はおいくらですか』(大蔵省印刷局、1998年)を読みます。経済学部4年、野老景久君が報告し、参加者全員でディスカッションします。上記 資料は、政府刊行物サービスセンターや書店などで入手できますので、おもちください。 |
| 99-2 | 無償労働の推計をめぐって 4 | 1999年4月24日(土)18:00〜 | 神田校舎 55ゼミ | 育児や介護など、政策的にも重要な問題を含む、無償労働の貨幣推計の問題を取り上げます。前回に引き続き、経済企画庁国民経済計算部編『あなたの家 事の値段はおいくらですか』(大蔵省印刷局、1998年)を読みます。今回からの参加も歓迎です。ゼミ生が報告し、ディスカッションします。上記資料は、政府刊行物 サービスセンターや書店などで入手できますので、おもちください。 |
| 99-3 | アマルティア・センとケイパビリティー | 1999年5月15日(土)18:00〜 | 神田校舎 55ゼミ | ノーベル経済学賞を受賞した、アマルティア・センについてのVTR(1時間程度)を観た後、短い説明をはさんで、各種資料(コピー等)を見ながらディスカッションを行ないます。 資料は用意してあります。 |
| 99-4 | 「自然」をめぐって――岩槻邦男氏の著作を読む―― | 1999年6月12日(土)18:00〜 | 神田校舎 55ゼミ | 岩槻邦男氏の『文明が育てた植物たち』(東京大学出版会、1997年)は、刺激的な著作です。環境経済学や環境会計の立場からも見逃せない重要な洞察を含んでいます。今回の公開ゼミでは、この著作の一部(第2章「新石器時代の自然」)を取り上げます。プリント教材を準備します。 |
| 99-5 | 国際収支の見方――経済対立は誰が起こすのか―― | 1999年7月17日(土)18:00〜 | 神田校舎 55ゼミ | S-Iバランス(貯蓄投資差額)論にもとづく国際収支の見方を勉強してみましょう。日米経済摩擦のような国際経済の諸問題を理解するうえで欠くことのできない視点を得られるでしょう。岡野裕介君(本学大学院M2、国際経済学専攻、野口旭ゼミ)が報告します。プリント教材を準備します。 |
| 99-6 | 東ティモール問題から「ナショナリズム」について考える | 1999年10月16日(土)18:00〜 | 神田校舎 55ゼミ | また、ナショナリズムの幻想が災厄をひきおこしてしまいました。8月30日の住民投票で8割近い人々がインドネシアからの独立の意思を表明した東ティモールで、独立反対派武装民兵らによる大規模な虐殺と破壊が起こってしまいました。テレビで、廃墟となった中心都市ディリの映像をごらんになったひとも多いでしょう。1975年にインドネシアが東ティモールを侵略してから20年以上の年月が過ぎました。今回の惨事は、ようやく、東ティモールのひとびとの悲願が達成される、という期待を多くの人がもった矢先のことでした。東ティモール問題を「ナショナリズム」という側面から考えてみます。プリント資料を配布します。 |
| 99-7 | 『ちびくろさんぼ』のことを考えてみよう! | 1999年11月13日(土)18:00〜 | 神田校舎 55ゼミ | ゼミナールにとって、経済学の<トレーニング>にとともに重要なのは、<ディスカッション>の経験を積むことです。みんなでディスカッションをしてみましょう。今回、題材に選んだのは、『ちびくろさんぼ』です。『ちびくろサンボ』が「差別」だと断定され、絶版になったのは、1988年12月から1989年1月にかけてのことでしたから、もう10年前のことになります。最近、『ちびくろサンボ』が書店で再び入手できるようになりました。いったい、『ちびくろサンボ』の「問題」とは、なんだったのでしょうか?一度じっくり考えてみませんか?ゼミ生野老景久君(4年)が問題の背景を説明します。資料を準備します。 |
| 99-8 | 槌田敦『エコロジー神話の功罪』を読む | 1999年11月20日(土)18:00〜 | 神田校舎 55ゼミ | 我が国で環境問題に取り組むひとびとに大きな影響を与え続けている槌田敦教授(名城大学)の著作を読んでみましょう。最近は、地球温暖化問題について、同教授が懐疑的姿勢を保ち続けていることが注目されています。今回の公開ゼミでは、昨年出版された『エコロジー神話の功罪』の第4章をとりあげます。この章は、エントロピー論や物質循環論の立場から、環境問題を考えてゆくという趣旨の章です。学生諸君にとっても、一読の価値があるでしょう。ゼミ生が報告し、そのあと、ディスカッションをしてみましょう。プリント教材を準備します。 |
| 99-9 | アメニティーとは何か? | 1999年12月4日(土)18:00〜 | 神田校舎 55ゼミ | OECDは、1976-77年に、日本の環境政策のレビューを行ないました。アメニティーということばががわが国で環境問題に取り組む多くのひとびとの注目を集めたのは、このレビューの報告書『日本における環境政策』(1977年)においてであったと言ってよいでしょう。この報告書の結論部分に有名なセンテンスがありました。「日本は、汚染の減少をめざした多くの戦いには勝利してきたが環境の質をめざす戦いにはいまだに勝利していない」。ここで、「環境の質」として言及されたのが「アメニティー」なのです。では、アメニティーとは、何でしょうか?考えてみませんか?資料を用意します。資料をここでダウンロードできます。ちょっと、長めですが、最近、こんな論文も書きました。 |
| 99-10 | 「無償労働の貨幣評価」をめぐって(卒論中間報告テーマ) | 1999年12月18日(土)18:00〜 | 神田校舎 55ゼミ | 本ゼミの現4年次生は、「無償労働の貨幣評価」をテーマとしてグループで卒業論文を準備中です。中間報告を聞いてみましょう! |
| 00-01 | 経済学とは何か? | 2000年4月15日(土)18:00〜 | 神田校舎 55ゼミ | 経済学をこれから学ぼうとする諸君、あるいは、もう何年か学んできたけれども、何のために経済学を学んでいるのかさっぱりわからないという諸君に向けたメッセージにしたいと思っています。作間がレクチャーします。あとでディスカッションしましょう。「経済学」の語源である「経世済民」、それから、「経済学は倫理学の侍女である」というピグーの箴言が<鍵>となります。 |
| 00-02 | SNA入門 | 2000年10月21日(土)18:00〜 | 神田校舎7階大学院72教室 | SNAとは何か、知っていますか?国内総生産(GDP)なら、知っているでしょう。SNAは、このGDPを計算する統計、つまり国民勘定統計の国際基準、System of National Accounts 「国民勘定体系」の略なのです。この「国民勘定」とは何かというと、普通の企業会計が企業を対象にして、いろいろな勘定によって、企業の活動を把握するのと同じように、一国経済を対象にする一組みの勘定によって、その活動を記録しようとするものなのです。こうしたことがらは、経済学の一分野である国民経済計算の研究対象となっています。SNAのルーツは、1930年代のケインズの研究にあります。ケインズの研究は、弟子のストーンに受け継がれました。国際連合が、ストーンの指導のもとに、SNAを開発し、発表したのは、1953年のことでした。SNAは、1968年と1993年に改訂され、わが国は、1978年以来、SNAに準拠した国民勘定統計を作成しています。今回の公開ゼミでは、SNAの入門コースを用意してみました。どうぞ、ご参加ください。 |
| 00-03 | 93SNA でどこが変わるのか | 2000年11月11日(土)18:00〜 | 神田校舎7階大学院72教室 | 長い間、わが国の国民勘定統計は、国際連合が1968年に発表した「1968年SNA」あるいは「新SNA」に準拠して、作成されていました。その国民勘定統計の作成基準が「1993年SNA」に切り替えられることが、つい先日、2000年10月27日に決まりました。作間は、国民経済計算調査会議の専門委員として、「93SNA」への移行作業に関わりました。今回の公開ゼミでは、この「93SNA」でどこが変わるのかということを、『日本経済新聞』の記事なども使いながら、簡単に説明してみようと思います。 |
| 00-04 | オギュスタン・ベルク『風土としての地球』を読む | 2000年12月9日(土)18:00〜 | 神田校舎7階大学院72教室 | 「風景」というと、いつでもどこにでもあるものと思いがちですが、そうではありません。西欧では、15、6世紀にならないと風景は存在しません。今回の公開ゼミでは、西欧における「風景」がこのように近代特有の現象であったことを「風景転換」というタームをつくって説明したオギュスタン・ベルク『風土としての地球』(筑摩書房刊)を取り上げます。 オギュスタン・ベルク(Augustin Berque)は、フランスの地理学者、日本学者です。和辻哲郎の有名な『風土』(岩波文庫)から「風土」や「風土性」の概念を摘出し、再解釈することに成功した『風土の日本』(ちくま学芸文庫)をはじめ、『都市のコスモロジー』(講談社現代新書)、『地球と存在の哲学――環境倫理を越えて』(ちくま新書)など、多くの著書があります。 教材として、『風土としての地球』(三宅京子訳、筑摩書房、1994年)をご用意ください。 |
| 01-01 | 経済学とはどのような学問か? | 2001年4月14日(土)18:00− | 神田校舎7階大学院72教室 | 経済学をこれから学ぼうとする諸君、あるいは、もう何年か学んできたけれども、何のために経済学を学んでいるのかさっぱりわからないという諸君に向けたメッセージにしたいと思っています。作間がレクチャーします。あとでディスカッションしましょう。「経済学」の語源である「経世済民」、それから、「経済学は倫理学の侍女である」というピグーの箴言が<鍵>となります。 |
| 01-02 | 市場主義の終焉を告げる英国総選挙'01 | 2001年6月30日(土)18:00− | 神田校舎7階大学院72教室 | 「第三の道」を提唱するブレア党首に率いられる労働党が地滑り的大勝利で政権に返り咲いたのは、1997年の総選挙においてであった。それから4年後の2001年6月7日の総選挙において、労働党は、再び、保守党に圧勝した。今回の公開ゼミでは、ニュースビデオなどを交えながら、今回の英国総選挙の意味を考えてみたい。 |
| 01-03 | 北アイルランド問題を考える | 2001年10月13日(土)18:00− | 神田校舎7号館8階大学院784教室 | 1998年、ブレア政権下で和平合意(グッド・フライデイ合意)が成立しました。和平の達成のために努力したヒュームSDLP党首とトリンブルUUP党首にノーベル平和賞が授与されたことも記憶に新しいと思います。しかし、北アイルランドでは、現在でも不安定な情勢が続いています。今回のゼミでは、問題の根源に遡りながら、この問題を考えてみたいと思います。レクチャーと学部生の報告のあと、ディスカッションをしましょう。 |
| 02-01 | 経済学とはどのような学問か?2002年版 | 2002年5月15日(水)18:00〜 | 神田校舎7号館6階大学院762教室 | 経済学をこれから学ぼうとする諸君、あるいは、もう何年か学んできたけれども、何のために経済学を学んでいるのかさっぱりわからないという諸君に向けたメッセージにしたいと思っています。作間がレクチャーします。あとでディスカッションしましょう。「経済学」の語源である「経世済民」、それから、「経済学は倫理学の侍女である」というピグーの箴言が<鍵>となります。資料(「経済学とはどのような学問か?」法学部経済原論の講義原稿に加筆したものです)をここでダウンロードできます。 |
| 02-02 | デフレの経済学 | 2002年7月24日(水)18:00〜 | 神田校舎7号館6階大学院762教室 | デフレ(物価が継続的に下落する現象)が続いています。デフレでいったい何が問題なのか、どのような対策が考えられるのか?岡野裕介君(本学大学院D3、国際経済学専攻、野口旭ゼミ)が報告します。ディスカッションの時間もあります。 |